七、仏教学の思想
王安石は藏経を熟読していて、仏教の典籍の理論について非常に熟知していた上に、多くの分野で独自の非常に優れた見識があったのだが、残念乍彼の仏教についての著作は多く無いので、其の全貌を垣間見ることが出来難く、彼の残した少しばかりの詩文の中から手懸りを見出すしか無いのだ。
王安石は禅宗を重視して、般若の空についての定見に尤もだという感想を受けていて、機会ある毎に此の面での見解を伝道していたのだ。《更答呂吉甫書》の中で、彼が《金剛経》の「一切の有為法(様々の因縁によって生じ、常に生滅し永続し無い凡ての物事・現象)は、夢幻の泡影の如く、現れたと思ったら一瞬に無くなるのだ」を引用した真意は,「人の身と世の中は、一切夢幻の泡の如く」であると説くもので、人身と世の中の全ては、無常な変幻にあり、『自性』などは無く、故に、空なのだと言うことだったのだ。彼には更に「身は泡沫の如く風の如く、香を刀で切って一空を塗る」や、「諸縁は夢のようなものだ」等の詩句を練って、同様な思想を言い表していたのだ。
《字説》と言う書の中で、王安石は「空」の字に逢ったことで『仏教での死』の解釈を行い、指摘している:「穴には土が無いように空とは実相が無いことで、空とすれば何も手を加えられることは無く作為も無くなるのだ;実相が無く作為も無いならば、空を定義することは意味が無くなるのだ」。《維摩経》の「空とは実相の無いことで、実相が無ければ作為も無い;実相が無くて作為が無くとも、心には働きがあるものだ」と言う一説は、空とは、実相が無く、作為も無いと言うのが諸経で慣れ親しんだ説法であっても、全ての事物・現象の本質が空であれば、其の実相を理解することも出来ず、実相も無く本体も無ければ為す術が無いと言うことになる。王安石は漢字で仏理を説明していて、空とは土が無い穴のようだとするのは、穴とは空っぽとは何も無く、空っぽとは実相が無く、だから空とは実相が無いことなのだ;空であれば現実には何も為されず、全ては元々空なのだから、手の付け様も無いので、如何あっても空では為す術は無く、空には元来作為が無いこととされるのだ;空には実相が無く作為も無いのであるから、痕跡も辿ることが出来無くなり、依って実相も説明し難く、名前も分からずに、作者が誰かも知れず、名も立てることも出来無いのは、元はと言えば空が空であるからで、空とは説明のつくものでは無く、空とは何かということも出来ず、空とは空であるとしか言いようが無いのだ。
王安石は《空覚義周彦真》中で近い思想を著していた:
悟りは空其のものでは無いとは迷うところだが、其のことが悟りには迷があると言われる所以となるのだ;空が悟り其のものでは無いと言うのは、確かなことである。空には元々分から無いことはあるのだが、其の存在は確かである;悟りには元々迷いが無い筈だが、現実として悟っても迷いがあるものなのだ。
空なるものはあらゆる存在(生きとし生けるもの)総ての本質であり、悟りの根源をも為す;悟りとは元々衆生の心にあるものであるから、悟ることが出来るのだ。空で無ければ悟ることも無く、仏教の道理の本質に達することも出来ず、自浄の願いも叶は無いのだが、空の意味は曖昧であるから、悟りと空との違いもはっきりし無くなって仕舞うのだ。悟る過程に全く空が関ら無ければ、本当の悟りとはならず、実際、悟りには到ら無いのだ;空で無ければ最終的な悟りに到ることも無く、悟ったと雖も迷いがあり、拠って、悟りには迷いがあると言われて仕舞うのだ。空が悟りに全く関わり無いとすれば、空を体験することも無く、結局、空と言う概念も無くなって仕舞うのだ;詰る所、空が意識の他に在ったとしても、空は悟りの過程に確実に存在するのだ;空であっても其の存在は確実にあるので、「空は確に存在するものである」と言い切れるのだ。空の本質が空其のものにあるので、確かに空であったとは言い切れず、当然、実態として確認出来無いので、実態のものとして対応していては、空との境目は明確に言い切れ無くなるのだ。
極短い数句の中に在って、王安石が正確に空と悟りとの関係を説明したことは良く知られていて、彼の仏教の理論に対する根本的な理解力を著したものとされた。仏教では衆生が本来は持っている本性は真理としてあるものでは無いとことを「空」と言う概念で説き、其れらの本性と言われるものが不変で恒常的なものと迄とは言い難いとし、根源的に諸法には本性が無いのだとも言い切れず、諸法の根源も空であると強調する同時に陀門も又其れらは感覚や意識に現れるものと認め、此れは飽くまで虚構のものであるとも言い、諸法の根源も空で虚構があると理解し、双方の概念を捨てること無く、其の平均値を採って実相と為したのだ。其処で空は虚無主義と迄は言え無いが、空を全ての「悪趣空」と分けることをせず、空其れ自身にも自我(其れ自身)の否定をも含んでいるものなのだから、空の概念は中々固定化出来無いとしたのだ。《和栖霞寂照庵僧云渺》と言う詩の中で同様な思想を表現している:
世間を離れて寂寞たる環境にあって、楽しみは皆同じで有りえようか? 宴座で老い
を忘れられようとも、精進料理は戴け無い。
仏事をする気があるのかと、客が家風を聞くことがある。笑って西来の意味するところを謂うと、空と雖も空しいとは同じでない。
晩年の王安石が憧れたのは殺風景でもの寂しい禅寺で宴座して精進料理を食べて生活することだったのだ。仏教の戒律には「午後は食べ無い」の決りがあり、詰り、昼から以後の食事は許されないので、依って「精進料理で粗満足する」と言いたかったのだ。仏法は元来求め無いものなので、求めるものを遠ざけるのだ;仏法は本来拘りを無くし、魔がさして、何かを為そうと仏事を行うべきで無く、成仏するように拝んでもいけ無いのだ。家風とは禅門の慣用語で、詰り、門風ことで、宗旨のことを言うのだ。西来と言う意味も、矢張り、禅門の慣用語で、詰り、祖師(達磨)が西から来たと言う意味で、本当の禅門の宗風を指し、仏祖の意志を言うのだ。西来の意味は、空は空虚のことでは無く、空本来の意味を言うのだ。此のことで王安石が仏教の空の意味を的確に把握したと言うことが表明出来、全身全霊で仏教にのめっていたことが分かるのだ。
王安石には更に《与蒋穎叔書》が有り、其の中で伝統の仏教の理論に対する理論を披露したのだ:
永い時間我慢して無いのに、如何してこんなに枯渇の思いに駆られるのか!評判に頼るのでは無く、疑われているところを自身で納得するまで調査してみたのだ。聞いたことがあると思うが、神で無ければ変わるべくは無く、思い通りに変われても、神が特別喜ぶものでは無いと言われている。所謂、仏性とは、四大のことを言うのだ;所謂、無性であれば、経典を見ることも無い。然れども無性であっても、拘りを捨て切ることは無く、無性も性の中であり、其の有無は余り意味が無いのだ。此の見解を通すべきかどうかは、言い難い処であった。無性でさえあれば、変幻は自在である;若し有性ならば、火は水にならず、水は大地にはならず、地は風にはなら無いのだ。長短は一対で、静動も一対でとするが、此れ然し、人にはかくの如く決め付けるべきで無い。言葉の意味と言うものは、両極端を著さなければ中庸を意味するとは限ら無いのだ。故に経で曰く:「現世には無く、彼岸にも無く、中枢にあるものでも無いのだ」。長爪梵志は一切の法は不変として、仏陀が訴えたことを受けようか受けまいかということを、全ての論点としたのだ。若し、生きる術を知っていても心が安定して無いなら、書に著したとしても、非難を浴びることになり、両極端に拘ら無いとしても、『三つ目の言葉』が未だ出て来無かったのだ。若し此のような過程を経て無ければ、此れと言って何もせず、三十六対に手を付けることは無かったのだ。《妙法蓮華経》は此の世の真実で有りの儘の姿の法を説いたもので、其の説も、上記のようなものであったのだ。因って、導師は「安んじて時を過ごし、行いを清め、限界まで行えば、行いは成就する」と言うのだ。芬陀利華と名付ける由来は、色々有るのだが、今日の法師が解釈する意にするものでは無いのだ。仏説では性は有ると説くが、第一義の要諦にあらざること無しとしている。若し、第一義の要諦とするならば、有っても無いと言うことで、無くても有ると言うことになるので、無いとしても様子は有るので、言葉を発する度に気に掛かるのだ。仏法には二法は無い筈なので、一切気に掛けず言い放てば、二法は無いのだと謂うのだが、此れ亦、都合が良く説得するものだ。然し、此のような子供騙しには、二の句を継げないのだ。
此の文は王安石の残した彼の仏教学の思想を纏めて表した比較的に長い一篇を述べたもので、当然重視されるべきものなのだ。彼は此の一首で先ず神変に対して解釈を行って、変化は超人的な力から為されるものであると考えられるからこそ、神変と言われるので、超人的な力を以って為されなければ、変わることが無いと、根拠無く思ったのだが、神掛りが具現されたものとしたのだ。神は仏教を通じて六つの神通力の一つを補足したので、超人的な力が思い通りに働ける場所を得られて、妨げるものは無くなったと説いた。
王安石は更に仏教で言う「有性」や「無性」に対して詳しい解釈を進めたのだ。彼は、地、水、火、風の四大元素は「有性」に属しているが、「来藏」のようなものは「無性」に属するとした。「来藏」が無性に属するとしても、断ち切ることが出来無いのは、何時も一定で不変で、純粋無垢な一つの「性」であるからこそ、一つの「性」を「無性」と言得るのだが、事の是非は兎も角、其の中の道理は、心で理解出来るだけで、言葉で説明することが出来無いのだ。「性」は変化することが無いのは当然で、火は水には変わるべくも無く、水は地に変わるべくも無く、地は風に変わるべくも無いので、「性」は不変なのだ。
仏教には自性を一義にすることに対して違った見解があって、一つ謂われているのは不変と言うことは動か無いことではあるが、不滅と言うことでは無く、正しく自性を完全に一体に解せば、此れは比較的流行の言い方とはなるが、一切世の中の法には全て自性は無いと説くのだが、性は元々空なものなので、世の法全ては縁と結びついているので、生滅は絶えず入れ替わり、実体は無いとするのだ;事物が持っている独自の性を自性と謂うのだが、水は濡れることを性とし、火は暖かいことを性とし、地は硬いことを性にとし、風は動くことを性とするように、全ての事物には他のものとは違う性が有り、然も、簡単に改められるものでは無いのだが、此のことは印度から仏教が伝えられた後に、「有部的薩婆多部」と俗に呼ばれ発展してきた理論で、其々のものは自性を持つとするものなので、「万物には他の性とは違い、独自の性があるのだ。一切の万物は、自性を持っているものなのだ」と言う此の一つの道理に落ち着いたのだ。
王安石の有性無性の説は、明らかに「有部の理論」に対する自分の考えを十分に表明したものであったので、幾つかの宗派の或る種の疑問に応えようとの努力は「空」を一頻り説明することで報われることになった。彼は現実の事物が自性とは無縁であることを認めたが、此れは「有部」の説法でもあったのだが、併し又、性が有ると言うことを認めれば事物の本源の変化や発展を阻害することになるので、或る種の規定の存在を成らしめて、硬直化を招いて仕舞うので、例えば「来藏」に象徴されるように無性こそ自由な変化の可能性が有ることを、自身も経典から読み知っていたので、身を諸仏に近づければ、自由を得始め、上手に優れた腕前を引き出すことも可能で、知らずに変化が出来るのだ。彼からすると、「来藏」のような才能は滅多にあるものでは無いとし、「或る性は性である」とする中道の実体は、有無を遣り過し、有無を超えて思い通りになるものだとしたのだ。
王安石は更に六祖恵能の三十六組についての解釈を進めたのだ。《壇経》によると、六祖恵能が法海に開示し、神会等の十大弟子の時には、「三科法門」、「三十六組」を講義するに到り、彼らに他の人が法について聞く時には「一対の言葉を尽して、全て互いに相反する対を決りとし、結果として二法は除外し尽され、更に行き着くところを無くした」。法相の言語の十二組とは。三十六組の法とは:「環境において無常とする五組とは、天と地の組、日と月の組、明と暗の組、陰と陽の組、水と火の組、此の五組なのだ。言葉として相反する十二組の法とは。有と無の組、有色と無色の組、有相と無相の組、有漏と無漏の組、色と空の組、静と動の組、清と濁の組、凡人と聖人の組み、僧と俗人の組、老と少の組、大と小の組、此の十二組なのだ。自性として起用される十九組とは。長と短の組、邪と正の組、痴と彗の組、愚と智の組、乱と定の組、慈と毒の組、戒と非の組、直と曲の組、実と虚の組、嶮と平の組、煩悩と菩薩の組、常と無の組、悲と害の組、喜と嗔の組、舎と慳の組、進と退の組、生と滅の組、法身と色身の組、化身と報身の組。此の十九組だ」。
六祖は三十六組の法を開示して互いの名を分別だけで無く、「お互いの意味が正反対」であり、「二つの意味は両端に置くが、其れらの間に入る言葉は無い」として、最終的には「日常的、世間的、人間的な認識では相対立して現れる事柄が、仏教の高度な理解においては統一して捉えられ、其の様な認識をもって、更に行き着く処が無い」という結論に達したのだ。六祖は弟子達に無の反対は有かと問い、短の反対は長かと問い、態と相反する回答を与えさせることで、二法に分類することに執着する学者流の遣り方を打破して、三十六組の法の本当の目的が執着を無くすことであることを知らしめたのだ。対語に拘ること無く些かも固執して表現せず、中道にも執着すべきで無く、中道に執着することも執着に変わりは無いとしたのは、悪習を打破する必要があったからなのだ。全く成果を上げられなかったのは、現世に関ることをせず、あの世も悪いものでは無いと、敢えて困難に立ち向かうことを避けたからなのだ。仏陀が長爪梵志に《雑阿含経》の漢訳を点検するように求めていたので、仏陀が王捨城の靈鷲山に居住する時、行脚の途中の長爪が来訪し、お互いに論争を展開したのだ。長爪が自分の意見としては「全くなってはいない」としたのだが、此の見解は揺ぎ無く変えてはなら無いと考えていたにも拘らず、仏陀が問い詰めたのだ:「如何して、貴方は自分の意見として『全くなってはいない』となるのか?」 明らかに長爪の見解には或る種極端な偏見と拘りが在り、相矛盾するところがあったのであって、此のような見解を持っているのに「全くなってはいない」、「或る面では私は認めるが、幾つかの面では私は認め無い」などと言うのは可笑しなことであり、若し自説に拘るならば、争点として論じられなければなら無いのだ。仏陀が長爪に更に教えたことは、笑われようと、苦い思いをさせられようと、三種の経典を授かれば苦しまず笑われることも無くなるので、此の主の経典を授かれば他に何も授かる必要は無いとしても、此れらは総べて因縁と結びついて生じるものとだと感じもあるので、此れも亦常に変化し、永く其の儘であることは無く、授かることに拘ったとしても、授かろうか授かるまいが、如何しても論争は免れ無いのだ。王安石が此の経義についての解釈を進めにつていて、将に《金剛経》の「当然と留まる所無くとも心に其れは生まれるのだ」の文と結び付けて、「当然心に生じても心に留めるべきでは無い」と主張し、一切の拘りを排除して、譬え「二対の句に関ら無い」としても、未だ「三つの文」(仏典の初めの一文、中間の一文、そして最後の一文に拠って経文全てを指し、禅宗が生まれた後には馬祖の三つの文、雲門の三つの文等が有り、此れら全て禅門の伝導装置となったのだ)から外に跳び出すことは出来無かったのだ。仮に拘りを無くせば、総てがあるべきものとなり、三十六組の使い道は無くなるので、三十六組の法への拘りは全く無くなり、最早、拘りさえ無くしさえすれば、三十六組の法を無益なものと為せるのだ。
王安石が《法華経》を非常に重視したのは、取分け、其れが修業を強調し実践と合い結びついていたからだ。《法華経》は実相の法を説くことで知られていたのに、彼が殊更に其の意を言葉で言うことが無かったのは、実践あるのみだと思っていたからだ。経の五巻の《従地湧出品》の第十五には、眼を見張るほどの完成度で見事に釈迦牟尼の仏説の功徳が著されており、彼(か)の国(くに)の諸菩薩が仏陀の滅後も彼等が此の経を保護維持することに仏陀の許しを乞うと、仏陀は躊躇無く「汝ら今からでも始めよ」と奨めたので、此の娑婆には河砂の粒程の多い数の六万全の菩薩がいるので、六万の菩薩の銘々一人々の此の世の全ての河砂の粒程の数に達する家族達迄もが此の経を読んで暗唱して保護と維持に関ろうとして、仏陀の法説がある時は此れを訊くことで、此の世の本来的な姿である遍く存在する本質、存在の究極的な姿としての真理其のものを言う『真如』を得ようと、地から湧き出すように此れらの菩薩と家族達がやって来るのだが、「此れら菩薩と大衆の中にあって、四人の指導者がいて、一名目は上行、二名目は無辺行、三名目は浄行、四名目は安立行と言った。此れらの四菩薩は、其の大衆の中で、最も上座にあって、教えを説き、人を導くのは此れらの師が行った」。此れら四行は上座の菩薩への命名だが、実は四行其のものを説明することの方が重要なのだ。王安石は更に『芬陀利華』の伝統的解釈に関しては不満を表していたのであり、当時、法師が釈明していたような決して狭い解釈で無く、其の中には多重の意義を含まれていると思っていたのだ。『芬陀利華』とは、以前に説明したように、『蓮華』が最盛で最美の時の名のことであると言うことに対して、王安石は全く不満であったが、決して文義を結んで自分の解釈を説明することが無かったのは、修業と結び付いて結論が出てくるものだと想っていたからで、只、実相を重んじ、理論だけを重視することに疑問を持っていたからだ。仏説での有性或いは無性は、全て第一義の諦理(究極の真理)であって、第一義の諦理とは、有るは即ち無く、無いは即ち有り、有るか無いかの境目は無いのだと言うものなのだ。「有る或いは無い」を分ける手立てを普通に推測すると、論争を生む筈だが、仏陀は最上の仏の教えだと言い乍、譬え最善の遣り方では無いとしても、一切言説を以って推し量ることは出来無いもので、此れも一種の方便だと説くのだが、王安石は納得することは無かったのだ。此の様に見事な道理は、只然し、奥が深いものと理解出来るが、言説を尽して達するものと考えたのだ。
王安石は各自が自分の為に用いるように衆に行き渡らせて、「有る、無い」が両端に立つことが無いことを完全に理解させることを通じて、二端は両立し無いことを中途半端にしなければ、そうすることで執着を無くすことを達成出来、執着が無ければ絶対的な自由を享受出来、無であるものも至る所に存在することになり、こうしたことが、彼自身が本当に追い求めたかったことだったのだ。
王安石は更に《答蔡天启書》中で『同生基』の問題を論評した:
何某かが申し述べた:近く書に付け加えて、完成させたい。日を追うにつれて如何なるものか?日々切望するが旨く行か無い。書で『同生基』の知識を得て色めき立ったが、凡そ次のようなものだった。所謂まるで野生の馬のように、悩める者をきらきらと光り輝くように清めようと、日の光が差込んだ思いであった。人々が精氷に集めることを知って、此の身を達したのだ。人々が想う蘊には、日の光に拠ること無く、何も見え無いのだ。暗闇の儘でいることを想い、せめて心に光をと発奮すれば、日の光が無くとも、ものが見えるのだ。此れこそ『同生基』と言うものだ。未だ遭遇することが無くとも、人の道を外さず自重するのだ。数々の書を見るに及び、教えを尊び日々比べて安寧を想い、未だ至らずと書を為す。
『同生基』については、出所は不明で、創ったのが宋人と繋がらず、由来は別に矢張りあり、文義からすれば、『阿頼耶識』を思い出す。『阿頼耶職』は別名を『藏職』と言いうが、全ての物事には由来が有り、慣習を燻すと一切のものが善悪の種を産むと言え、其れを『同生基』と言ったのだ。仏教には八識義と言うものがあり、即ち、目識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識、末那識、阿賴耶識、前五識は主に感覚に関わるもので、第六識詰り意識は通常の意識が現れると言ったものに近く、第七の末那識は自己の意識或いは主体的意識のことで、第八の『阿頼耶識』は諸々の『識』の根本を為すもので、『蔵識』には前の七識を含んでいるのだと、密に俗世間では言われている。『阿頼耶識』と『色』は対応するもので、『色』で無ければ『色』で無く、『色』で無ければ『識』で無いとされているので、『識』は『色』と関ってこそ成り立つものなのだ。
『同生基』の一段は、《楞厳経》の十巻から出典したものである。原文は蘊に思いを尽すと謂うもので、「生滅は根源のことだと、此れから披露する。十方十二衆生に諸々見られるのは、畢殫(生涯を尽す)という其の類のものである。各々の命には其の時に至る迄の道筋があると未だ分かって無いとしても、『同生基』に出会うと、野性の馬のように、邪魔なものが清められきらきらと光り輝き、仏教の六根と六塵との究極の障害を浮かび上がらせ、此れ即ち『行陰区宇』と言うのだ」。意味は五蘊の中で蘊を想い尽くした後には、滅根が生じるので、此のことから披瀝されることは、あらゆる方面での各種の衆生に特有な本質を(これが次の目標だ)を未だ尚十分には分から無かったにも拘らず、其れらの生命の根源に共通するもの、詰り、其の共通性に達することが出来て、其の本質までは分から無くとも、此の共通性こそ『同生基』であるとして、実は蘊への知識を広めるのだ。同生基は野生の馬のように自由に彷徨する気質のもので、光り輝き煌めいて、消えて無くならずに生き続け、揺れ動き絶えず変わる六根の此の世の六つの煩わしさの根源でもあり、蘊の中核を為すものなのだ。長水子璿の《首厳経義疎註経》巻十の一つで「同生基に出会う者は、同分生基即ち行蘊にも会うのだ。十二品類は、行蘊(意志作用)に依って其の根源を為すのだ」。
【注釈】五蘊:〔「蘊」は梵語の訳で、集まったものの意〕諸存在を構成する物質的・精神的五つの要素。色・受・想・行・識の総称。色は物質的存在、受は事物を感受する心の働き、想は事物を思い描く心の働き、行は心の意志的働き、識は識別・判断する心の働き。五陰。五衆。
根: 感覚器官など、一定の機能・能力を有するもの。
王安石は、蔡天が「同生基が色(物質的な存在)からの而立(じりつ)の観点に従うよう」に申し述べたことに賛同した。五蘊の中で、色蘊は物質的な要因に拘るもので、受・想・行・識の四蘊は色とは而立するもので、精神的な事象の要因に関るものである。王安石は『同生基』が矢張り『蘊』である行蘊に属するものだとは決して明確に言うことは無かったが、但併し、「精氷に相当するものだと知って、此の身が成り、……此れ即ち所謂『同生基』なり」と言う意見を述べるに至り、漸く『蘊』とは『同生基』と知るに至ったと説明したとも取れるのだ。野生の馬の類の蜃気楼は滅多に見られるものでは無く、雲の切れ目から入って来る一筋の陽光を通じて、其れらがちらちらと消えてはぱっと光り輝き、漸く引切り無しに動き回っているのを見ることが出来るものなのだ。衆生も亦然り、両親の精が偶然に一致して此の身が生ったのであるが、其の様子は冷厳だが、堅牢では無く、日の光によって初めて見ることが出来るのだ。其処で、衆生が悟りを開く時に初めて諸仏や菩薩或いは『大善知識』が外縁(外から力を与えて物の生起を助ける要因)を為して教え導くのであり、慧日の仏光に依らなければ、不安な陰を完全に取り除くことが出来ず、諸法の本性を見極めることも出来ず、悟りへの道は得難く為って仕舞うのだ。一旦すっかり不安を取り除けると想えば、二つの障害(煩悩の障害、知ることの障害)全てを取り除け、自分の心に光を取り戻し、本覚(本来の悟り)への知恵の兆しが現れて、更に外界の日光菩薩に頼る必要も無くなるのだ。此の事態に至って、漸く、本当の『同生基』に出会うことが出来、法の根源を知り得るのだ。見た処、王安石は外縁(外から力を与えて物の生起を助ける要因)の助力を重視するのだが、併し、最も強調したのは矢張り意識的な悟りであって、此のことは仏教、特に禅宗の目的に適うものだったのだ。
王安石は般若の『空』の意味を重視するけれども、『仏性』については『来藏』の学説と同様に深い研究があった。其処に至る迄には努力があったのだ。彼は先ず外縁を示すことで不安を打ち破れるのだとし、不安を克服すると、本当の意味で空などの仏教の真理に即せば、正しく物事を認識し判断する能力が養われ、此の真実の悟りの光に依って自身と一切の諸法の実相を知ることが出来るので、仏教典の如くに自身の方便を解き放って真実を顕示すれば、其れに依って本質から成仏出来るとしたのだ。修行の為の方法論については、彼は妄りな心を洗って取り除くことを主張していて、「因習を削り取り」、煩悩の悪弊を削り取り払って浄化すれば改めて始めなければなら無いことなど何も無く、見た処、北宗の神秀の「払い拭って穢れが無い」に相近く、南宗の「真を求めず、妄を断たず」とはかけ離れた見識をもっていたのだった。
王安石は伝統的な仏教の考え方について深く会得したものがあったのだが、だからと云って、彼は決して満足し無かったのであり、彼は百家の書を読み尽くして広い知識と優れた理解力で彼の熾烈な批判の精神と際立った個性の意識を人が真似することが出来無い速さで覚性させたのだが、彼は飽く迄仏教を基礎にして、一貫して諸家の思想と融合させ、彼一流の思想的体系を成したのだ。《寓言》三首の中で、彼は禅宗の幾つかの不正な行為に対しても批判を行っていたのだ。
其の一として
宇宙万物の根源は実際追い求められるべくも無いが、松の枝から葉落するのは古今の事実であるのだ。
桃花を見て悟りを開いたが、未だ自ずと疑念が涌くのだ。
《祖堂集》の十九巻には、霊雲は潙山の霊祐の弟子として志勤した、福州人で、初め潙山の不契に参じて、「春に偶々花蕊の咲き乱れる花を見て、突然、悟りが開けたが、余り喜ぶことが無く、一喝を作って曰く:三十年来剣客を探し続けて来たことは、花が芽を出す度に枝を伸ばすようであった。桃の花に会った後には、桃花を一目眺めてからは、漸く迷いが無くなったのだ」。
牛(にゅう)頓(とん)が林檎の落ちるのを見て万有引力の法則を発見したように、如何して桃花に出会うことで霊雲が道を悟ることが出来たのかは、他人には理解し難いことであった。
王安石からすると、宇宙万物には実質は無く、果てし無いもので、あらゆる存在は総て実体が無く空であり、全て宇宙万物に等しく、物を観ることで解脱を感じ、花で悟りを得ることになったと言うが、見たところ、此れだけでは恐らく最高の境地になる筈は無く、所謂疑うこと無く、間違い無く懐疑に値するのだ。此処で、王安石が禅宗の大家の霊雲に対して道を悟ったことに懐疑の意を示していたことで、彼が批判の心を持っていたことが分かるのだ
其の二として
元来無常だと人に疑わせていては、参禅は全く馬鹿馬鹿しいものにさせるのだ。
無常を通して法を説けるかと自問し、面壁して終日心乱れて自問する。
六祖恵能は真理としての「本来一物も無い」と言う偈の一文によって、法性(存在の本質)には本来何も無いのだと説明して、実在は存し無いとした人だった。無常は禅門で常識的に言われていた説法の手法で、六祖の弟子の南陽の慧忠国師が《華厳経》から引用した無常の説法をしても、世間の人には理解が得られず、其の後、洞山の良価は潙山と霊山に問うたが、雲岩は反省して同意し、偈を呈して曰く:「大きくて珍しくて、大きくて珍しくて、無常の説法は思いも拠ら無いものだった。声が聞こえても姿を現さ無いならば、目は音が聞こえる方に自ずと向くものなのだ」。壁に面した儘とは学ぼうとし無いという意味であったが、爾後、禅宗では達磨祖師が壁に向かって禅を参じてからは、壁に面する法門を創立したのだ。如何しても気になる典故を理解しようと、石頭は六祖恵能の最後の弟子に成ることを望んでいたのだが、恵能が亡くなった時には彼は未だ年幼であったので、六祖が臨終の間際で「行くことを考えてみよ」と言ったのだが、彼は其意が分からず、其れ以降の日々苦慮し続けたが、結局、理解することが出来ず、先生の言葉の意味を大兄弟子に聞くと「別に面壁で苦しい思いもせずとも青原行思を尋ねて行け」と言ったのだと教えられたので、彼は漸く忽然と大な理解を得て、其の後に漸く青原から法を得ることが出来たのだ。
王安石は数典を連用して、本来無物であると説明して人に怪しまれたのに、参禅して疑いを晴らそうとしたのに更に愚かしくい迷いを増して、疑惑の念を再び大きくして仕舞ったのだ。無常とはちょっと聞いただけで説明し切れるものでは無く、毎日壁に向かって法を聞き、百般を量って較べて、よくよく思い考えても、道は益々遠く離れて仕舞うのだ。彼は其れ故、禅宗の宗旨として禅客に参禅すること只求めることを無駄なことだと風刺して、此のようなことは禅では出来無いだけで無く、もっと大きな障害を生んで仕舞うだけだとしたのだ。
其の三として
未だ根源に達せずに本筋を得られず、真照の無知と言う言葉まで待つ必要があるのだろうか!
枯木と岩を前にして猶も道を失って、そんなことで春の武陵原に入れようか!
禅宗は元々面目ばかりを重んじて、本筋に帰ると主張したものとして、三祖僧璨は《信心銘》で「宗旨を本来の場所に帰すのに、照に従って宗旨を失う」と言う文を載せていた。 「真照の無知」とは僧肇の《般若無知論》の意味する処のものであって、「真照」は般若で生まれ、拠って、般若を知ら無ければ「真照」も分から無いので、「真照」とは説明し難いもので、互いに訳も分からずに意見を交わしていたのでは宗旨も見失うので、「真照」を知らずとも宗旨を得られるのだ。安禅師には「枯木と岩を前にして道が多く分かれていて、此処に到って人の歩みは悪戯に手間取るのだ」との文があり、冬には全ての樹木は物寂しく、目障りなものは無い筈なのだが、此の期に及んでも猶も迷うのだが、春日の花木は盛んであり、木に青葉が茂って出来る日陰は天の武陵原に迄繋がっているか?王安石は此れに依って根源に達することが叶は無い情況の下では出来るだけ謹んで本分を守り切る方が良いのだと説明して、知ら無いことは言わず、欲張って求めず、道を離れれば益々遠くなるので、迷って見失は無いようにするのだが、此れらは大凡当時流行した「文章での糾弾」を用いた或る種不満の表明だったのだ。
王安石は可也の自信を持っていたが、彼は流行っていた禅宗の悪弊に対して批判を行っただけでは無くて、同様に、古代の法師の経典の説明に対して不満の意を表して、彼は自分の努力で完全に理解した三つの教えを通じて、独自に理路整然とした理論を創説したのだ。彼の《字説》では、彼の経典の注釈と各種の詩文全てを通じて此れらの努力を表明していたのだが、残念乍後世に著作を伝えるものが少な過ぎて、其の全貌は知り得無いのだ。
「第十巻(完結巻)」に続く











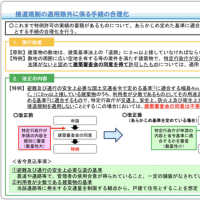






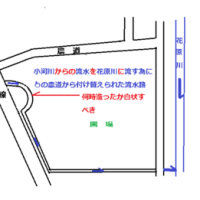

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます