函館旅行最終日。函館市街地からちょいと東側へ行ったところにある志苔館へ行ってきました。
志苔館は14世紀後半頃に、倭人領主である小林氏によって建てられた居館です。道南地域に建てられた同様の他の館とともに、「道南十二館」のひとつにも数えられています。
松前藩の歴史書「新羅之記録」によると、1512年にアイヌとの間で起きたコシャマインの戦いに敗れて陥落。ほどなく廃館になったと推定されています。
現在は国の史跡に指定されており、続日本100名城にも選定されています。

この日は朝から小雨というか霧雨。前日までの暑さとは打って変わり、涼しい一日となりました。函館山にも雲がかかっています。
志苔館は函館駅から東に8.5㎞ほど。さすがに歩いていくには遠いので、函館駅前から出ているバスで移動。本数は少ないのですが、行きは適当な時間のバスが出ていて助かりました。

というわけで、最寄りのバス停「志海苔」で下車。ちょっと漢字が違っていますが、志苔館は函館市志海苔町にあります。

バス停から歩いてすぐのところに志苔館はあります。

入口付近に、志苔館の和人殉難御霊、阿伊努(あいぬ)悵魂御霊の慰霊碑があります。コシャマインの戦いによる犠牲者が、倭人とアイヌと両陣営ともに一緒に祀られています。御祭神として志苔館の小林氏の人たちが祀られ、アイヌの人たちも合祀された後に、他の館の人たちも御祭神として祀られているようです。
ただ、門が閉められていて、中に入ることはできませんでした。


志苔館入口にある碑と案内板。

正門に回った辺りに東屋があります。続日本100名城のスタンプもここに置いてあります。

スタンプの図案は志苔館を上空から見た様子。あんまり凝った構図より、こういうシンプルなやつの方が好きですね。

正門の土塁を登っていく階段。

土塁の奥には空堀があり、橋が架かっています。
その奥に見えるのが居館の本体。空堀+土塁で四方を囲まれています。入口にはかつては門があったようです。

これは居館外側の空堀。さすがに昔はもっと深かったと思います。

これは居館の土塁とその手前の空堀。

館の中に入る前に、道が付いていたので土塁を南へ回り込んでいきます。


そのまま進んでいったのですが、だんだん道が悪くなっていったのでほどほどの所で引き返します。昨日からの雨で下草が濡れていて、歩くと足元が結構濡れちゃいますしね。

正門に戻り、館の中へ。



とはいえ、四方を土塁に囲まれているだけで、中は広場になっており、いくつかの碑と案内板がある他には、ほぼなにもありません。

一応、何があった場所なのかを示すものは設置されています。

館内では陶磁器類、金属製品、石製品、木製品など、いろいろな遺物が出土しています。

北側の土塁に登って。
右側が館内、左側が館の北側になっています。

土塁の上から館内を見下ろして。

館内部でほぼ唯一のわかりやすい遺構である、井戸跡があります。

東側の土塁から、館の東側を見下ろして。

南側の土塁から、函館山方面を望んで。

これはすぐ近くにある、志海苔漁港。


志苔館内部をあちこち眺めて。
志苔館には土塀とその周辺の堀跡が見事に残っています。ただ、正直、あまり見るところは多くないです。なるべくじっくりと見て回りましたが、30分くらいが限界でした。
帰りはバスの時間が合わなかったので、函館市電の湯の川駅まで3.5㎞ほど歩いてい行きました。

志苔館はすぐそばに函館空港があるので、飛行機が頻繁に離着陸していました。飛行場に隣接して、空港を見学できる展望広場がありました。


展望広場には飛行機と滑走路を模した池が設えられています。



時間に余裕があったので、しばらく飛行機を眺めていました。

最後に、函館駅近くにある、「函館市青函連絡船記念館・摩周丸」へ。
青函連絡船として活躍した摩周丸の内部で、青函連絡船関連の展示がなされています。






函館駅前にあった郵便ポスト。

旧函館駅所在地と、0マイル地点の記念碑。
これにて函館旅行は終了。夏休み期間中でしたが、思っていたほど人込みは気になりませんでしたね。ただ、やっぱり暑さがきつかった。やっぱりお盆期間の旅行は控えるべきかなぁ。
今回、緯度を上げてもあまり涼しくならなかったので、次は標高を上げる方向で試してみようかしらん。北アルプスとかまでは行くつもりはないけれど、霧ヶ峰とか美ヶ原くらいなら夏でもそれなりに涼しく歩けるかも。
志苔館は14世紀後半頃に、倭人領主である小林氏によって建てられた居館です。道南地域に建てられた同様の他の館とともに、「道南十二館」のひとつにも数えられています。
松前藩の歴史書「新羅之記録」によると、1512年にアイヌとの間で起きたコシャマインの戦いに敗れて陥落。ほどなく廃館になったと推定されています。
現在は国の史跡に指定されており、続日本100名城にも選定されています。

この日は朝から小雨というか霧雨。前日までの暑さとは打って変わり、涼しい一日となりました。函館山にも雲がかかっています。
志苔館は函館駅から東に8.5㎞ほど。さすがに歩いていくには遠いので、函館駅前から出ているバスで移動。本数は少ないのですが、行きは適当な時間のバスが出ていて助かりました。

というわけで、最寄りのバス停「志海苔」で下車。ちょっと漢字が違っていますが、志苔館は函館市志海苔町にあります。

バス停から歩いてすぐのところに志苔館はあります。

入口付近に、志苔館の和人殉難御霊、阿伊努(あいぬ)悵魂御霊の慰霊碑があります。コシャマインの戦いによる犠牲者が、倭人とアイヌと両陣営ともに一緒に祀られています。御祭神として志苔館の小林氏の人たちが祀られ、アイヌの人たちも合祀された後に、他の館の人たちも御祭神として祀られているようです。
ただ、門が閉められていて、中に入ることはできませんでした。


志苔館入口にある碑と案内板。

正門に回った辺りに東屋があります。続日本100名城のスタンプもここに置いてあります。

スタンプの図案は志苔館を上空から見た様子。あんまり凝った構図より、こういうシンプルなやつの方が好きですね。

正門の土塁を登っていく階段。

土塁の奥には空堀があり、橋が架かっています。
その奥に見えるのが居館の本体。空堀+土塁で四方を囲まれています。入口にはかつては門があったようです。

これは居館外側の空堀。さすがに昔はもっと深かったと思います。

これは居館の土塁とその手前の空堀。

館の中に入る前に、道が付いていたので土塁を南へ回り込んでいきます。


そのまま進んでいったのですが、だんだん道が悪くなっていったのでほどほどの所で引き返します。昨日からの雨で下草が濡れていて、歩くと足元が結構濡れちゃいますしね。

正門に戻り、館の中へ。



とはいえ、四方を土塁に囲まれているだけで、中は広場になっており、いくつかの碑と案内板がある他には、ほぼなにもありません。

一応、何があった場所なのかを示すものは設置されています。

館内では陶磁器類、金属製品、石製品、木製品など、いろいろな遺物が出土しています。

北側の土塁に登って。
右側が館内、左側が館の北側になっています。

土塁の上から館内を見下ろして。

館内部でほぼ唯一のわかりやすい遺構である、井戸跡があります。

東側の土塁から、館の東側を見下ろして。

南側の土塁から、函館山方面を望んで。

これはすぐ近くにある、志海苔漁港。


志苔館内部をあちこち眺めて。
志苔館には土塀とその周辺の堀跡が見事に残っています。ただ、正直、あまり見るところは多くないです。なるべくじっくりと見て回りましたが、30分くらいが限界でした。
帰りはバスの時間が合わなかったので、函館市電の湯の川駅まで3.5㎞ほど歩いてい行きました。

志苔館はすぐそばに函館空港があるので、飛行機が頻繁に離着陸していました。飛行場に隣接して、空港を見学できる展望広場がありました。


展望広場には飛行機と滑走路を模した池が設えられています。



時間に余裕があったので、しばらく飛行機を眺めていました。

最後に、函館駅近くにある、「函館市青函連絡船記念館・摩周丸」へ。
青函連絡船として活躍した摩周丸の内部で、青函連絡船関連の展示がなされています。






函館駅前にあった郵便ポスト。

旧函館駅所在地と、0マイル地点の記念碑。
これにて函館旅行は終了。夏休み期間中でしたが、思っていたほど人込みは気になりませんでしたね。ただ、やっぱり暑さがきつかった。やっぱりお盆期間の旅行は控えるべきかなぁ。
今回、緯度を上げてもあまり涼しくならなかったので、次は標高を上げる方向で試してみようかしらん。北アルプスとかまでは行くつもりはないけれど、霧ヶ峰とか美ヶ原くらいなら夏でもそれなりに涼しく歩けるかも。










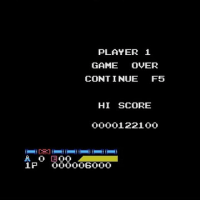

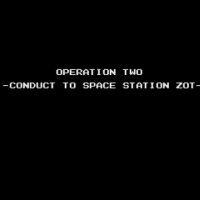












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます