5月下旬に、神奈川県横浜市にある小机城へ行ってきました。
小机城が築城された正確な時期は分かっていませんが、山内上杉氏によって築城されたとされています。
1478年に長尾景治が反乱を起こした際、景治に味方した矢野兵庫助らが城に立てこもりましたが、太田道灌によって攻め落とされています。
その後、上杉氏が後北条氏の台頭によってこの地を奪われた後に廃城となりましたが、1524年に修復されて笠原信為が城主として入ります。ただ、秀吉の小田原攻めの際にここで戦があったという記録はなく、後北条家に替わって徳川家が武蔵に入ると廃城となりました。

前の記事でも書いたように、いろいろなところに寄りながら、小机城までたどり着きました。
現在、小机城は、「小机城址市民の森」となっています。実際の小机城址はもう少し広いのですが、南北に走る第三京浜と、東西に走るJR横浜線によって敷地が分断されてしまっています。

城跡への入口は、市民の森の南側にあります。

いくつか案内板がありますので、それに従っていけば入口となる根古谷広場に着きます。

根古谷広場に地図がありますので、参考にしましょう。
私はこの写真を撮っておきながら、きちんと参照しなかったために、一部行けなかった場所もありました。


両脇に竹林の広がる坂を上っていくと、目の前に大きな空堀が現れます。


この空堀が、幅も深さもかなりの規模で、なかなかの迫力です。
空堀を回り込んで、右(東)へ行けば二の丸広場、左(西)へ行けば本丸広場に出ます。ここでは便宜上、本丸、二の丸と表記されていますが、どちらもそれなりに大きな郭で、実際にどちらが本丸だったのかははっきりしていないそうです。
まずは二の丸広場へ向かいます。

空堀を東側から眺めた様子。

二の丸広場の手前に井楼跡の標識があります。
ただ、跡っぽいところは見られません。

その近くには櫓台もあります。
左側の階段を上っていったところに櫓があったようです。

その先にある広場が二の丸かと思ったのですが、根古谷広場にあった地図によると、この辺りが井楼跡となっています。
まあ井楼があったのかもしれませんけど、さっきあった櫓台の方が高さがあるし、こんなにすぐ近くに役割の被る施設を建てるものですかねぇ?

その奥に二の丸広場があります。

二の丸広場の奥には下りていく階段があります。ここを下りていくと城跡の北側にある空堀の底へと通じています。
空堀に下りるのは後回しにして、本丸広場へと向かいます。

本丸と二の丸の間にも空堀があり、土橋で連絡しています。

土橋の手前にも櫓台跡があります。多分、この櫓台跡が小机城内で一番高い位置に当たります。

土橋の上から、空堀を眺めて。


土橋を渡っていくと、本丸広場に出ます。
ずいぶんとだだっ広いスペースになっていますね。本丸広場の南側には復元された冠木門もあります。

この本丸広場にあった縄張り図が、小机城の構造を理解する上ではわかりやすくなっています。

本丸から南へ行くと根古谷広場の方に戻るのですが、そちらではなく、この案内板にある富士仙元を目指します。

ただここで、地図をきちんとチェックしていなかったために、ちょっとミスをしてしまいました。
富士仙元の方へ歩いていくと、道はどんどん下って行って、小机城市民の森入口近くの民家まで出ちゃったんですよね。途中分かれ道もなかったし、富士仙元ってどこだったんだろう? と疑問に思いながら、また本丸広場まで戻ってしまいました。
どうやら富士仙元へ行くには、一回民家まで出た後、第三京浜の下をくぐって西の方へ行かなくてはならなかったようです。これ、根古谷広場にあった地図をちゃんと見ていればわかったことなのですが、民家に出た段階で城跡はもうおしまいだと思ってしまいました。いかんですなぁ。

最後に、本丸広場の北側から、空堀へと下りていきます。

空堀の底から。
右側の上の方が二の丸広場となっています。かなり深くて広い空堀です。
左側にも土塁が築かれています。

根古谷広場から上がっていく辺りもそうでしたけど、小机城址は竹が多く生えています。
わざわざ孟宗竹の説明もあったのですが、孟宗竹が日本に広まったのは江戸時代だそうなので、小机城が現役だったころには竹は生えていなかったと思います。

空堀をずっと東へ歩いていくと、二の丸広場に上がっていく階段が現れます。

二の丸広場から根古谷広場へと戻る通路から下を見ると、腰曲輪っぽい跡もあります。

小机城址市民の森を出ると、その南に横浜線が走っています。
横浜線の向こう側は高台になっていますが、本来はその辺りも小机城の一部でした。

小机駅へ向かう途中、東側から小机城址を眺めて。

最後に、小机駅近くにある横浜市城郷小机地区センターで、続日本100名城のスタンプを押しました。
ちょっと、どこを表現しているのかわかりにくいのですが……。左の方にあるのが、北側の空堀から本丸広場か二の丸広場辺りに上っていく階段ですかねぇ? いや、根古谷から上がっていく道? 割と似たような風景が多かったから、いまいち自信がありません。
間違えて、上下反対に押してしまったのはご愛敬。
小机城はけして大きな城とは言えませんし、歴史的にもそれほど大きな役割を果たしたわけではありません。それでも空堀をはじめ、郭跡、土塁など、遺構が多く残っており、とても楽しめました。
都心に近くてアクセスしやすいのに、人もそんなに多くない。続100名城の中でもどちらかと言うと地味な城だと思っていましたが、見どころがコンパクトに詰まっている隠れ家的な良城跡ですね。割とお気に入りです。
小机城が築城された正確な時期は分かっていませんが、山内上杉氏によって築城されたとされています。
1478年に長尾景治が反乱を起こした際、景治に味方した矢野兵庫助らが城に立てこもりましたが、太田道灌によって攻め落とされています。
その後、上杉氏が後北条氏の台頭によってこの地を奪われた後に廃城となりましたが、1524年に修復されて笠原信為が城主として入ります。ただ、秀吉の小田原攻めの際にここで戦があったという記録はなく、後北条家に替わって徳川家が武蔵に入ると廃城となりました。

前の記事でも書いたように、いろいろなところに寄りながら、小机城までたどり着きました。
現在、小机城は、「小机城址市民の森」となっています。実際の小机城址はもう少し広いのですが、南北に走る第三京浜と、東西に走るJR横浜線によって敷地が分断されてしまっています。

城跡への入口は、市民の森の南側にあります。

いくつか案内板がありますので、それに従っていけば入口となる根古谷広場に着きます。

根古谷広場に地図がありますので、参考にしましょう。
私はこの写真を撮っておきながら、きちんと参照しなかったために、一部行けなかった場所もありました。


両脇に竹林の広がる坂を上っていくと、目の前に大きな空堀が現れます。


この空堀が、幅も深さもかなりの規模で、なかなかの迫力です。
空堀を回り込んで、右(東)へ行けば二の丸広場、左(西)へ行けば本丸広場に出ます。ここでは便宜上、本丸、二の丸と表記されていますが、どちらもそれなりに大きな郭で、実際にどちらが本丸だったのかははっきりしていないそうです。
まずは二の丸広場へ向かいます。

空堀を東側から眺めた様子。

二の丸広場の手前に井楼跡の標識があります。
ただ、跡っぽいところは見られません。

その近くには櫓台もあります。
左側の階段を上っていったところに櫓があったようです。

その先にある広場が二の丸かと思ったのですが、根古谷広場にあった地図によると、この辺りが井楼跡となっています。
まあ井楼があったのかもしれませんけど、さっきあった櫓台の方が高さがあるし、こんなにすぐ近くに役割の被る施設を建てるものですかねぇ?

その奥に二の丸広場があります。

二の丸広場の奥には下りていく階段があります。ここを下りていくと城跡の北側にある空堀の底へと通じています。
空堀に下りるのは後回しにして、本丸広場へと向かいます。

本丸と二の丸の間にも空堀があり、土橋で連絡しています。

土橋の手前にも櫓台跡があります。多分、この櫓台跡が小机城内で一番高い位置に当たります。

土橋の上から、空堀を眺めて。


土橋を渡っていくと、本丸広場に出ます。
ずいぶんとだだっ広いスペースになっていますね。本丸広場の南側には復元された冠木門もあります。

この本丸広場にあった縄張り図が、小机城の構造を理解する上ではわかりやすくなっています。

本丸から南へ行くと根古谷広場の方に戻るのですが、そちらではなく、この案内板にある富士仙元を目指します。

ただここで、地図をきちんとチェックしていなかったために、ちょっとミスをしてしまいました。
富士仙元の方へ歩いていくと、道はどんどん下って行って、小机城市民の森入口近くの民家まで出ちゃったんですよね。途中分かれ道もなかったし、富士仙元ってどこだったんだろう? と疑問に思いながら、また本丸広場まで戻ってしまいました。
どうやら富士仙元へ行くには、一回民家まで出た後、第三京浜の下をくぐって西の方へ行かなくてはならなかったようです。これ、根古谷広場にあった地図をちゃんと見ていればわかったことなのですが、民家に出た段階で城跡はもうおしまいだと思ってしまいました。いかんですなぁ。

最後に、本丸広場の北側から、空堀へと下りていきます。

空堀の底から。
右側の上の方が二の丸広場となっています。かなり深くて広い空堀です。
左側にも土塁が築かれています。

根古谷広場から上がっていく辺りもそうでしたけど、小机城址は竹が多く生えています。
わざわざ孟宗竹の説明もあったのですが、孟宗竹が日本に広まったのは江戸時代だそうなので、小机城が現役だったころには竹は生えていなかったと思います。

空堀をずっと東へ歩いていくと、二の丸広場に上がっていく階段が現れます。

二の丸広場から根古谷広場へと戻る通路から下を見ると、腰曲輪っぽい跡もあります。

小机城址市民の森を出ると、その南に横浜線が走っています。
横浜線の向こう側は高台になっていますが、本来はその辺りも小机城の一部でした。

小机駅へ向かう途中、東側から小机城址を眺めて。

最後に、小机駅近くにある横浜市城郷小机地区センターで、続日本100名城のスタンプを押しました。
ちょっと、どこを表現しているのかわかりにくいのですが……。左の方にあるのが、北側の空堀から本丸広場か二の丸広場辺りに上っていく階段ですかねぇ? いや、根古谷から上がっていく道? 割と似たような風景が多かったから、いまいち自信がありません。
間違えて、上下反対に押してしまったのはご愛敬。
小机城はけして大きな城とは言えませんし、歴史的にもそれほど大きな役割を果たしたわけではありません。それでも空堀をはじめ、郭跡、土塁など、遺構が多く残っており、とても楽しめました。
都心に近くてアクセスしやすいのに、人もそんなに多くない。続100名城の中でもどちらかと言うと地味な城だと思っていましたが、見どころがコンパクトに詰まっている隠れ家的な良城跡ですね。割とお気に入りです。










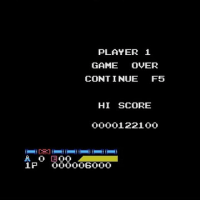

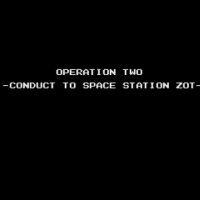











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます