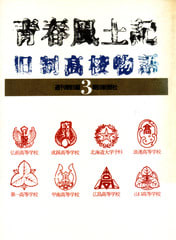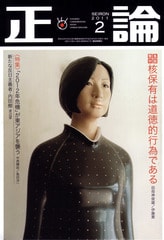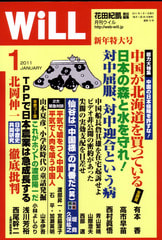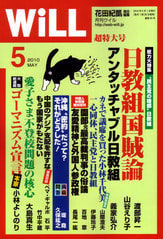フジテレビ制作の時代劇・鬼平犯科帳(中村吉右衛門主演)第1シリーズは平成元年(1989)7月にスタートした。私が僻地に流刑となって半年以上が過ぎていたが、出来ることなら文化都市広島へ戻りたいという気持ちに変わりは無かった。退屈という責め苦にもだえていた大学3年生を救ってくれたのが、このテレビドラマであった。名作と言われる第二話・本所桜屋敷から見始めたと記憶する。
若き長谷川平蔵と道場で腕を磨いていた岸井左馬之助(江守徹)が淡い恋心を抱いたおふさ(マンキュウ)が何と悪女に変わっていたという話で、時の流れの残酷さが主題であった。平蔵の密偵(お上の犬と蔑まれた元盗人達)へのさり気ないやさしさやエンディングテーマがジプシー・キングスの「インスピレーション」だった(原作者の池波さんもこの曲は気に入っていたらしい)こともあり、鬼平シリーズにどっぷりとはまった。
傑作時代劇を更に楽しむために出版された実録『鬼平犯科帳のすべて』には罪人の捕縛・取調・仕置について詳しい記述がある。中でも黒木喬氏の小論文は凶悪火付け犯を例にとって江戸の治安維持の仕組みを丁寧に説明しており資料的価値が非常に高い。
火災都市 江戸の放火と火刑 *火盗改の取り締まりにもかかわらず頻繁に起きた江戸の火災と火刑の実態は? / 黒木 喬
明和九年(一七七二)の江戸。…二月二十九日…目黒村行人坂の大円寺で出火があったのは午後一時すぎである。…大火が終息したのは翌三十日の午後一時ごろである。
この大火で焼失した町は九百三十四、大名屋敷百六十九、橋百七十、寺院三百八十二、死者一万四千七百人、行方不明四千六百人、明暦三年(一六五七)の振袖火事以来の大火といわれた。
四月二十二日に放火犯が逮捕された。…武州熊谷長五郎坊主真秀という悪党であった。幼少から武家奉公をしていたが、十四歳の時、屋敷の塀に放火し、衣類を盗んで在所に逃げ帰ったが、勘当されて江戸に出た。願人坊主…になったが、ほどなく破門されて無宿人の群に入った。無宿仲間と追はぎ・強盗など悪のかぎりを尽くしたという凶悪犯である。長谷川平蔵は吟味がむずかしいので、町奉行所に引き渡したいと上申した。だが、老中松平右近将監武元は、…重々不届至極に付、町内引廻し、五ヶ所に科書捨札を建て火罪を申付ける…と言い渡した。町内引廻しは牢屋敷を出て、きまった順路で江戸の町々をめぐり、牢屋敷にもどるのだが、火罪の場合は牢屋敷にもどらず処刑場に行くのである。そのさい、日本橋・筋違橋・両国橋・赤坂御門・四谷御門を必ず通る。この五ヶ所に罪状を記した捨札を建てた。八百屋お七を例にとると、…此しちと申女、火を付候とがによって町内引廻し、所々にさらし、火あぶりに行ふもの也…という文言である。火罪とは火あぶりのことで、真秀は浅草(実際には千住小塚原)で処刑されたから、捨札は小塚原にも建てられた。ちなみにお七の処刑は品川(鈴ヶ森)でおこなわれた。
…焼死体はそのまま三日間さらされた。真秀の火あぶりは六月二十一日で、二十六歳で生涯を終えた。
明暦三年(一六五七)から明治十四年(一八八一)まで、江戸・東京は九十三回も大火に見舞われたといわれる。三年に一度の発生率である。この頻発ぶりに着目した西山松之助氏は、江戸を〝火災都市〟と規定された。異常なのは火災の原因に放火が多かったことである。…火をつけて燃え上がった家の人々があわてふためいているすきに金品を盗むという放火の方がはるかに多かった…
江戸は武家政権の所在地であるから、大火後、放置しておくわけにはいかない。ただちに復旧工事が始まり、建築資材を扱う商人、大工・石工・屋根ふき・畳屋・建具屋・庭師などの職人、さらには長屋住まいの下層民に至るまで、景気の恩恵を受けるのである。江戸は大火のたびごとに不死鳥のようによみがえり拡大した。…西山松之助氏は…火事だ、というと、やれ助かった、と思った人が少なからずいたのであると考えられる。したがって、江戸の大火は、こういう人々の間から、かなり広く巧みに火付けをした者がいたと思われる。わからないように火を付けて大きな火事にしたものがいたと考えられるのである(『江戸町人の研究・第五巻』)。と指摘されているが、この見解は正鵠を得ていると思う。
…お七が放火したのは『天和笑委集』によると、…天和三年三月二日の夜のことで、本郷森川宿にあった生家の八百屋近くの商店の軒板のすきまに、綿くずをわらに包んで炭火といっしょにさし込んだだけで、近所の人々がかけつけ、たちまち消してしまった。…実害のないボヤであったからこそ、人々に大きな感動を与えたのではないだろうか。
第一、当時の刑罰をまとめている『元禄御法式』にも、…火を付る者之類、火罪…とあって、たとえばボヤであろうが自分の意志で火をつけた以上は、火あぶりなのである。…女性でも少年でも、けっして容赦はしなかったのである。
凶悪犯の仕置の過程はあまりにもエグイので割愛したが、興味のある人はネットで古本を探されるとよい。罪と罰、世の中の表と裏を小説の中にサラリと描いた池波作品は今も色あせていない。徴兵経験皆無・団塊世代の(自称)歴史研究家とやらが可哀想な者(罪人)の視点のみから過去の出来事を恣意的に評価するのとは大違いである。彼らの低質な作文が読み継がれないのは当たり前なのだ(笑)

若き長谷川平蔵と道場で腕を磨いていた岸井左馬之助(江守徹)が淡い恋心を抱いたおふさ(マンキュウ)が何と悪女に変わっていたという話で、時の流れの残酷さが主題であった。平蔵の密偵(お上の犬と蔑まれた元盗人達)へのさり気ないやさしさやエンディングテーマがジプシー・キングスの「インスピレーション」だった(原作者の池波さんもこの曲は気に入っていたらしい)こともあり、鬼平シリーズにどっぷりとはまった。
傑作時代劇を更に楽しむために出版された実録『鬼平犯科帳のすべて』には罪人の捕縛・取調・仕置について詳しい記述がある。中でも黒木喬氏の小論文は凶悪火付け犯を例にとって江戸の治安維持の仕組みを丁寧に説明しており資料的価値が非常に高い。
火災都市 江戸の放火と火刑 *火盗改の取り締まりにもかかわらず頻繁に起きた江戸の火災と火刑の実態は? / 黒木 喬
明和九年(一七七二)の江戸。…二月二十九日…目黒村行人坂の大円寺で出火があったのは午後一時すぎである。…大火が終息したのは翌三十日の午後一時ごろである。
この大火で焼失した町は九百三十四、大名屋敷百六十九、橋百七十、寺院三百八十二、死者一万四千七百人、行方不明四千六百人、明暦三年(一六五七)の振袖火事以来の大火といわれた。
四月二十二日に放火犯が逮捕された。…武州熊谷長五郎坊主真秀という悪党であった。幼少から武家奉公をしていたが、十四歳の時、屋敷の塀に放火し、衣類を盗んで在所に逃げ帰ったが、勘当されて江戸に出た。願人坊主…になったが、ほどなく破門されて無宿人の群に入った。無宿仲間と追はぎ・強盗など悪のかぎりを尽くしたという凶悪犯である。長谷川平蔵は吟味がむずかしいので、町奉行所に引き渡したいと上申した。だが、老中松平右近将監武元は、…重々不届至極に付、町内引廻し、五ヶ所に科書捨札を建て火罪を申付ける…と言い渡した。町内引廻しは牢屋敷を出て、きまった順路で江戸の町々をめぐり、牢屋敷にもどるのだが、火罪の場合は牢屋敷にもどらず処刑場に行くのである。そのさい、日本橋・筋違橋・両国橋・赤坂御門・四谷御門を必ず通る。この五ヶ所に罪状を記した捨札を建てた。八百屋お七を例にとると、…此しちと申女、火を付候とがによって町内引廻し、所々にさらし、火あぶりに行ふもの也…という文言である。火罪とは火あぶりのことで、真秀は浅草(実際には千住小塚原)で処刑されたから、捨札は小塚原にも建てられた。ちなみにお七の処刑は品川(鈴ヶ森)でおこなわれた。
…焼死体はそのまま三日間さらされた。真秀の火あぶりは六月二十一日で、二十六歳で生涯を終えた。
明暦三年(一六五七)から明治十四年(一八八一)まで、江戸・東京は九十三回も大火に見舞われたといわれる。三年に一度の発生率である。この頻発ぶりに着目した西山松之助氏は、江戸を〝火災都市〟と規定された。異常なのは火災の原因に放火が多かったことである。…火をつけて燃え上がった家の人々があわてふためいているすきに金品を盗むという放火の方がはるかに多かった…
江戸は武家政権の所在地であるから、大火後、放置しておくわけにはいかない。ただちに復旧工事が始まり、建築資材を扱う商人、大工・石工・屋根ふき・畳屋・建具屋・庭師などの職人、さらには長屋住まいの下層民に至るまで、景気の恩恵を受けるのである。江戸は大火のたびごとに不死鳥のようによみがえり拡大した。…西山松之助氏は…火事だ、というと、やれ助かった、と思った人が少なからずいたのであると考えられる。したがって、江戸の大火は、こういう人々の間から、かなり広く巧みに火付けをした者がいたと思われる。わからないように火を付けて大きな火事にしたものがいたと考えられるのである(『江戸町人の研究・第五巻』)。と指摘されているが、この見解は正鵠を得ていると思う。
…お七が放火したのは『天和笑委集』によると、…天和三年三月二日の夜のことで、本郷森川宿にあった生家の八百屋近くの商店の軒板のすきまに、綿くずをわらに包んで炭火といっしょにさし込んだだけで、近所の人々がかけつけ、たちまち消してしまった。…実害のないボヤであったからこそ、人々に大きな感動を与えたのではないだろうか。
第一、当時の刑罰をまとめている『元禄御法式』にも、…火を付る者之類、火罪…とあって、たとえばボヤであろうが自分の意志で火をつけた以上は、火あぶりなのである。…女性でも少年でも、けっして容赦はしなかったのである。
凶悪犯の仕置の過程はあまりにもエグイので割愛したが、興味のある人はネットで古本を探されるとよい。罪と罰、世の中の表と裏を小説の中にサラリと描いた池波作品は今も色あせていない。徴兵経験皆無・団塊世代の(自称)歴史研究家とやらが可哀想な者(罪人)の視点のみから過去の出来事を恣意的に評価するのとは大違いである。彼らの低質な作文が読み継がれないのは当たり前なのだ(笑)