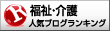俺は44歳の時、釣行先で脳幹出血に倒れ、救急車で運ばれた
秋田の病院に1か月、地元の病院で9か月の入院生活の心境などを記した冊子
・
見舞い返しや、昔お世話になった方への報告として創った冊子がなぜか?
地元新聞、地方放送で取り上げられた、この冊子が俺の第二の人生の始まりだった気がする
コロナが発生する前の10年、夫婦で活動した福祉学習
思春期を迎えた生徒におこなった「心の授業」、俺は体験からこんなことを伝えた
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「心の授業」 武久ぶく
・
どんなにつらくとも
どんなに悲しくても
・
ものごとの見方を少し変えてごらん
すべてのことは、ものは考えようなのだよ
・
自分だけ不幸だとか
自分だけつまらないと思ったなら
・
喜びを自分の心の中に探してごらん
楽しい事だけが幸せではないのだからね
・
どんな時でも
どんなにつらくとも
手をのばしたら君はもう独りなんかじゃないよ
・
夢はかなえることが大切なのじゃない
夢のためにがんばることが大切なのさ
人生はあきらめなきゃなんとかなるものだよ
・
ケア職の方から見ると、俺らは仲むづましい夫婦、頑張る夫婦らしい
「一生懸命な奥さんですね」「武久さん、奥さんに感謝ですね」とかとか
・
俺らも「そうですかぁ~」「そうですねぇ」と相づちはうつものの
もちろん、仲が悪い訳でもないし、感謝していない訳でもない、が
・
しかし、俺ら夫婦は特別なものではなく
言い合いもすれば口も利かないこともあるどこにでもいるような普通の夫婦だ
・
妻が重度障害を介護している在宅介護生活だけどごくごく普通の夫婦
ケアを受けている人も、ケアしている人も特別ではなく普通のどこにでもいる人。

「楽しくなければ人生じゃない」とはよく聞くフレーズ
そして、人は誰しも幸せになりたくて生きているのだろう
・
しかし、ケアの対象となる人たちにとっては
一般的に言う「楽しさ」とか「幸せ」の感覚と無縁の人は沢山いる
・
別に楽しくもなく、幸せとも言えない、そんな生活を支えるもの
それは「喜び」と言う感情、感覚、生きている喜び、他人との関わりの喜び、、、
・
ケアする人たちは
楽しさや幸せなどの追求から、喜びを感じられることへと視点を変えてみよう。

脳卒中に倒れ、気がつけば四肢麻痺、、、その時に抱いた絶望感や喪失感
長く苦しめられたものの、その想いは時の流れ共に慣れと諦めとで風化して行った
・
が、いつまでも周期的に心に湧く「妬みや僻み」には悩まされる
それは些細な出来事や些細な言葉、些細なことをきっかけにして湧き上がる
・
他人からみれば本当に些細なことなのだろうが負のスパイラルに落ち込む
いじけたり悪く憶測してみたり自暴自棄に、、、考え過ぎだとは分かっていても
・
この感情はなかなか手ごわい、油断しているとすぐにやられる
俺は思う、この周期的に繰り返す「妬み僻み」を制する者は中途障害を制する、と。

住みなれた自宅で、、、とか表現される在宅医療などだけど
俺が経験した病院やデイサービスでの生活、在宅での生活に感じること
・
一番の違いは自由さ、ホームゲームとアウェイゲームの違い、主役の違い
施設などでは全て施設側のタイムテーブルでの生活になり、主導権は施設側
・
一方、在宅生活ならお腹が空いたら食べ、眠くなったら寝る、夜更かしも、、、
家だと他人や時間を気にせずにゆっくりトイレができる、つまり主役は自分
・
だから住みなれたと言うより、自由な環境の我が家で、、、と言った方がピッタリ。