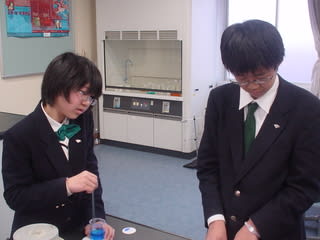2月21日(月)
硫酸銅の結晶の「お世話」を終えて、カブトムシの幼虫のマットを交換することにしました。
・なぜ交換しなければならないか
それは、カブトムシの幼虫はマット(腐葉土)を食べながらフンも同時に出して動いていくのです。自然ではフンがたまっても、別の場所に移動すればいいのですが、容器の中では移動もできません。だから、どんどんフンはたまっていくのです。周りがフンだらけになることもしばしばあることなのです。そうすると、幼虫は「自分のフン」を食べることになり、栄養がないためにどんどんやせてしまうのです。そのままほったらかしにすると、幼虫が死んでしまったり、極端に小さい成虫が生まれてきたりするのです。だからこそ、マットがフンだらけになる前に交換するのがお勧めなのです。
・どのようにして交換するのでしょうか。
昆虫マットをホームセンターやペットショップで買ってきて、水で少し湿らせて入れてあげればいいのです。
簡単ですね。(正確には、マットを握って形がこわれないぐらいの水分量)しかし、名古屋経済大学高蔵高校理科部はちょっと違います。何でもリサイクルなのです。
以前、理科部では大量に日本各地のクワガタムシを飼育していました。そのフンが大量にストックしてあり、現在はこれを再利用しています。昆虫マットも買わなくてすむし、ゴミもでないので一石二鳥です。クワガタムシのフンは、カブトムシの幼虫にも良いだろうと考え、試してみると、よく成長することがわかりました。
さらに、クワガタムシのフンを食べたカブトムシのフンは、学校内の植物の根本にまいています。これが良い肥料となっています。
では、今回の作業ですが、手順は次の通りです。
〈手順〉
1.現在のマットを全部交換するのではなく、ふるいで、フンだけを集めてそれを校内の
樹木の下にまきます。
2.クワガタムシのフンで作ったマットを水で湿らせてから足りなくなったマットとして容器
の中に入れます。
しかし、今回はトラブルが発生してしまいました。
クワガタの「フンマット」に水を大量に入れてしまったのです。
片付けが大変でした。
作業は全員で行ったため、その過程の写真は撮れませんでした。

この写真は、作業に使った衣装ケースを洗って乾かしているところです。

片付けも終わり、帰宅準備です。

こんな感じのマットです。なかなかのものです。

このような衣装ケースで幼虫を飼育しています。
1匹も死なずに元気に育っています。
これは、むやみに「掘り返して触ったり」していないからです。
皆さんも、是非飼育してみてはいかがですか。
ちなみに、私たち理科部の生徒の中にも幼虫が触れない人が多いのです。
不思議ですが、本当の話です。
硫酸銅の結晶の「お世話」を終えて、カブトムシの幼虫のマットを交換することにしました。

・なぜ交換しなければならないか

それは、カブトムシの幼虫はマット(腐葉土)を食べながらフンも同時に出して動いていくのです。自然ではフンがたまっても、別の場所に移動すればいいのですが、容器の中では移動もできません。だから、どんどんフンはたまっていくのです。周りがフンだらけになることもしばしばあることなのです。そうすると、幼虫は「自分のフン」を食べることになり、栄養がないためにどんどんやせてしまうのです。そのままほったらかしにすると、幼虫が死んでしまったり、極端に小さい成虫が生まれてきたりするのです。だからこそ、マットがフンだらけになる前に交換するのがお勧めなのです。
・どのようにして交換するのでしょうか。
昆虫マットをホームセンターやペットショップで買ってきて、水で少し湿らせて入れてあげればいいのです。
簡単ですね。(正確には、マットを握って形がこわれないぐらいの水分量)しかし、名古屋経済大学高蔵高校理科部はちょっと違います。何でもリサイクルなのです。
以前、理科部では大量に日本各地のクワガタムシを飼育していました。そのフンが大量にストックしてあり、現在はこれを再利用しています。昆虫マットも買わなくてすむし、ゴミもでないので一石二鳥です。クワガタムシのフンは、カブトムシの幼虫にも良いだろうと考え、試してみると、よく成長することがわかりました。
さらに、クワガタムシのフンを食べたカブトムシのフンは、学校内の植物の根本にまいています。これが良い肥料となっています。
では、今回の作業ですが、手順は次の通りです。
〈手順〉
1.現在のマットを全部交換するのではなく、ふるいで、フンだけを集めてそれを校内の
樹木の下にまきます。
2.クワガタムシのフンで作ったマットを水で湿らせてから足りなくなったマットとして容器
の中に入れます。

しかし、今回はトラブルが発生してしまいました。
クワガタの「フンマット」に水を大量に入れてしまったのです。
片付けが大変でした。
作業は全員で行ったため、その過程の写真は撮れませんでした。

この写真は、作業に使った衣装ケースを洗って乾かしているところです。

片付けも終わり、帰宅準備です。

こんな感じのマットです。なかなかのものです。

このような衣装ケースで幼虫を飼育しています。
1匹も死なずに元気に育っています。
これは、むやみに「掘り返して触ったり」していないからです。
皆さんも、是非飼育してみてはいかがですか。
ちなみに、私たち理科部の生徒の中にも幼虫が触れない人が多いのです。
不思議ですが、本当の話です。