ブラームスの『ドイツ・レクイエム』が某所から送付されてきた(カラヤン指揮ベルリン・フィルによる64年5月ウィーン、ムジークフェラインザールでの録音、2004年DSDマスタリング盤)。
なんと6月23日発売予定のSHM仕様のSACD(シングル・レイヤー)と既に発売されているハイブリッド盤SACDの2枚である。
現在、OIBP(オリジナル・イメージ=ビット・プロセッシング)製の輸入盤CDを持っているので、今回新譜となるSHM仕様のSACD(シングル・レイヤー)盤とハイブリッドのSACD盤(CD層、SACD2チャンネル、5.1ch)という3枚が我が家に勢揃いした形になる。当然ながら「比較試聴せよ!」とのご託宣だ。
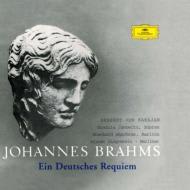 さて、比較試聴のし甲斐がある音源なので、その聴き所も満載という感じだけに目移りしちゃいそうだ。ゆえに今回は第1楽章での混声四部合唱の位置関連(左右、上下定位と遠近感)、ハープの音色、コントラバスの定位(明瞭度)、第2楽章では、連打されるティンパニーの音色、第3楽章と第6楽章のバリトン独唱の質感、第5楽章のソプラノ独唱のヌケといったところに視点を置いて聴いた。
さて、比較試聴のし甲斐がある音源なので、その聴き所も満載という感じだけに目移りしちゃいそうだ。ゆえに今回は第1楽章での混声四部合唱の位置関連(左右、上下定位と遠近感)、ハープの音色、コントラバスの定位(明瞭度)、第2楽章では、連打されるティンパニーの音色、第3楽章と第6楽章のバリトン独唱の質感、第5楽章のソプラノ独唱のヌケといったところに視点を置いて聴いた。
新譜のSHM=SACDはひとまず置いておいて、まずはハイブリッドSACDなのだが、この盤の良さは音に厚みがあることだろう。混声4部の声の厚み、コントラバスの沈み込み、弦楽器のピチカートの空気感など、とても柔らかで弾力のある質感を聴かせてくれる。第1楽章で聴こえるハープの音は、SACDハイブリッドの方が本物の音であると誰が聴いてもそう思うはずだ。またコーラスの左右の広がりは、CDや今回のSHM=SACDよりも広いのだ。
なにかハイブリッドSACDの方が良いことずくめのようなのだが、SHM=SACDの良さは別の所にある。すなわちオーディオという視点でこの盤を聴くけば明らかに全体の質感向上によるクォリティ感がアップしていることを実感出来るはずだ。同じ音源(OIBPマスター)であるし、実際にこのSHM=SACD製作マスターも同一と聞いている。聴いていてその違いが出ているのは、その盤の素材と製作過程の違いだけだ。そう、液晶用のポリカーボネイトという違いだけなのだ。で、その音の違いは何か。
一口に質感の向上と言っても、今回のシングル・レイヤーのSACDの音は、明らかにオーディオ専用と言っても過言ではない音質が聴けている。楽器群、声楽、コーラスともに実にリアルなのだ。一聴するとSHM=SACD盤は、やや線が細い音のように聴こえる。しかし混声合唱の各パートの分離や、ソプラノ、アルト、テノール、バリトン(バス)といったコーラス・セクションの位置関係がより明確になっている。また通奏低音(鼓動)のように鳴らされるティンパニーの皮の質感描写は、やはりシングル・レイヤー盤の方が圧倒的にいい。なぜか盤自体の全体の音圧も高く聴こえる(本盤製作の技術者曰く、ハイブリッドSACD盤と全く同一にしているとのことだが、ポリカーボネイトの反射率の問題でそういう風に聴こえているのかもしれない)。
ソリストであるバリトンのエーベルハルト・ヴェヒターの声も素晴らしい。そう、胸板の厚さがリアルに感じられるくらいホログラフィカルで、声そのものがダイレクトに伝わってくる歌声だ。ハイブリッドSACDも厚い声なのだが、SHM=SACDには鮮度があってよりリアルな雰囲気があるのが望ましい。同様にグンドゥラ・ヤノヴィッツのソプラノ独唱も凄い。この位の音圧(声圧)になると、当然強音部が潰れたりしないためにコンプレッサーを通してしまうことが多いので、平坦な声に響くことがあるのだが、全く潰れずにヌケ切っている。ソプラノ(高音)だけに直進性が抜群でダイレクトに鼓膜を刺激する。快感度抜群なのはSHM=SACDだった。
コーラスといえば、音場である。今回、セッティングを追い込んで聴いている(相当追い込んでみました:大爆)。これが怖いくらいギッシリと合唱団が居並んでいるわけです。それも、かなり高い位置の定位したりして、もう聴いていてゾクゾクしました。ただ唯一、SHM=SACDが負けているのは左右の音場。これはハイブリッドSACDの方が広いですね。
それにしても、45年も前の録音なのです。聴けば聴くほど当時のエンジニアが行ったマイク・セッティングや、機器のメンテナンスなんてことが思い起こされました。本当に素晴らしいクラフトマンシップ。そしてプロ意識満載の録音かと思います。現場で見てみたいと心底思いましたから。まさに素晴らしい音楽的遺産が見事なまでに眼前に繰り広げられるのですから驚くしかありません。いい機会を作っていただき、感謝しています。ありがとうございました。
ちなみに今回のSHM=SACDは、初回限定で4500円。うーん、最大のネックはこの金額にあるのかもしれません
なんと6月23日発売予定のSHM仕様のSACD(シングル・レイヤー)と既に発売されているハイブリッド盤SACDの2枚である。
現在、OIBP(オリジナル・イメージ=ビット・プロセッシング)製の輸入盤CDを持っているので、今回新譜となるSHM仕様のSACD(シングル・レイヤー)盤とハイブリッドのSACD盤(CD層、SACD2チャンネル、5.1ch)という3枚が我が家に勢揃いした形になる。当然ながら「比較試聴せよ!」とのご託宣だ。
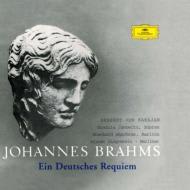 さて、比較試聴のし甲斐がある音源なので、その聴き所も満載という感じだけに目移りしちゃいそうだ。ゆえに今回は第1楽章での混声四部合唱の位置関連(左右、上下定位と遠近感)、ハープの音色、コントラバスの定位(明瞭度)、第2楽章では、連打されるティンパニーの音色、第3楽章と第6楽章のバリトン独唱の質感、第5楽章のソプラノ独唱のヌケといったところに視点を置いて聴いた。
さて、比較試聴のし甲斐がある音源なので、その聴き所も満載という感じだけに目移りしちゃいそうだ。ゆえに今回は第1楽章での混声四部合唱の位置関連(左右、上下定位と遠近感)、ハープの音色、コントラバスの定位(明瞭度)、第2楽章では、連打されるティンパニーの音色、第3楽章と第6楽章のバリトン独唱の質感、第5楽章のソプラノ独唱のヌケといったところに視点を置いて聴いた。新譜のSHM=SACDはひとまず置いておいて、まずはハイブリッドSACDなのだが、この盤の良さは音に厚みがあることだろう。混声4部の声の厚み、コントラバスの沈み込み、弦楽器のピチカートの空気感など、とても柔らかで弾力のある質感を聴かせてくれる。第1楽章で聴こえるハープの音は、SACDハイブリッドの方が本物の音であると誰が聴いてもそう思うはずだ。またコーラスの左右の広がりは、CDや今回のSHM=SACDよりも広いのだ。
なにかハイブリッドSACDの方が良いことずくめのようなのだが、SHM=SACDの良さは別の所にある。すなわちオーディオという視点でこの盤を聴くけば明らかに全体の質感向上によるクォリティ感がアップしていることを実感出来るはずだ。同じ音源(OIBPマスター)であるし、実際にこのSHM=SACD製作マスターも同一と聞いている。聴いていてその違いが出ているのは、その盤の素材と製作過程の違いだけだ。そう、液晶用のポリカーボネイトという違いだけなのだ。で、その音の違いは何か。
一口に質感の向上と言っても、今回のシングル・レイヤーのSACDの音は、明らかにオーディオ専用と言っても過言ではない音質が聴けている。楽器群、声楽、コーラスともに実にリアルなのだ。一聴するとSHM=SACD盤は、やや線が細い音のように聴こえる。しかし混声合唱の各パートの分離や、ソプラノ、アルト、テノール、バリトン(バス)といったコーラス・セクションの位置関係がより明確になっている。また通奏低音(鼓動)のように鳴らされるティンパニーの皮の質感描写は、やはりシングル・レイヤー盤の方が圧倒的にいい。なぜか盤自体の全体の音圧も高く聴こえる(本盤製作の技術者曰く、ハイブリッドSACD盤と全く同一にしているとのことだが、ポリカーボネイトの反射率の問題でそういう風に聴こえているのかもしれない)。
ソリストであるバリトンのエーベルハルト・ヴェヒターの声も素晴らしい。そう、胸板の厚さがリアルに感じられるくらいホログラフィカルで、声そのものがダイレクトに伝わってくる歌声だ。ハイブリッドSACDも厚い声なのだが、SHM=SACDには鮮度があってよりリアルな雰囲気があるのが望ましい。同様にグンドゥラ・ヤノヴィッツのソプラノ独唱も凄い。この位の音圧(声圧)になると、当然強音部が潰れたりしないためにコンプレッサーを通してしまうことが多いので、平坦な声に響くことがあるのだが、全く潰れずにヌケ切っている。ソプラノ(高音)だけに直進性が抜群でダイレクトに鼓膜を刺激する。快感度抜群なのはSHM=SACDだった。
コーラスといえば、音場である。今回、セッティングを追い込んで聴いている(相当追い込んでみました:大爆)。これが怖いくらいギッシリと合唱団が居並んでいるわけです。それも、かなり高い位置の定位したりして、もう聴いていてゾクゾクしました。ただ唯一、SHM=SACDが負けているのは左右の音場。これはハイブリッドSACDの方が広いですね。
それにしても、45年も前の録音なのです。聴けば聴くほど当時のエンジニアが行ったマイク・セッティングや、機器のメンテナンスなんてことが思い起こされました。本当に素晴らしいクラフトマンシップ。そしてプロ意識満載の録音かと思います。現場で見てみたいと心底思いましたから。まさに素晴らしい音楽的遺産が見事なまでに眼前に繰り広げられるのですから驚くしかありません。いい機会を作っていただき、感謝しています。ありがとうございました。
ちなみに今回のSHM=SACDは、初回限定で4500円。うーん、最大のネックはこの金額にあるのかもしれません











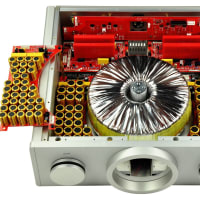


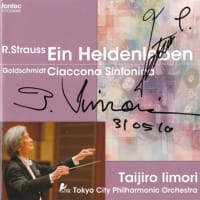





わたくしも、先日、ショップの方に半ば強引にSHM-SACDを数枚予約されてしましました。とても好きなジャズ盤が数点あったので、持っているのにな~とおもいつつ同じCDを購入しております。
もうお聞きになられたと聞いて、とてもお詳しい方だと存じました。これからも新しい情報(MAJIK DSでも)宜しくお願いします。