神戸在住の信太一郎さんがインターネットで主宰するおしゃべりの会に2年ほど前から参加している。インターネット上で同好の士が集まるこうしたグループは刺激的で息抜きにも勉強にもなる。ただし星の数ほど様々なグループがあるので、良質でかつ自分の興味に沿ったものを厳選する必要がある。信太さんのは今まで私が参加したものの中で最良のものだ。 http://homepage1.nifty.com/forty-sixer/
信太さんを筆頭に、ここで発言する人達に私は一度も会ったことがない。しかし、個人攻撃や差別的な発言は慎むなどといったエチケットを守り、しかも主宰者のポリシー(問題のある発言は削除するなど)がしっかりしていれば何ら問題なく知的好奇心を満たせる。今さらながらにインターネットという文明の利器の有難さを実感している。「三人寄れば文殊の知恵」というぐらいだから、言葉に関する話題がどれほど自由闊達に討議出来るか、想像して戴けるだろう。
そうした暗黙上のエチケットの一つに「討議を聞いているばかりでなく発言する/情報を貰うばかりでなく与える」ということがある。日本語文法以外でも、当地に住む私にはよくフランス語に関する質問が来る。今日はそんな質問の一つを御紹介してみよう。
「昔の映画の主題歌で、ケセラセラというのがありましたね。ケセラセラってフランス語ですか」と先日突然尋ねられてハタと返答に窮した。確かによく知られた歌であるし、随分前にその映画を観たこともおぼろげながら記憶していた。映画は「日曜は駄目よ」だったか?歌っていたのはドリス・デイだったと思うが…。いずれにしてもケセラセラはフランス語の文ではなさそうだ。Que sera sera.と書くのだろうか。もしそうなら、発音も「クスラスラ」となって「ケセラセラ」じゃないだろう。それにこれがもし仏文でも意味が通じない。きっとスペイン語じゃないか、と考え「調べてみましょう。少し時間を下さい」と書いた。
さてどうしよう。ふと思い立って「仏語協会(Office de la langue francaise)」の「仏語何でも相談室」に電話してみる。初めての経験だったが、初老(と思われる声)の男性が「スペイン語の諺ですよ」と即答してくれた。何度も同じ質問を受けたのだろうか。この歌を作曲したのが米国のリビングストンという人であること、この曲でオスカーを受賞したこと、そして昨年86才でロサンゼルスで亡くなったことまで、おまけに教えてくれたのには吃驚した。有料(5$)だが、誠に行き届いたサービスではないか。(電話:1-900-565-8899)
早速そうした情報をネットに流したら、今度は信太さんからの新情報があった。この歌が歌われた映画はヒッチコックの「知りすぎていた男」だとのこと。そう言えばジェームズ・スチュワートとドリス・デイの共演だった。「日曜は駄目よ」は別の歌で、遅れ馳せながらメロディーを思い出した次第である。
さて「ケセラセラ」だが、歌詞は英語でWhatever will be, will be.と続く。「なるようになるわよ」と母親が娘に語っている歌だ。「なるようになるわよ」か。それじゃビートルズの「Let it be.」と同じ様なメッセージじゃないか、という風にネット上のおしゃべりの会はひとしきり盛り上がる。すると誰が「Let it be.」の it って何だろうと難問を発する。こうしたやり取りは刺激的で実に楽しい。
森本哲郎という評論家の書いた「ことばの旅」という随筆をちょうど読んでいた所で、たまたまこの曲のことが出ていた。森本は先ず「Let it be」を「あるがままにあらしめよう」と直訳。その意味は要するに「放っておこう」であると述べている。生をそのまま受け入れよう、現実を肯定しよう、ということだろうか。
それで思い出した。先日トロントに行く用事があったので待望の小野洋子展「Yes」を見て来た。ヨーコとジョン・レノンが1966年にロンドンで運命の出会いをしたアート作品展である。会場に置かれたはしごを昇って、天井からぶら下がっている虫眼鏡で覗いた時に、天井に小さくタイプしてある「Yes」をジョンは読んだ。心から感動したジョンは、はいごからまっ逆さまに恋に落ちたのだった。大いなる現実の肯定。きっと「Yes」と「Let it be」とはどこかで繋がっていると思う。
(追記:昨年9月11日のテロの後、アメリカの一部のメディアが放送を自粛した歌の中にジョン・レノンの「イマジン」があったと聞く。やれやれ「Give Peace a Chance.」の実現は一体いつのことだろうか。ジョンは天国で歎いていることだろう)(2002年4月)
応援のクリック、よろしくお願いいたします。

信太さんを筆頭に、ここで発言する人達に私は一度も会ったことがない。しかし、個人攻撃や差別的な発言は慎むなどといったエチケットを守り、しかも主宰者のポリシー(問題のある発言は削除するなど)がしっかりしていれば何ら問題なく知的好奇心を満たせる。今さらながらにインターネットという文明の利器の有難さを実感している。「三人寄れば文殊の知恵」というぐらいだから、言葉に関する話題がどれほど自由闊達に討議出来るか、想像して戴けるだろう。
そうした暗黙上のエチケットの一つに「討議を聞いているばかりでなく発言する/情報を貰うばかりでなく与える」ということがある。日本語文法以外でも、当地に住む私にはよくフランス語に関する質問が来る。今日はそんな質問の一つを御紹介してみよう。
「昔の映画の主題歌で、ケセラセラというのがありましたね。ケセラセラってフランス語ですか」と先日突然尋ねられてハタと返答に窮した。確かによく知られた歌であるし、随分前にその映画を観たこともおぼろげながら記憶していた。映画は「日曜は駄目よ」だったか?歌っていたのはドリス・デイだったと思うが…。いずれにしてもケセラセラはフランス語の文ではなさそうだ。Que sera sera.と書くのだろうか。もしそうなら、発音も「クスラスラ」となって「ケセラセラ」じゃないだろう。それにこれがもし仏文でも意味が通じない。きっとスペイン語じゃないか、と考え「調べてみましょう。少し時間を下さい」と書いた。
さてどうしよう。ふと思い立って「仏語協会(Office de la langue francaise)」の「仏語何でも相談室」に電話してみる。初めての経験だったが、初老(と思われる声)の男性が「スペイン語の諺ですよ」と即答してくれた。何度も同じ質問を受けたのだろうか。この歌を作曲したのが米国のリビングストンという人であること、この曲でオスカーを受賞したこと、そして昨年86才でロサンゼルスで亡くなったことまで、おまけに教えてくれたのには吃驚した。有料(5$)だが、誠に行き届いたサービスではないか。(電話:1-900-565-8899)
早速そうした情報をネットに流したら、今度は信太さんからの新情報があった。この歌が歌われた映画はヒッチコックの「知りすぎていた男」だとのこと。そう言えばジェームズ・スチュワートとドリス・デイの共演だった。「日曜は駄目よ」は別の歌で、遅れ馳せながらメロディーを思い出した次第である。
さて「ケセラセラ」だが、歌詞は英語でWhatever will be, will be.と続く。「なるようになるわよ」と母親が娘に語っている歌だ。「なるようになるわよ」か。それじゃビートルズの「Let it be.」と同じ様なメッセージじゃないか、という風にネット上のおしゃべりの会はひとしきり盛り上がる。すると誰が「Let it be.」の it って何だろうと難問を発する。こうしたやり取りは刺激的で実に楽しい。
森本哲郎という評論家の書いた「ことばの旅」という随筆をちょうど読んでいた所で、たまたまこの曲のことが出ていた。森本は先ず「Let it be」を「あるがままにあらしめよう」と直訳。その意味は要するに「放っておこう」であると述べている。生をそのまま受け入れよう、現実を肯定しよう、ということだろうか。
それで思い出した。先日トロントに行く用事があったので待望の小野洋子展「Yes」を見て来た。ヨーコとジョン・レノンが1966年にロンドンで運命の出会いをしたアート作品展である。会場に置かれたはしごを昇って、天井からぶら下がっている虫眼鏡で覗いた時に、天井に小さくタイプしてある「Yes」をジョンは読んだ。心から感動したジョンは、はいごからまっ逆さまに恋に落ちたのだった。大いなる現実の肯定。きっと「Yes」と「Let it be」とはどこかで繋がっていると思う。
(追記:昨年9月11日のテロの後、アメリカの一部のメディアが放送を自粛した歌の中にジョン・レノンの「イマジン」があったと聞く。やれやれ「Give Peace a Chance.」の実現は一体いつのことだろうか。ジョンは天国で歎いていることだろう)(2002年4月)
応援のクリック、よろしくお願いいたします。











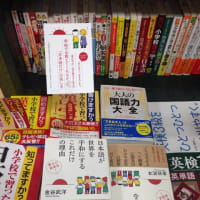

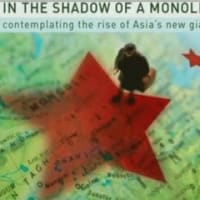
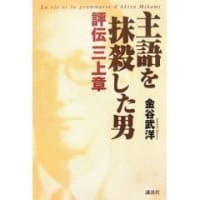
今から15・6年前・三十代後半までの私は、球技と名のつくモノは、ほとんど?やった!と思っていました。小さい玉から順に書いていきますと、ビー玉・パチンコ・スマートボール・ピンポン・ソフトボール・軟式野球・サッカー・バスケットボール、それから運動会の玉転がしとなります。まだまだあると思いますが、日本で考え付く球技はこんなものでしょうか。球技と名のつくスポーツ以外のモノも入っていますが、ほとんど手を出したと思っていたのです。
東京から九州・福岡に転勤になって、やってない球技をしなければならないハメになってしまい、ハタと困ってしまったのです。一朝一夕では、競技に参加できるどころか、顰蹙を買ってしまうことになりかねず、人並みに悩んだのでした。しかも、伝統ある世界的な球技・スポーツで、日本ではプレー費が高く、道具も高いときている。ここまで書けば、この球技をやったことのある人は、もうお分かりかと思います。ゴルフだけは、手を出してなかったというより、先立つものがなくて手を出せなっかたのです。それと、あんなスポーツと小バカにしていました。
ところが、嵌ってしまうんですね。厄年から始めてしまったのです。そしてのめりこんでしまうから、人間は分からないのですね。
スミマセン、またしてもイントロが長くなりました。
プレイ ザ ボール アズ イット ライズ という、ゴルフの格言?があります。私もこれを肝に銘じているのですが。私流に訳すと「あるがままの状態で打て」ということになります。森本哲郎サンは、Let it be を「あるがままにあらしめよう」と直訳されたとありました。アズ イツトの as it は、レット・イット・ビーともケセラセラともその意味合い?は違うのでしょうが、同じような同じでないような・・・気がしているのです。でも、同じなような・・・。
それと Yes と同じなようにも思えてくるのです。
中・高・大の学生時代、英語はほとんど赤点でした。
失礼しました。