日本語をよく観察すると、日本人がいかに「対話の場」を大切にする民族かということに驚く。話し手である自分がいて、自分の前に聞き手がいる。聞き手は2人以上のこともあるが多くは1人だ。ここで大切なのは、この「対話の場」に<我>と<汝>が一体となって溶け込むということだ。この点が日本文化の基本であるように思えてならない。日本語における<我>は、決して「対話の場」から我が身を引き離して、上空から<我>と<汝>の両者を見下ろすような視線をもたない。<我>の視点は常に「いま・ここ」にあり、「ここ」とは対話の場である。
これに対して、西洋の考え方は自己を世界から切り取る所に特徴があるように思える。自分に地球の外の一点を与えよ、地球を動かしてみせると豪語したのはアルキメデスだった。自分を「我思う、ゆえに我あり」と、思考する<我>を世界と対峙させることで<我>の存在証明にしようと試みたのはデカルト(「方法序説」1637年)である。端的に言えば、西洋の<我>は<汝>と切れて向き合うが、日本の<我>は<汝>と繋がり、同じ方向をむいて視線を溶け合わすと言えるだろう。
臨床心理学者で元文化庁長官の河合隼雄(1928-2007)も「ユング心理学と仏教」(1995年)の中で同じことをいっている。このシリーズ41回目「切る言葉、繋ぐ言葉」でも引用した箇所に再び耳を傾けてみよう。河合は、西洋人と日本人の自我を比較してこう言う。「他と区別し自立したものとして形成されている西洋人の自我は日本人にとって脅威であります。日本人は他との一体感的な繋がりを前提とし、それを切ることなく自我を形成します。(…)非常に抽象的に言えば、西洋人の自我は「切断」する力が強く、何かにつけて区別し分離していくのに対して、日本人の自我は出来るだけ「切断」せず「包含」することに耐える強さをもつと言えるでしょう」
そうした日本人の包含志向が「対話の場」の重視に表れるのは当然である。今回はいくつかの日常表現から観察してみよう。日本語を教えていると「なぜそんな言い方をするのですか」と不思議な顔をした学習者によく尋ねられる。尋ねられて答えを考えているうちに「対話の場」の重要性が見えてきたのである。
「対話の場」を重視する典型的な例が「行って来ます」と送り出す「行ってらっしゃい」だ。家を、会社を、国を出る時に誰もが口にする表現で、ほとんどの日本人が毎日使っているだろう。だが、これを直訳するととてもおかしなことになる。何故か。英仏語にはそう言おうとする発想がないからだ。「行って来ます」には動詞が二つあるから、本来の意味は「行きます(が、必ず帰って)来ます」であったろう。つまり、対話の場に必ず戻ることを約束しているのである。送り出す方も同じ発想で、「行ってらっしゃい」は「行って+いらっしゃい」の「い」が落ちたもの。 「いらっしゃる」は尊敬語で「いる・来る・行く」の3つの意味があるが、ここは明らかに「来る」の尊敬語だ。「行ってきます」が敬語の「行って参ります」や打ちとけた「行って来るね」になったところで、動詞が重なる文構造も、その本来の意味も全く変わらない。同様に、ぶっきら棒に「おぅ、行って来い」などと応じたところで、やはり「行ってらっしゃい」と同じ意味の答えなのである。英語では「I'm going now」や「I'll be back soon」などは言うが、この2つを一緒にし、しかも日常表現として毎日使うということはしない。
「行ってきます」の応用編とでも思えるのが「焼き芋を買って来たよ」「カナダへ行って来ました」などで、これらも英語であれば後半の「and I came back」は全く蛇足である。やはり日本語話者の発想に「そうやってここに戻って来ましたよ」という「対話の場」を大切にする、ひいては相手への気配りが伺える。
出かけた後は自宅や会社に帰ってくる。その時に日本人はまたしても外国人に不可解な表現を使うのである。それが「ただいま」だ。「ただいま」とは言うまでもなく「只今」の意味で、直訳すれば「Right now」だが、こう言って帰って来る英語話者は見たことがない。何故日本人はこんな言い方をするのか。またしても学習者が頭を傾げる場面だ。
出迎える方がまた不思議な発話をする。「お帰りなさい」だが、その本来の意味を英訳するとナンセンス極まりない文となる。これはどう見ても「お食べなさい、お話しなさい」などと同じ構造の命令文ではないか。もう目の前に帰ってきた聞き手がいるのに「Please come/go back」などと頓珍漢なことを言うのだろう。
この受け答えは、「お帰りなさい」「ただいま」と発話の順序を逆にすると真意が分かりやすい。出迎えて「お帰りなさい」と言うのは、字句通りの「はやく帰ってきて」という祈りを、姿が見える直前、まさに文字通りの「ただいま」まで、唱えていた名残ではないだろうか。対話の場への帰還をどんなにか待っていたという気持ちほど、相手への気配り、思いやりを雄弁に物語るものはないと思う。それに応えて帰還者は不在の長さを詫びる。長いこと対話の場を離れてすまなかった、さぁ今、帰ったよ、という気持ちで日本人は「ただいま」と言うのだ。「ただいま」とは「たった今」なのである。
何という白熱、緊張した再会の場面を日本人は言語化しているのかと改めて驚くばかりだ。あたかも孵化した雛が殻の内側から、そして親の雌鳥が殻の外から同時に卵を突くように、両者が積極的に再会の場面に参加し、そして対話の場への復帰を言祝ぐのが我々日本語話者であると言えないだろうか。 (2008年1月)
応援のクリック、よろしくお願いいたします。

これに対して、西洋の考え方は自己を世界から切り取る所に特徴があるように思える。自分に地球の外の一点を与えよ、地球を動かしてみせると豪語したのはアルキメデスだった。自分を「我思う、ゆえに我あり」と、思考する<我>を世界と対峙させることで<我>の存在証明にしようと試みたのはデカルト(「方法序説」1637年)である。端的に言えば、西洋の<我>は<汝>と切れて向き合うが、日本の<我>は<汝>と繋がり、同じ方向をむいて視線を溶け合わすと言えるだろう。
臨床心理学者で元文化庁長官の河合隼雄(1928-2007)も「ユング心理学と仏教」(1995年)の中で同じことをいっている。このシリーズ41回目「切る言葉、繋ぐ言葉」でも引用した箇所に再び耳を傾けてみよう。河合は、西洋人と日本人の自我を比較してこう言う。「他と区別し自立したものとして形成されている西洋人の自我は日本人にとって脅威であります。日本人は他との一体感的な繋がりを前提とし、それを切ることなく自我を形成します。(…)非常に抽象的に言えば、西洋人の自我は「切断」する力が強く、何かにつけて区別し分離していくのに対して、日本人の自我は出来るだけ「切断」せず「包含」することに耐える強さをもつと言えるでしょう」
そうした日本人の包含志向が「対話の場」の重視に表れるのは当然である。今回はいくつかの日常表現から観察してみよう。日本語を教えていると「なぜそんな言い方をするのですか」と不思議な顔をした学習者によく尋ねられる。尋ねられて答えを考えているうちに「対話の場」の重要性が見えてきたのである。
「対話の場」を重視する典型的な例が「行って来ます」と送り出す「行ってらっしゃい」だ。家を、会社を、国を出る時に誰もが口にする表現で、ほとんどの日本人が毎日使っているだろう。だが、これを直訳するととてもおかしなことになる。何故か。英仏語にはそう言おうとする発想がないからだ。「行って来ます」には動詞が二つあるから、本来の意味は「行きます(が、必ず帰って)来ます」であったろう。つまり、対話の場に必ず戻ることを約束しているのである。送り出す方も同じ発想で、「行ってらっしゃい」は「行って+いらっしゃい」の「い」が落ちたもの。 「いらっしゃる」は尊敬語で「いる・来る・行く」の3つの意味があるが、ここは明らかに「来る」の尊敬語だ。「行ってきます」が敬語の「行って参ります」や打ちとけた「行って来るね」になったところで、動詞が重なる文構造も、その本来の意味も全く変わらない。同様に、ぶっきら棒に「おぅ、行って来い」などと応じたところで、やはり「行ってらっしゃい」と同じ意味の答えなのである。英語では「I'm going now」や「I'll be back soon」などは言うが、この2つを一緒にし、しかも日常表現として毎日使うということはしない。
「行ってきます」の応用編とでも思えるのが「焼き芋を買って来たよ」「カナダへ行って来ました」などで、これらも英語であれば後半の「and I came back」は全く蛇足である。やはり日本語話者の発想に「そうやってここに戻って来ましたよ」という「対話の場」を大切にする、ひいては相手への気配りが伺える。
出かけた後は自宅や会社に帰ってくる。その時に日本人はまたしても外国人に不可解な表現を使うのである。それが「ただいま」だ。「ただいま」とは言うまでもなく「只今」の意味で、直訳すれば「Right now」だが、こう言って帰って来る英語話者は見たことがない。何故日本人はこんな言い方をするのか。またしても学習者が頭を傾げる場面だ。
出迎える方がまた不思議な発話をする。「お帰りなさい」だが、その本来の意味を英訳するとナンセンス極まりない文となる。これはどう見ても「お食べなさい、お話しなさい」などと同じ構造の命令文ではないか。もう目の前に帰ってきた聞き手がいるのに「Please come/go back」などと頓珍漢なことを言うのだろう。
この受け答えは、「お帰りなさい」「ただいま」と発話の順序を逆にすると真意が分かりやすい。出迎えて「お帰りなさい」と言うのは、字句通りの「はやく帰ってきて」という祈りを、姿が見える直前、まさに文字通りの「ただいま」まで、唱えていた名残ではないだろうか。対話の場への帰還をどんなにか待っていたという気持ちほど、相手への気配り、思いやりを雄弁に物語るものはないと思う。それに応えて帰還者は不在の長さを詫びる。長いこと対話の場を離れてすまなかった、さぁ今、帰ったよ、という気持ちで日本人は「ただいま」と言うのだ。「ただいま」とは「たった今」なのである。
何という白熱、緊張した再会の場面を日本人は言語化しているのかと改めて驚くばかりだ。あたかも孵化した雛が殻の内側から、そして親の雌鳥が殻の外から同時に卵を突くように、両者が積極的に再会の場面に参加し、そして対話の場への復帰を言祝ぐのが我々日本語話者であると言えないだろうか。 (2008年1月)
応援のクリック、よろしくお願いいたします。











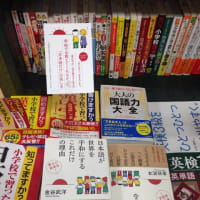

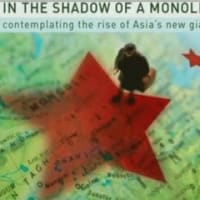
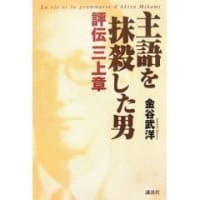
こうした体験はとても多いのだと思います。
でも、フランス語でも、短時間の行ってきますなら、Je reviens!があるし、今夜落ち合おうぜ、というときは、A ce soir!っていいますよね。
でも、この言葉は怖いです。なぜなら、Je reviens とか A ce soirって言われてしまったら、私は何時間でも相手を待ってしまいます。そこに貼り付けられてしまうのです。
(けど、実際はそんな絶対的なものでもないですよね?)
不確実な中に、祈りをこめて「早くかえってきれくれ」と願い、ぼんやりと関係性(時間・空間)の継続を担保するような言葉の中で育った私などは、フランス語が命令文のように聞こえてしまうのです。
話がそれますが、例えば、「いただきます」はフランス語でどうなるのでしょうか。
Bon appétit には違和感を感じています。
なぜなら、このBon appétitはどこに?誰に?向かって発せられる言葉なのですか。「有難う」の意味はないですか。
また、私などは「有難う」と言う代わりに「すみません」を使ってしまいます。
有難う、とストレートに言えないのです。
「こっちの気がすまないよ」ってなことなら、「だったら、頼まなきゃいいでしょ」という話になるが、そうもいかないのですけど。
これは先生がどこかで仰っていたように記憶しているのですが、「日本では、褒められても、決して『有難うございます』とは言うべきではない」という事と似ているのでしょうか。
ともかく、こんな私などにも、合理的な思考回路の人たちとうまく共存する希望はあるのでしょうか・・・。
つまり、自分の感情を、ちょっと他人に委ねちゃうっていう、甘えは、他人に対しては案外耐えがたいことなのよね、と反省することが多いのです。
はぁ、国際交流は難しいですね。
英語ではその場合に何か言うか、どう言うかを問題にしたのではなく、
日英語の表現を比較して双方の発想の違いを考察したのです。
すみません。だいぶ前に書かれたコメント、気づきませんでした。
ありがとうございます。
Je reviens!は「行って来ます」と確かにちょっと似てますね。
「行って」の部分がありませんけど。
お尋ねの「Bon appétit」は、「Bonjour」と同じ様に「そうなるように相手のために祈願する」表現でしょうね。同じ「ボン」で始まってますし。この稿で取り上げた「Good morning」と同じ発想で、仏語の場合もその前に「Je vous souhaite...」が隠れているのだと思います。
はい、国際交流は難しいです。でもそれだけに考察する甲斐があって、楽しくかつ面白いとも言えます。