管子嘉言録
◎始めに
以前、<管子>について触れる機会があったが、その時に奇抜な好言が目にとまり、いつかまとめて公開してみようと思ったのが動機で、その機会がやってきたという次第である。<管子>は、門人との共作だとか、一時の作ではないなどと言われ、管仲の独自性が疑われる批判もあるが、時代を超えた含みのある提言が多数見られるので、私見を加えながら順次紹介して行きたい。
1.管仲の評価。
管仲は主君の桓公を、初代の覇者に祭り上げた点が高く評価され、歴史書には名
臣として記録されているが、低い評価も多々見られる。
唐宋八大家の一人である蘇洵は、<管仲論>の中で「彼管仲者、何以死哉?」
と、その行動に疑問を呈している。更に無二の親友にして竹馬の友である鮑叔牙
を管仲が、剛(剛情)・愎(頑固)にして悍(凶暴)と評する件りが<韓非子>
に見られるが、これまたなんとも言えぬものがある。
管仲は、他人を利用するのが上手いのか、好感を持たれる先天的素質があるの
か、不思議な存在である。何れにしろ「管鮑の交わり」も、「桓公が覇者の先陣
を切った」ことも事実なのだから、管夷吾は、「人を導く巧みさ」に長けた素質
を持った人物と言えそうである。
一方覇者となった桓公について、韓非子が厳しい評価を下しているが、評価する
人が違えばこうも違うものかと感心する。
諸葛孔明に、管仲が理想の人として目標とされていたという言い伝えがあるが、
玄徳公と孔明の立場が桓公と管仲の立場に似ている處から出た話とも考えられ
る。
2.時代背景。
周王室の権威衰え、東遷して春秋時代に移行した時代に活躍した人物。
東周時代:前半時代(春秋時代)→五覇の時代(初代:齊の桓公、前651年)
後半時代(戦国時代)→戦国の七雄(前403年~)、諸子百家の時代。
[参考]
<論語、八佾>
「子曰、管仲之器小哉。」
子曰く、管仲の器は小なるかな。
<論語、憲問>
「問管仲。曰、是之人也、奪伯氏駢邑三百、伯氏飯疏食、没歯無怨言。」
管仲を問う。曰く、是の人や、伯氏の駢邑三百を奪い、伯氏は疏食を飯
いて、歯(よわい)を没するまで怨言無し。
「子路曰、桓公殺公子糾、召忽死之、管仲不死。」
子路が曰く、桓公が公子糾を殺し、召忽は之れに死し、管仲は死せず。
「子曰、管仲相桓公覇諸侯、一匡天下。民到于今受其賜。微管仲、吾其被
髪左衽矣。」
子曰く、管仲は桓公を相けて諸侯に覇たりて、天下を一匡す。民は今に
至るまで其の賜を受く。管仲微(な)かりせば、吾れは其れ髪を被り衽
を左にせん。
<孟子、公孫丑>
「曾西勃然不悅、曰、〈爾何曾比予於管仲。管仲得君、如彼其專也、行乎
國政、如彼其久也。功烈如彼其卑也。爾何曾比予於是。〉」
曾西は勃然として悅ばずして、曰く、〈爾は何んぞ曾ち予れを管仲に比
するや。管仲は君を得ること、彼の如く其れ專らにして、國政を行える
こと、彼の如く其れ久しかりしも、功烈は彼の如く其れ卑し。爾何んぞ
曾ち予れを是れに比するや。〉と。
(管仲の功績というものも、詰まらぬ覇道を行ったに過ぎない。)
<三国志、蜀書五、諸葛亮傳>→西晋時代の作。
「諸葛亮字孔明、・・・身長八尺、毎自比於管仲・樂毅,時人莫之許也。」
諸葛亮字は孔明、・・・身長は八尺、毎(つね)に自らを管仲・樂毅に比す
るも、時の人は之れを許すもの莫(すく)なし。
(この時期には自らを管仲・楽毅に比していたが、当時の人間でこれを
認める者はほとんどおらず。)
<蘇洵、管仲論>→北宋時代の作。
「夫國以一人興、以一人亡、賢者不悲其身之死、而憂其國之衰、故必複有
賢者而後可以死。彼管仲者、何以死哉?」
夫れ国は一人を以て興り、一人を以て亡ぶ。賢者は其の身の死を悲しま
ず、而して其の国の衰を憂ふ。故に必ず復た賢者有りて 而る後に以て死
す可し。彼の管仲なる者、何を以て死すや。」
蘇洵:唐宋八大家の一人。(蘇軾・蘇轍の父)
<韓非子、説林・上>
「16管仲、隰朋從於桓公而伐孤竹,春往冬反,迷惑失道,管仲曰:「老馬
之智可用也。」乃放老馬而隨之,遂得道。→「管仲随馬」
管仲、隰朋(しゅうほう)桓公に従がいて孤竹を伐ち、春往きて冬反
える。迷惑して道を失しなう。管仲曰く、「老馬の智用うべきなり」
と。乃ち老馬を放ちて之れに随がい、遂に道を得たり。」
<韓非子、十過>
「9・・・君曰:「鮑叔牙何如?」管仲曰:「不可。鮑叔牙為人,剛愎而上
悍。剛則犯民以暴,愎則不得民心,悍則下不為用,其心不懼。非霸者
之佐也。」・・・居一年余、管仲死。君遂不用濕朋而与豎?。?涖事三年、
桓公南遊堂阜。豎?率易牙衛公子開方、及大臣為乱。桓公渇餒而死南門
之寝公守之室。身死三月不収、虫出于戸。故桓公之兵、横行天下、為
五伯長、卒見弑於其臣而滅高名、為天下笑者何也。不用管仲之過也。
故曰、「過而不聴於忠臣、独行其意、則滅其高名、為人笑之始也。」
・・・君曰く、「鮑叔牙(ほうしゅくが)はいかん」。管仲曰く、「不可
なり。それ鮑叔牙の人となりや、剛愎(ごうふく)にして悍(かん)
を上(たっと)ぶ、剛なればすなわち民を犯すに暴をもってし、愎な
ればすなわち民心を得ず、悍なればすなわち下(しも)用さず、その
心懼(おそ)れず、覇者の佐に あらざるなり」。・・・居ること一年
余、管仲死す。君ついに濕朋を用いずして豎刁に与う。事に涖(の
ぞ)むこと三年、桓公、南のかた堂阜(どうふ)に遊ぶ。豎刁は易
牙、衛の公子開方、および大臣を率いて乱をなす。桓公渇餒(かつだ
い)して南門の寝、公守の室死す。身死して三月収められず、虫、戸
より出(い)ず。故に桓公の兵、天下に横行し、五伯の長となり、つ
いにその臣に弑(しい)せられて高名を滅し、天下の笑いとなるは何
ぞや。管仲を用いざるの過ちなり。故に曰く、「過ちて忠臣を聴か
ず、ひとりその意を行うは、すなわちその高名を滅ぼし、人の笑いと
なるの始めなり。
(令和04.12.01)










![<管子>形勢第二[形勢:天地自然の運行や形態の意。]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/33/76/b546abbd8859471b7d48992e9963c47c.jpg)
![<管子>形勢第二[形勢:天地自然の運行や形態の意。]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/6f/fc/ff4f1913453484b7fb27362c1bc38785.jpg)
![[气・氣]余論](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/60/cf/474d4603ef57f75d1b900d89556a851a.jpg)
![古漢籍に見る[氣]の思想⑥](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0e/89/decce3eb22007e8c6f956526b60c23af.jpg)
![古漢籍に見る[氣]の思想④](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0f/40/60a584fecf8d13614520cfa41d100484.jpg)
![古漢籍に見る[氣]の思想④](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/30/a0/4470c4c67b629a3baa3eae9fcedc163d.jpg)
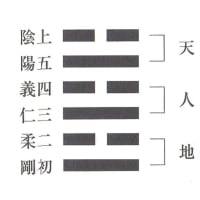
![古漢籍に見る[气]の思想①](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/5b/c8/369d5c23d0dad9a542f1e0e44bb5e297.jpg)

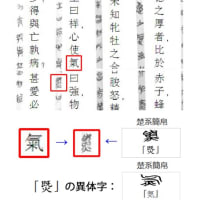
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます