古漢籍に見る[氣]の思想⑥
10.<荘子>に見る『氣』の思想、[戰國(公元前350年~公元前250年)]成立
引き続き、古漢籍について見てみよう。
『氣』の字は、全てで44個登場する。その内、『氣』字単独で用いられてい
る数は18個、成語は以下の15種類、24個である。
①物理的実体(形而下的対象)
氣:16 雲氣:3 六氣之辯:1 噫氣:1 血氣:1 天氣:1
地氣:1
②心理的実体(形而上的対象)
人氣:1 神氣:2 志氣:1
③総合的実体(私的追加区分)
氣:2 雲氣:3 六氣:2 氣母:1 一氣:2 衡氣機:1
邪氣:1 純氣:1 馮氣:1
珍しい成語としては、以下のようなものがある。すなわち、
噫氣:あいき。大地の欠伸で吐き出された息。
氣母:きぼ。元氣の本原。(元氣を構成する最も根本的な実体)。
衡氣機:氣の巡りを調和させる働き。
馮氣:(ヒョウキ)。成氣。脂ぎった盛んな血氣。
特に記する物も無いが、『氣』と萬物生成の関連に触れた記述があるので、触れておこう。<外篇、田子方>に「天から生まれて地上に降り立った最も根源的で冷徹な陰氣と、地から発して天に升った最も根源的で熱血の陽氣とが通じ合って和合すると、そこから萬物が化生する。そこには始原と為る物があるようだが、目にすることは出来ない。陰陽の二氣は盛衰を繰り返しながら化生を繰り返すが、その詳細は感知出来ない。死滅する物はどこかに帰って行き、生成する物はどこからか萌え出てきて、その始めと終わりとが互いに連続して循環を繰り返し、其の窮まる所を知らない。その働きが無始・無終・無限だからこそ万物を生み出す核心と成り得るのである。」とある。荘子の『氣』の思想は、<外篇、知北遊>で述べられている『通天下一氣耳』なる一文に集約されていると見て良さそうである。これは先に触れた老子の、『道生一,一生二,二生三,三生萬物。』の思想を受け継いだものであることは、云うまでもない。 更に言えば、現代に於ける『萬物と素粒子』の発想に通じるものがあるところは、それ以前のものと変わりはないのである。
[参考]
<外篇、知北遊>
「1生也死之徒,死也生之始,孰知其紀!人之生,氣之聚也,聚則為生,散則
為死。若死生為徒,吾又何患!故萬物一也,是其所美者為神奇,其所惡
者為臭腐、臭腐復化為神奇,神奇復化為臭腐。故曰:『通天下一氣
耳。』。聖人故貴一。」
生なるは死の徒(ともがら)、死なるは生の始め、孰(たれ)か其の紀
(はじめ)を知らん!人の生なるは、氣の聚(あつ)まれるものなりて、
聚まれば則ち生と為り、散ずれば則ち死と為る。若し死生を徒と為せ
ば、吾れ又た何をか患えん!
故に萬物は一(おな)じなりて、是れ其の美とする所の者を神奇と為
し、其の悪とする所の者を臭腐(しゅうふ)と為すも、臭腐は復た化し
て神奇と為り、神奇は復た化して臭腐と為る。故に曰く:『天下を通じ
て一氣のみ』と。聖人は故に一を貴ぶ。
『通天下一氣耳。』:<莊子、內篇、逍遙遊>にある『旁礡萬物以為
一。』と同じ意味合いのもの。
<外篇、田子方>
「4・・・至陰粛粛、至陽赫赫。粛粛出乎天、赫赫発乎地。両者交通成和、而物
生焉。或為之紀、而莫見其形。消息満虚、一晦一明、日改月化、而莫見
其功。死有所乎帰、生有所乎萌、始終相反乎無端、而莫知乎其所窮。非
是也、且敦為之宗。」
・・・至陰は粛々たり、至陽は赫々たり。粛々は天に出で、赫々は地に発
す。両者交々通じて和を成し、而して物生ず。或いは之が紀(はじめ)
を為すも、其の形を見ること莫し。消息満虚し、一(ある)いは晦(く
ら)く一いは明るく、日に改まり月に化するも、其の功を見ること莫
し。死には帰するに所有り、生には萌(きざ)す所有り。始めと終わり
と無端に相い反りて、其の窮まる所を知ること莫し。是れに非ざれば、
且(は)た孰れかこれが宗たらん。
・素粒子

[感想]
荘子が表現している「至陰粛粛、至陽赫赫。粛粛出乎天、赫赫発乎地。」は、列子の言う「清軽者上為天、濁重者下為地。」と意を同じくするものであろうが、何ともややこしい表現である。「万物が陰と陽の根源的な二気が和合して万物が化生する」と言う発想が、二千数百年も前に出現していたことに、驚嘆する次第。現代科学者には失礼かもしれないが、陽電荷を持った陽子と陰電荷を持った電子を想像させるような発想に驚くばかりである。発端の<老子の道徳経>に有る「「道生一,一生二,二生三,三生萬物。萬物負陰而抱陽,沖氣以為和。」に始まって、多くの後年の諸儒家が知恵を絞って肉ずけした結果とは言え、単純ではあるがその奥深さには敬意を表すべきであろう。 (令和3.12.14)










![<管子>形勢第二[形勢:天地自然の運行や形態の意。]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/33/76/b546abbd8859471b7d48992e9963c47c.jpg)
![<管子>形勢第二[形勢:天地自然の運行や形態の意。]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/6f/fc/ff4f1913453484b7fb27362c1bc38785.jpg)
![[气・氣]余論](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/60/cf/474d4603ef57f75d1b900d89556a851a.jpg)
![古漢籍に見る[氣]の思想⑥](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0e/89/decce3eb22007e8c6f956526b60c23af.jpg)
![古漢籍に見る[氣]の思想④](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0f/40/60a584fecf8d13614520cfa41d100484.jpg)
![古漢籍に見る[氣]の思想④](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/30/a0/4470c4c67b629a3baa3eae9fcedc163d.jpg)
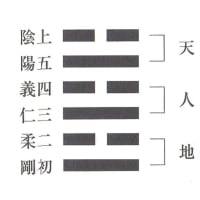
![古漢籍に見る[气]の思想①](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/5b/c8/369d5c23d0dad9a542f1e0e44bb5e297.jpg)

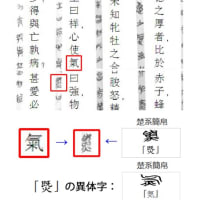






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます