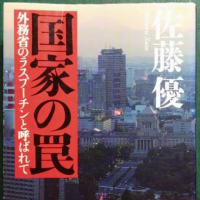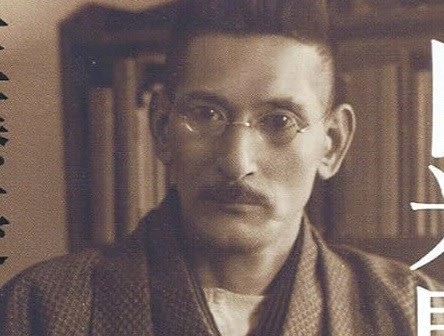
創価学会の「内在的論理」を理解するためといって、創価学会側の文献のみを読み込み、創価学会べったりの論文を多数発表する佐藤優氏ですが、彼を批判するためには、それこそ彼の「内在的論理」を理解しなくてはならないと私は考えます。
というわけで、こんな本を読んでみました。
佐藤優/大川周明「日米開戦の真実-大川周明著『米英東亜侵略史』を読み解く」

興味深い内容でしたので、引用したいと思います。
この本の特徴は、戦前の思想家・大川周明の著書である『米英東亜侵略史』のテキストを2部に分けて再現し、その間に著者・佐藤優氏の解説を挟み込むという形式をとっていることです。
この形式は、佐藤氏が創価学会系の雑誌『潮』に記事を連載するときや、その著書「池田大作研究」を書いた時のスタイルと共通するものです。
さらに言えば、私がいろいろな本を読んでブログで引用する際に、記事の最後に【解説】として私見を述べていますが、そのスタイルにも通じます。
そこで、読者が読みやすく理解しやすいように、あたかも佐藤氏がこのブログを書いているかのように、私のブログのスタイルをまねて、この本の内容を再構成してみました。
必要に応じて、改行したり、文章を削除したりしますが、内容の変更はしません。
なるべく私(獅子風蓮)の意見は挟まないようにしますが、どうしても付け加えたいことがある場合は、コメント欄に書くことにします。
ご理解の上、お読みください。
日米開戦の真実
――大川周明著『米英東亜侵略史』を読み解く
□はじめに
■第一部 米国東亜侵略史(大川周明)
■第二部「国民は騙されていた」という虚構(佐藤優)
□第三部 英国東亜侵略史(大川周明)
□第四部 21世紀日本への遺産(佐藤優)
□あとがき
米国東亜侵略史(大川周明)
第六日 敵、東より来たれば東条
国民から湧き上がってきた大なる憂い
ロンドン会議は、日本現代史に対して深刻無限の意義を有しております。第一次世界戦以来、日本の上下を支配してきた思想は、英米を選手とする自由主義・資本主義と、ロシアを選手とする唯物主義・共産主義であります。深く思いを国史に潜め、感激の泉を荘厳なる国体に汲み、真箇に日本的に考え、日本的に行わんとする人々は、たとえあったにしてもその数は少なく、その力は弱かったのであります。
ところがロンドン会議は、それだけにこれら少数の人々のみならず、多数の国民の魂に強烈なる日本的自覚を呼び起こす機縁となったのであります。そしてロンドン会議の責任者・浜口首相は、遂に国民義憤の犠牲となったのであります。日本はワシントン会議以来、アメリカとの政治的決闘において、常に負け続けてきたのであります。いまやロンドン会議に勝ち誇れるアメリカを見て、この上負けては遂に息の根が止められるぞという大なる憂いが、国民の魂の底から湧き上がってきたのであります。それは我らの先輩が黒船の脅威によって、幕府も忘れ各自の藩も忘れて尊皇攘夷のために奮い起ったと同じことで、米国国務長官スティムソンは、百年以前にペリーが日本に対して務めた同じ役割を務めたのであります。
ロンドン会議に至るまで、日本はアメリカの東洋進出に対して受け身であり、アメリカの対日政策に対して常に譲歩してきたのであります。そのアメリカの政策が余りに傍若無人であったために、アメリカの政治家のうちにさえ、日本の憤激を買って戦争を誘発せぬかと心配した人が少なくなかったほどであります。
例えば、加州における排日問題の時でも、大統領ルーズヴェルトは、日本人はこのような侮辱を甘受する国民でないと信じていたので、フィリピン陸軍司令官ウッドに対し、何時日本軍の攻撃を受けても戦い得るよう準備せよという命令を発し、しかも万一日米戦争になれば、フィリピンは日本のものとなるであろうと甚だ憂鬱であったのであります。そして心配に堪えかね、フィリピン派遣という名目で陸軍長官タフトを東京に寄越したのでありますが、タフトが来てみると、国民こそ激しく憤慨しておりましたが、政府は毛頭そのようなことを考えておりません。そこでタフトは東京から「日本政府は戦争回避のために最も苦心を払いつつあり」と打電して、ルーズヴェルトの愁眉を開かせております。
その後十数年を経て、移民問題が再び日本国民を憤激させたときも、余りに日本の体面を傷つけては戦争になるかもしれんと心配した米国政治家が少なくなく、当時の駐日米国大使モリスのごときもその一人であります。ただこのときも日本政府は、干戈(かんか)に訴えても国家の面目を保とうなどとは夢にも考えていなかったのであります。
最後に1934年、埴原大使をして、無法に日本人排斥法を通すならば「重大なる結果」を生ずるだろうと抗議させましたが、かえって上院議員ロッジのために「日本はアメリカを脅迫するつもりか」と開き直られ、もともと覚悟を決めての抗議でなかったのでありますから、結局いかなる結果をも生ぜずに済みました。
ところがロンドン会議以後、事情は全く一変したのであります。政府は依然として英米に気兼ねしながら、国際的歩みを徐々に進めんとしたにかかわらず、国民は日本国家の根本動向を目指して闊歩し始めたのであります。政府はロンドン会議において低く頭を下げたにかかわらず、国民は昂(たか)く頭をもたげて、アメリカ並びに全世界の前に、堂々と進軍をはじめたのであります。この日本の進軍は、実に満州事変においてその第一歩を踏み出したのであります。
満州事変
1928年、父張作霖の後を継いで満州の支配者となった張学良は、南京政府及び多年にわたるアメリカの好意を背景として、東北地帯における政治的・経済的勢力の奪回を開始したので、満州における日本の権益に対する支那側の攻撃は年と共に激化し、排日の空気は全満に漲らんとするに至りました。もともと満州における日本の権益は、ポーツマス条約に基づくものであります。もし当時日本が起ってロシアの野心を挫かなかったならば、満州・朝鮮は必ずロシアの領土となったであろうし、支那本部もやがて欧米列強の俎板(まないた)の上で料理されてしまったことと存じます。日露戦争における日本の勝利は、ただロシアの東洋侵略の歩みを阻止したのみならず、白人世界征服の歩みに、最初の打撃を加えた点において、深甚なる世界史的意義を有しております。このとき以来日本は、朝鮮・満州・支那を含む東亜全般の治安と保全とに対する重大なる責任を荷い、かつその重任を見事に果たしてきたのであります。
その間にいかにアメリカが日本の意図を理解せず、日本の理想を認識せず、間断なく乱暴狼藉を働きかけてきたかは、三日にわたって述べた通りであります。このアメリカの後援を頼み、南京政府の排日政策に呼応した満州政権は、遂に暴力をもって日本に挑戦してきたのであります。それは取りも直さず、1931年9月18日の柳条溝事件であります。そして時の政府が断じてこれを欲しなかったにもかかわらず、日本全国に澎湃として漲りはじめた国民の燃える精神が、遂に満州事変をしてその行くべきところに行き着かしめ、大日本と異体同心なる満州国の荘厳なる建設を見るに至ったのであります。
我らは満州事変が、こうした事変の発生を最も憎みかつ恐れていた幣原(しではら)氏が、日本の外交を指導していた時代に起こったことを考えて、歴史の皮肉を想わざるを得ぬものであります。しかしながら満州事変は、決して日本にとって不利なる時期に起こったのではありません。運命は明らかに日本に向かって微笑していたのであります。すなわちこの事変の起こった1931年の夏の末には、世界を挙げて大不景気の影響を深刻に感じなかったことはなく、とりわけイギリスとアメリカは、ヨーロッパ及び本国において、経済的混乱に陥っていたのであります。
すなわちこの年は信用機関の没落、イギリスの金本位制離脱、フーヴァー大統領のモラトリアムなど、欧米の政府及び国民を途方に暮れさせた重大問題の頻発した年であります。さればこそスティムソンは、その著『極東の危機』の中で「もし誰かが、外国の干渉を受けずに済むと考えて、満州事変を計画したとすれば、無上の好機会を掴んだものと言わねばならん」と申しております。満州事変はそれほど国際的に好都合のときに起こったので、日本のためには甚だ幸運であったと存じます。
ただしアメリカは、もちろん手をこまねいて見ているわけはありません。国務長官スティムソンは事変勃発の4日後、すなわち9月22日に駐米日本大使を経ていわゆる「熱烈なる覚書」を日本政府に交付しております。その中で彼は「過ぐる4日間、満州において展開せられつつある事態には、夥しき数の国々の道徳・法律及び政治が関係している」と、居丈高になっております。その後に至り満州事変に対して執った国際連盟の行動は、一つとしてスティムソンと相談しなかったものがなく、またその指図に由らぬものがなかったのであります。
国際連盟は旧秩序維持の機関
当初スティムソンは、幣原外相に大なる期待をかけていました。国際連盟、四ヵ国条約、九ヵ国条約、不戦条約、総じてこれらの世界現状維持のための約束に欣然参加し来れる日本の外務省は、このたびとてもアメリカの意図を無視した行動を取るまいと考えていたのであります。これは決して私の想像でなく、スティムソン自身が同年9月23日、すなわち「熱烈なる覚書」を日本に叩きつけた翌日の日記に「予の問題は、アメリカの眼が光っているぞということを日本に知らせること、及び正しい立場にある幣原を助けて彼の手によって事件の処理を行わしめ、これをいかなる国家主義煽動者の手にも委ねてはならぬということである」と書いております。
スティムソンは、これも彼自身の言葉によれば、日本の外務大臣が日本に燃え上がった国家主義の炎々たる焔を消し止め、過去及び現在の征服を中止して、日本をして九ヵ国条約及び不戦条約に再び忠実ならしむべきことを希望し、かつその可能を信じていたのであります。そして幣原外相も恐らくこの希望に添いたかったに相違ありませんが、事変の発展はスティムソンの希望を完全に打ち砕き、彼は矢継ぎ早に「不愉快なるニュース」のみを受け取らねばならなかったのであります。そしてこの年の12月に民政党内閣が倒れ、翌1932年1月、日本軍が錦州を占領するに及んで、スティムソンは遂に「談合によって満州問題を解決せんとした予らの企図は失敗に終わった」と告白しております。そうして今度は「満州の平和攪乱者に対して、全世界の道徳的不同意を正式に発表する手段を取り、もし可能ならば日本の改心を要求する圧力となるべき制裁を加える」と決心したのであります。
彼はこの目的のために国際連盟を利用せんとしたのであります。国際連盟は、スティムソンの属する共和党とは反対の政党、すなわち民主党の大統領ウィルソンを生みの親とし、しかも共和党のために勘当を受けたる子どもであります。それが今や共和党の国務長官が、自ら勘当した子どもを日本制裁のために働かせようとして、一切の鞭撻と激励とを与えたのであります。彼は1932年春、カリフォルニアとハワイとの間において、全米国艦隊の大演習を行わしめ、演習終了後もこれを太平洋に止めて日本を威嚇しました。そして一方絶えずロンドンとジュネーヴに圧力を加え、この年3月12日には、連盟総会をして2月18日に独立を宣言した満州国に対し、不承認の決議をなさしめました。それからこの年11月末には、国際連盟はいわゆるリットン報告に基づいて、日本に対して満州を支那に返還せよという宣告を下したのであります。その後この宣告を巡って長い劇的な討論が行われましたが、遂に我が松岡代表が「欧羅巴やアメリカのある人々は、いま日本を十字架にかけんとしている。それでも日本人の心臓は、恫喝や不当なる抑制の前には鉄石である」と叫んで、日本の決意を世界万国の前に声明したのは、英米に対する宣戦詔勅を渙発した12月8日と、日も月も同じ十年前の12月8日であります。
そして翌1933年2月14日(原文ママ)、リットン報告書が遂に連盟総会によって採択されるに及んで、松岡代表は即刻会場を退出し、日本はたちどころに国際連盟を脱退したのであります。国際連盟は言うまでもなく世界旧秩序維持の機関であります。それゆえに我々は、復興亜細亜を本願とすべき日本が、世界の現状すなわちアングロ・サクソンの世界制覇を永久ならしめんとするこのような機構に加わることに、当初より大なる憤りを感じていたのであります。それなのにスティムソンの必死の反日政策が、日本をして国際連盟より脱退しめる直接の機縁となったことは、これまた歴史の皮肉と申さねばなりません。
来るべき日が遂に来た
さてスティムソンは、1932年12月下旬、次期大統領に選ばれたフランクリン・ルーズヴェルトから、外交政策について相談したいからという招待を受け、紐育(ニューヨーク)ハイド・パークのルーズヴェルト邸で、長時間の会談を行いましたが、その後数日を経てルーズヴェルトは、米国の対外政策において両者の意見は完全に一致したことを発表しております。したがって現大統領の東亜政策または対日政策が、スティムソンのそれと同一なるべきことは、すでにこのときより明白であったのであります。
スティムソン政策の拠って立つところはあくまでも九ヵ国条約及び不戦条約を尊重し、これに違反する行動はすべて不法なる侵略主義と認め、徹底してこれを弾劾するというものであります。したがってこの政策を完全に継承するルーズヴェルトは、今回の支那事変に際しても、当初より日本の行動を不法と断定し、支那の抗戦能力強化を一貫不動の方針として、あらゆる援助を蒋介石に与えてきたのであります。
このことはルーズヴェルトが、1937年10月5日、シカゴにおいて試みたる最も煽動的な演説の中に、極めて露骨に言明されております。――「条約を蹂躙し、人類の本能を無視し、今日のごとき国際的無政府状態を現出せしめ、我らをして孤立や中立をもってしてはこれより脱出し得ざるに至らしめし者に反対するために、アメリカはあらゆる努力をなさねばならぬ」。
そしてまさしくこの言明の通り、日米通商条約を廃棄し、軍需資材の対日輸出を禁止し、資金凍結令を発布して、一歩一歩日本の対支作戦継続を不可能ならしめんとすると同時に、蒋政権の抗戦能力を強化するためには、一切の可能なる精神的並びに物質的援助を惜しまなかったのであります。
日本は、もしアメリカが東亜における新秩序を認めさえすれば、東亜におけるアメリカの権益をできるだけ尊重し、かつアメリカのいわゆる門戸開放主義も、この新秩序と両立し得る範囲内においては十分にこれを許容する意図をもっていたのであります。ところがアメリカは、東亜新秩序建設を目的とする我が国の軍事行動をもって、あくまでも九ヵ国条約・不戦条約に違反する侵略行為とし、頑としてその見解を改めざるのみならず、東亜新秩序はやがて世界新秩序を意味するがゆえに、このような秩序――アングロ・サクソン世界制覇を覆すに至るべき秩序の実現を、その根底において拒否するのであります。
しかもこれらは決して現大統領の新しき政策にあらず、実にアメリカ伝統の政策であります。すなわちシュワードによって首唱され、マハンによって理論的根拠を与えられ、大ルーズヴェルトによって実行に移された米国東亜侵略の必然の進行であります。この伝統政策あるがゆえに、日米両国の衝突は遂に避くべからざるものであり、今や来るべき日が遂に来たのであります。
弘安四年、蒙古の大群が多々良浜辺に攻め寄せたとき、日本国民は北条時宗の号令の下、たちどころにこれを撃退しました。いまアメリカが太平洋の彼方より日本を脅威する時、東条内閣は断固膺懲(ようちょう)を決意し、緒戦において海 戦史上振古未曾有の勝利を得ました。
敵、北より来たれば北条、東より来たれば東条、天意か偶然か、めでたきまわり合わせと存じます。熟々考え来れば、ロンドン会議以後の日本は、目に見えぬ何者かに導かれて往くべきところにぐんぐん引っ張られて往くのであります。この偉大なる力、部分部分を見れば小さい利害の衝突、醜い権力の争奪、些々(ささ)たる意地の張り合いによって目も当てられぬ紛糾を繰り返している日本を、全体として見れば、いつの間にやら国家の根本動向に向かって進ませていくこの偉大なる力は、私の魂に深き敬虔の念を呼び起こします。私はこの偉大なる力を畏れ敬いまするがゆえに、聖戦必勝を信じて疑わぬものであります。
【佐藤氏による解説】
アメリカの「二重基準(ダブルスタンダード)」外交
(つづきです)
満州国の問題でアメリカは国際連盟を通じて、さらに側面からも日本に圧力を加えてくる。アメリカは国際連盟の加盟国ではないにもかかわらずだ。このような手法は卑怯である。そもそも国際連盟はウィルソン米大統領(民主党)の提唱で生まれたものだが、アメリカ議会で共和党が反対したため、アメリカは国際連盟加盟国ではなかった。アメリカが国際連盟を通じて日本に圧力をかけたいのならば、まず国内の意見対立を克服し、国連に加盟してから行動するのが筋である。
国際連盟での審議にあわせて、1932年春、アメリカはカリフォルニアとハワイの間で海軍大演習を行い、演習終了後も艦隊を太平洋に残して日本を牽制した。
満州国は1932年2月18日に独立を宣言したが、国際連盟は翌1933年2月24日に不承認を議決する。そのときの議決は、賛成42カ国、反対1カ国(日本)、棄権1カ国(タイ)で、日本の国際的孤立は決定的になる。しかし、大川周明は国際連盟からの脱退を肯定的に評価する。
国際連盟は言うまでもなく世界旧秩序維持の機関であります。それゆえに我々は、復興亜細亜を本願とすべき日本が、世界の現状すなわちアングロ・サクソンの世界制覇を永久ならしめんとするこのような機構に加わることに、当初より大なる憤りを感じていたのであります。
大川のこの評価は、国際連盟は資本家階級の利益を体現したブルジョア国家の連合体に過ぎないと批判したソ連と基本認識を共有しているのである。
大川周明は、アメリカの外交政策を分析して4つの矛盾を具体的に指摘する。
①自ら国際連盟を提唱しながら、それに加わらない。それでいて加盟国でないにもかかわらず国際連盟を用いて日本に圧力を加える。
②不戦条約を締結して、戦争を国策遂行の道具にしないと約束しているにもかかわらず、攻撃能力のある世界一の海軍を保有している。
③大西洋では、英米海軍の10対10の比率が、平和を害するものでないと言いながら、太平洋においては日米海軍の7対10の比率でさえ、平和に対する脅威であると強弁する。
④ラテン・アメリカに対しては門戸閉鎖主義を固執しながら、東アジアに対しては門戸開放主義を強要する。例えば、日本人漁業者が、メキシコのマグダレナ湾頭に土地を租借しようとしたとき、これがアメリカのモンロー主義に反するという決議案がアメリカ上院を通過している。他方、東アジアにおいて日本が占める地位はアメリカがメキシコやニカラグアで占める地位の十分の一にも及ばないのに、門戸開放主義の名において日本の権益を認めようとしない。
アメリカの行動はあまりに矛盾に満ちていて、利己的なのである。しかも自らの過ちを反省しない。大川は、「アメリカの乱暴狼藉このようであるにもかかわらず、世界のいかなる一国もアメリカに向かって堂々とその無理無法を糾弾せんとする者がなかったのであります」と指摘する。そして、アメリカという病理現象を治癒することが日本の歴史的責務であるという方向に考えを進めていくのである。そして『米英東亜侵略史』の「米国東亜侵略史」篇を以下のように締めくくる。
弘安四年、蒙古の大群が多々良浜辺に攻め寄せたとき、日本国民は北条時宗の号令の下、たちどころにこれを撃退しました。いまアメリカが太平洋の彼方より日本を脅威する時、東条内閣は断固膺懲(ようちょう)を決意し、緒戦において海戦史上振古未曾有の勝利を得ました。
敵、北より来たれば北条、東より来たれば東条、天意か偶然か、めでたきまわり合わせと存じます。
熟々考え来れば、ロンドン会議以後の日本は、目に見えぬ何者かに導かれて往くべきところにぐんぐん引っ張られて往くのであります。この偉大なる力、部分部分を見れば小さい利害の衝突、醜い権力の争奪、些々(ささ)たる意地の張り合いによって目も当てられぬ紛糾を繰り返している日本を、全体として見れば、いつの間にやら国家の根本動向に向かって進ませていくこの偉大なる力は、私の魂に深き敬虔(けいけん)の念を呼び起こします。私はこの偉大なる力を畏れ敬いまするがゆえに、聖戦必勝を信じて疑わぬものであります。
大川は、日本の現状を決して肯定的に評価しているわけではない。日本国内では、「小さい利害の衝突、醜い権力の争奪、些々たる意地の張り合いによって目も当てられぬ紛糾を繰り返している」のであるが、大川はロンドン軍縮会議の後、何か目に見えない大きな力に引き寄せられて、日米開戦という現実に至ったのだという認識を率直に吐露している。もっともこの引き寄せられた先にはアメリカの「オレンジ計画」が口を開けて待っていたのである。
大川は「勝算」をどう見ていたか
『米英東亜侵略史』における日米開戦に至る経緯については、アメリカの文献をよく読み込んだ上での実証性に富むものであった。しかし、大川は戦争の今後の展望については、「敵、北より来たれば北条、東より来たれば東条、天意か偶然か、めでたきまわり合わせと存じます」、「想えば1941という数は、日本にとって因縁不可思議の数であります。元寇の難は皇紀1941年であり、英米の挑戦は西紀1941年であります」とレトリックで受け流し、この開戦に向けた大きな力を敬うが故に聖戦必勝を疑わないなどという没論理的な発言をしている。大川は日本の国家主義者の中では、論理整合性や経済統計を重視する数少ない論客である。筆者が見るところ、大川は軍事行動で日本がアメリカやイギリスに勝利することは不可能であると考えていた。むしろ戦争を契機に、日本国家と日本人が復古的改革の精神で団結し、アジアの同胞から信頼され、新たな世界システムを作る端緒を掴めば、そのときに軍事力以外の力、すなわち外交力や国家としての道義の力でアメリカ、イギリスと折り合いをつけることができる可能性が あるという認識をもっていたのではないかと思われる。
開戦当初、戦勝気分で国民が浮かれるなかで、彼(大川)は「[戦争は]冥途の旅の一里塚目出度くもなし目出度くもなし」と詠んだという。これは「門松は冥途の旅の一里塚目出度くもあり目出度くもなし」という一休の歌をもじったものであり、彼が戦争の行く末を案じていたことがうかがえる。(大塚健洋『大川周明――ある復古革新主義者の思想』中公新書、1995年、174頁)
それではこれまでたどってきた大川周明の日米開戦の理由説明について、その意義と限界を簡潔に整理しておきたい。
まず、大川の認識を整理すると次のようになる。
①日米戦争は帝国主義戦争との性格が強い。特に米西戦争以降、アメリカが太平洋とアジアを支配するという国家戦略をもって着実に歩みを進めた点が実証的に説明されている。つまり交通が発達して、日本という小世界とアメリカという小世界が本格的に切磋琢磨する世界史の時代が到来したので、戦争が起きるのである。
②軍縮や国際連盟といった類の国際秩序は、欧米列強が自己に都合がよい旧体制を維持するための方便に過ぎない。究極的に信頼できるのは自国と自国民の力だけだ。
③国家は道義性を失ってはならない。アメリカのように建前と本音が分離した国家は国際秩序の撹乱要因になるので、整理する必要がある。日本はアメリカと「棲み分け」を提案しているに過ぎないのに、アメリカは北米への日系移民を一切受け入れないようになった。さらに中南米への日本の進出も認めないという門戸閉鎖政策をとっているにもかかわらず、日本の勢力圏である中国には門戸開放政策を唱え、露骨に利権を追求している。折り合いがつかない以上、戦争による問題の解決もやむを得ない。
筆者から見て、大川の言説で最も評価できるのはそのリアリズムだ。アメリカの帝国主義的変質を実証的に、一般国民にわかりやすく説明している。帝国主義は必ず植民地主義を伴う。大川が反植民地主義の観点から帝国主義を批判するが、さらにその背後に国家には道義が不可欠であるという信念がある。国際関係を論ずる識者は、理念先行の非現実的平和主義陣営と国家の軍事力や経済力にだけ目が奪われ、道義性を冷笑する力の論理の信奉者の陣営に分かれがちであるが、大川はそのどちらにも属さない。道義性とリアリズムを大川なりの方法で統合しようとしているのである。
確かに日本は太平洋戦争に敗れた。歴史で「もし○○がなかったならば」と問うことには思考実験以上の意味はないが、あの状況で戦争を避け、アメリカの理不尽な要求を呑んでいても、日本にとってよいシナリオにはならなかったと筆者は考える。日本は徐々にアメリカへの従属を強め、植民地にはならずとも保護国のような状態になった可能性も十分ある。あるいは反米、植民地解放運動が高揚した場合は、そこにソ連が働きかければ、日本が社会主義化した可能性もある。国家にも個人にも運不運がある。急速に帝国主義化、軍事大国化を遂げたアメリカと太平洋をはさんだ隣国という地政学的状況におかれた日本は「運が悪かった」と諦めるほかないというのが筆者の偽らざる見解だ。
大川の限界は『米英東亜侵略史』の後半部分、「英国東亜侵略史」で明らかになる。近代化において欧米列強の植民地にならなかった日本は、中国を含むアジアの諸民族国を植民地支配のくびきから解放しようと真摯に考え、行動した。しかし、後発帝国主義国である日本は基礎体力をつけなくてはならない。そのために、期間を限定して、アジア諸国を日本の植民地にすることはやむを得ないと考えた。ここに日本人の民族的自己欺瞞が忍び込む隙ができてしまった。
「あなたを痛みから解放するために、あなたに一時的に痛みを加えます」というのは外科手術が前提としている論理であるが、これを国際政治に適用した場合、痛みを追加的に加えられた民族にその理屈は理解されないのである。イギリスのような老獪な帝国主義国は、植民地住民の人権などはじめから考えておらず、また植民地は帝国を維持するために不可欠と考えていた。そのために植民地住民に対する圧迫をほどほどにしていた。相手にどの程度の痛みがあれば、どの程度の反発があるかということを冷徹に計算していたのである。植民地支配の打破を真剣に考えていたからこそ日本はアジア諸国に痛みを与えていることに気づかなかった。ここに大川のみならず、高山岩男や田邊元といった京都学派の優れた思想家が落ちていった罠があるのだ。
構成・文責:獅子風蓮