最近時間が取れないのもあり、またストレスのたまる出来事もあり、なかなかブログが更新できなかった。あまり気負って書くものでもないわけだが、なかなかまとまった文章にならなかった。
さて、ディルタイ「精神科学序説Ⅰ」(『ディルタイ全集』第1巻所収)をやっと読了した。ただ全集には「精神科学序説」の「草稿」も収録されており、理解を助けるためにも、これも読んでしまおうと思う。そのため「精神科学序説Ⅱ」は第2巻に所収されているが、これを読むのはもう少し先になりそうだ。「精神科学序説Ⅰ」の後半は哲学の歴史であり、同時に歴史哲学にもなっているような内容である。ディルタイはギリシャ哲学から中世哲学までの哲学史を概括しながら、形而上学がいかにして近代において、「精神科学」と「自然科学」へと分かれていくのかを論じている。まずディルタイは形而上学を特徴づけるのであるが、そこではアリストテレスの『形而上学』に現れる「不動の動者」という二律背反に注目するとわかりやすい。この形而上学に貫かれている問題意識は、有限と無限の問題であり、永遠と生成、運動と静止を二律背反のまま、この世界を構成している根源として理解するというものだ。即ちこの世界には運動があり、生成があり消滅があり、それは有限の時間の内に生起するのであるが、この有限の時間内の生成変化や運動を可能にしている、無時間的で恒常的な根源が存在しているはずだということである。つまり、変化を可能にしている変化しない根源、「不動の動者」という二律背反を思考する法則を発見することこそが、形而上学の使命ということになるだろう。
これはキリスト教の「神」にも引き継がれる問題である。単純化していえば、「神」は必然によって世界を創造しているはずであるが、被造物は偶然性や不完全性、あるいは悪を内包している。「神」がこの世界の必然性そのものだとしたら、何故世界に偶然性が存在するのか。この「神」と被造物の間の神学における二律背反の問題は、形而上学が思考してきた「不動の動者」の二律背反を引き継いでいる。この二律背反を解決するために汎神論や「神」からの「流出」の問題などが提起されることになる。ここで横道にそれるが、僕は学生時代一般教養の講義でアンセルムスの『プロスロギオン』の講義を受けて、所謂アンセルムスの神の存在証明に感銘を受けたことがある。確か、その講義のレポートは、アンセルムスの神の存在証明を批判し、論理的に何が誤謬であるのかを論じなさい、というもので、まさしく『プロスロギオン』の存在証明は、この二律背反の問題を含んでおり、何の哲学的訓練も受けていない学生であったが、そのレポートを書くのに妙なやりがいを感じた。そして、思考するとはこういうことを言うのか、という〈大学的〉(?)な興奮を覚えた、と記憶している。偶然履修した5人ほどしか聴講していない、後期の5限目で薄暗い教室での講義であったが、今でも鮮明に記憶している。
さて、そのような「神」と世界の二律背反の問題は古代と中世の形而上学の二律背反として現れているが、近代になるとそれは「主観」や「心」の問題になる。デカルトのcogitoの問題となり、カントで言うならば主観における悟性と感性の二律背反的構造を、構想力や理性が代補するという問題である。人間は自然科学的、力学的には法則の必然性に従属させられているが、しかし、理性という自律的な内なる道徳律によってそれと対峙している。これが法則に従属させられている「物」と「動物」と、理性の自律性を有する人間を差異化するわけだ。そして、この二律背反を橋渡しするのは、「自由」になるわけだが、それ故「自由」はこの二律背反が人間の主観に構造的に内在していなければ存在しないわけである。この自然科学的、力学的な法則に従属する、〈物体〉や〈動物〉としての人間と、それに理性によって対峙し、そこで裂け目としての〈深淵=自由〉に晒される、まあ〈現存在〉(ハイデガー的な意味での)がいるわけである。人間は必然性と内的自律性の齟齬という二律背反を主観の構造として持っており、しかしその齟齬こそが人間の「自由」の源泉であり、潜勢力としてのデュナミスでもあるのだ。「神」はその存在が必然性それ自体のため、齟齬や二律背反を持たないので、人間のようなデュナミス・潜勢力としての可能性や「自由」を持たない。即ち意志や欲望を持たないのだ。しかし人間はこの二律背反を認識論的に内在させているため、「自由」と意志という自律的な〈力学〉を有している。
近代とはまさしくこの人間の認識や主観、「心理」に内在するデュナミスとしての人間の潜勢力や可能性、欲望や「自由」が問題化されるわけである。形而上学の二律背反は、主体の二律背反となり、それは人間のデュナミスや「自由」、欲望を思惟する問題となっていく。そしてこの主観や「心理」における二律背反こそが、「自然科学」と「精神科学」と対応するのだ。つまり、「自然科学」という人間が逃れられない法則を研究する科学と、「精神科学」という理性の内的自律性と対応するような科学とに分かれるのである。実は「精神科学序説Ⅰ」は、この近代に入ったところで終了し、恐らく「Ⅱ」から近代の主観や「心理」の内的自律性の問題が論じられるのだろう。「自然科学」と「精神科学」は確かに内在させる法則や自律性は違うものであるが、カントを見ればわかるように、自然法則と理性のような主観の内的自律性は何らかの形で連関している。ディルタイは、「自然科学」と「精神科学」は別であり、「精神科学」の独立性を論じていくわけではあるが、それは「自然科学」の法則性と全く無関係ではない。やはりそこには「自然科学」と「精神科学」の弁証法的な関係が成り立つわけだ。即ち相互浸透して重なり合う法則の「連関」があるわけだ。
また、ディルタイは主観や「心理」を無数の目的の「連関」によって構造化されていると見るのであるが、それはつねに歴史的なものである。そこには「自然科学」とは違った歴史学の法則が見出される。そういう意味では「精神科学」は歴史的な目的「連関」だといえる。そのため、主観や「心理」が認識する対象と「適合」することが認識とはしない。主観や「心理」も歴史的に法則化されているのであり、その認識が人間の「生」の構造を創り出しているのであり、世界の「連関」をなしているということである。
近代の認識論における主観と「心理」の問題は、「Ⅱ」を読まなければわからないわけだが、ここまで読んでみて、ハイデガーの存在論とのつながりなども見えてきた。ディルタイのいう認識を可能にする主観や「心理」という「生」を構成する「連関」は、その「連関」自体が歴史的な目的「連関」によって歴史的に構造化されており、これは時間的存在としての、それは歴史的な存在としてのハイデガーの「現存在」の思考に繋がっていくのであろう。ディルタイを腰を据えて読んでみると、ハイデガーから現代思想に至るまでの道筋がよく見られるようになる。
『失われた時を求めて』は電車の中で読んでいるが、まだ3巻の半分くらいまでしか進んでいない。登場人物が入り組みすぎて、整理できない。
さて、ディルタイ「精神科学序説Ⅰ」(『ディルタイ全集』第1巻所収)をやっと読了した。ただ全集には「精神科学序説」の「草稿」も収録されており、理解を助けるためにも、これも読んでしまおうと思う。そのため「精神科学序説Ⅱ」は第2巻に所収されているが、これを読むのはもう少し先になりそうだ。「精神科学序説Ⅰ」の後半は哲学の歴史であり、同時に歴史哲学にもなっているような内容である。ディルタイはギリシャ哲学から中世哲学までの哲学史を概括しながら、形而上学がいかにして近代において、「精神科学」と「自然科学」へと分かれていくのかを論じている。まずディルタイは形而上学を特徴づけるのであるが、そこではアリストテレスの『形而上学』に現れる「不動の動者」という二律背反に注目するとわかりやすい。この形而上学に貫かれている問題意識は、有限と無限の問題であり、永遠と生成、運動と静止を二律背反のまま、この世界を構成している根源として理解するというものだ。即ちこの世界には運動があり、生成があり消滅があり、それは有限の時間の内に生起するのであるが、この有限の時間内の生成変化や運動を可能にしている、無時間的で恒常的な根源が存在しているはずだということである。つまり、変化を可能にしている変化しない根源、「不動の動者」という二律背反を思考する法則を発見することこそが、形而上学の使命ということになるだろう。
これはキリスト教の「神」にも引き継がれる問題である。単純化していえば、「神」は必然によって世界を創造しているはずであるが、被造物は偶然性や不完全性、あるいは悪を内包している。「神」がこの世界の必然性そのものだとしたら、何故世界に偶然性が存在するのか。この「神」と被造物の間の神学における二律背反の問題は、形而上学が思考してきた「不動の動者」の二律背反を引き継いでいる。この二律背反を解決するために汎神論や「神」からの「流出」の問題などが提起されることになる。ここで横道にそれるが、僕は学生時代一般教養の講義でアンセルムスの『プロスロギオン』の講義を受けて、所謂アンセルムスの神の存在証明に感銘を受けたことがある。確か、その講義のレポートは、アンセルムスの神の存在証明を批判し、論理的に何が誤謬であるのかを論じなさい、というもので、まさしく『プロスロギオン』の存在証明は、この二律背反の問題を含んでおり、何の哲学的訓練も受けていない学生であったが、そのレポートを書くのに妙なやりがいを感じた。そして、思考するとはこういうことを言うのか、という〈大学的〉(?)な興奮を覚えた、と記憶している。偶然履修した5人ほどしか聴講していない、後期の5限目で薄暗い教室での講義であったが、今でも鮮明に記憶している。
さて、そのような「神」と世界の二律背反の問題は古代と中世の形而上学の二律背反として現れているが、近代になるとそれは「主観」や「心」の問題になる。デカルトのcogitoの問題となり、カントで言うならば主観における悟性と感性の二律背反的構造を、構想力や理性が代補するという問題である。人間は自然科学的、力学的には法則の必然性に従属させられているが、しかし、理性という自律的な内なる道徳律によってそれと対峙している。これが法則に従属させられている「物」と「動物」と、理性の自律性を有する人間を差異化するわけだ。そして、この二律背反を橋渡しするのは、「自由」になるわけだが、それ故「自由」はこの二律背反が人間の主観に構造的に内在していなければ存在しないわけである。この自然科学的、力学的な法則に従属する、〈物体〉や〈動物〉としての人間と、それに理性によって対峙し、そこで裂け目としての〈深淵=自由〉に晒される、まあ〈現存在〉(ハイデガー的な意味での)がいるわけである。人間は必然性と内的自律性の齟齬という二律背反を主観の構造として持っており、しかしその齟齬こそが人間の「自由」の源泉であり、潜勢力としてのデュナミスでもあるのだ。「神」はその存在が必然性それ自体のため、齟齬や二律背反を持たないので、人間のようなデュナミス・潜勢力としての可能性や「自由」を持たない。即ち意志や欲望を持たないのだ。しかし人間はこの二律背反を認識論的に内在させているため、「自由」と意志という自律的な〈力学〉を有している。
近代とはまさしくこの人間の認識や主観、「心理」に内在するデュナミスとしての人間の潜勢力や可能性、欲望や「自由」が問題化されるわけである。形而上学の二律背反は、主体の二律背反となり、それは人間のデュナミスや「自由」、欲望を思惟する問題となっていく。そしてこの主観や「心理」における二律背反こそが、「自然科学」と「精神科学」と対応するのだ。つまり、「自然科学」という人間が逃れられない法則を研究する科学と、「精神科学」という理性の内的自律性と対応するような科学とに分かれるのである。実は「精神科学序説Ⅰ」は、この近代に入ったところで終了し、恐らく「Ⅱ」から近代の主観や「心理」の内的自律性の問題が論じられるのだろう。「自然科学」と「精神科学」は確かに内在させる法則や自律性は違うものであるが、カントを見ればわかるように、自然法則と理性のような主観の内的自律性は何らかの形で連関している。ディルタイは、「自然科学」と「精神科学」は別であり、「精神科学」の独立性を論じていくわけではあるが、それは「自然科学」の法則性と全く無関係ではない。やはりそこには「自然科学」と「精神科学」の弁証法的な関係が成り立つわけだ。即ち相互浸透して重なり合う法則の「連関」があるわけだ。
また、ディルタイは主観や「心理」を無数の目的の「連関」によって構造化されていると見るのであるが、それはつねに歴史的なものである。そこには「自然科学」とは違った歴史学の法則が見出される。そういう意味では「精神科学」は歴史的な目的「連関」だといえる。そのため、主観や「心理」が認識する対象と「適合」することが認識とはしない。主観や「心理」も歴史的に法則化されているのであり、その認識が人間の「生」の構造を創り出しているのであり、世界の「連関」をなしているということである。
近代の認識論における主観と「心理」の問題は、「Ⅱ」を読まなければわからないわけだが、ここまで読んでみて、ハイデガーの存在論とのつながりなども見えてきた。ディルタイのいう認識を可能にする主観や「心理」という「生」を構成する「連関」は、その「連関」自体が歴史的な目的「連関」によって歴史的に構造化されており、これは時間的存在としての、それは歴史的な存在としてのハイデガーの「現存在」の思考に繋がっていくのであろう。ディルタイを腰を据えて読んでみると、ハイデガーから現代思想に至るまでの道筋がよく見られるようになる。
『失われた時を求めて』は電車の中で読んでいるが、まだ3巻の半分くらいまでしか進んでいない。登場人物が入り組みすぎて、整理できない。













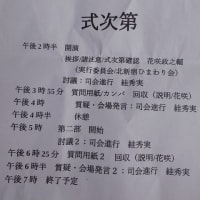






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます