『文学的絶対』(法政大学出版局)を読了した。そして本書を読む中で、ベンヤミンの『ドイツ・ロマン主義における芸術批評の概念』(ちくま学芸文庫)のロマン主義分析がいかに後世のロマン主義研究に影響力があり、またベンヤミンがその核心を分析していたのかもよくわかった。ナンシーの「無為の共同体」における「無為」がロマン主義に由来するものであるのも見当が付いた気がする。確か、ナンシーはラクー=ラバルトと一緒に『ナチ神話』(松籟社)を出していたと思うが、この分析もロマン主義分析と関わるものだと思う。また、ロマン主義者がdichtenの作用を「創作する」や「文学的な制作」だけではなく、「でっちあげる」という意味でも使っているが、このポイエーシスの作用は「文学的絶対」の作用でもあるが、前にも書いたように、これはフィクション論としてのファイヒンガーの『かのように(als ob)の哲学』とも重なるものだといえる。ファイヒンガーは「歴史」と「神話」を区別しようとするが、その区別を脱構築してしまうals ob の dichten の働きに注目していた。「歴史」は実証的であり、「神話」は創作的であるという、通俗的な区分はあるものの、「歴史」にも「神話」にも dichten としての「でっちあげ」の力は働いており、「歴史」と「神話」は als ob の地点で不分明となる。「歴史」を実証的に constative なレベルで認識するのではなく、「神話」に働いているような dichten の作用が、「歴史」をも performative に形作っている。この performative な力こそが、 dichten という「創作」でありながら「でっちあげ」でもあり、しかし、schaffen でもあり erfinden でもあるような「発明」の地平を開いている。ファイヒンガーはこの「発明」の力を als ob と呼んでいた。ファイヒンガーはこれをカントとニーチェの関係から分析していたはずで、このファイヒンガーの発想は、ロマン主義の「文学的絶対」の力を継承して形作ったフィクションの理論だったのだということが、改めて確認することができた。ロマン主義が「神話」を求めていたのはここに、 dichten としての「絶対」の力があったからだろう。
そしてこの『文学的絶対』を読む中で、日本近代文学における絓秀実のロマン主義分析(批判)も、この本が翻訳される前に、かなり似た議論をしていたということも確認できた。絓は『日本近代文学の〈誕生〉』(太田出版)の中で、近代文学を「俗語」と「雑」という概念で分析するが、これはロマン主義の「断片性」とその「散文性」に相当する。絓は日本近代文学における「現前性」という「透明性」が、逆説的に「雑」によってなされるとするが、これこそがロマン主義の「イロニー」が存在して初めて成立する構造であり、この中心には dichten としての構想力の問題があるわけだ。もちろん絓は本書が翻訳されなくとも、ヘーゲルやデリダ、ベンヤミンの著作などを通してこの結論を導き出していたと思うのだが、この本が翻訳されたことで、その同時代性を確認することができてよかった。そういう意味で日本の文芸批評も、ナンシーやラクー=ラバルトたちと同じような時期に「文学的絶対」と対峙していたわけである。特にこれは1930年代の「日本浪曼派」の分析などにも有効だろう。
ともかくも『文学的絶対』を読むうちに、分析の対象となっているロマン主義のテクストを読んでみたいと強く思わせられた。古本屋で買ったが、長い間読み止しになっているノヴァーリスの『花粉』とかもきちんと読もうか、と思う。またこれはまだ何の確証もない考えではあるが、「批評(性)」とはこの「断片」と「雑」それ自体のことだとするならば、今ちまちま読んでいる『失われた時を求めて』のテクストというのはものすごい「雑」であり、社交界なんて「雑」そのものであり、その意味で、プルーストはまさしく「批評」を書いたのだな、と思うようになった。ロマン主義をきちんと考えるきっかけとなった大著であった。
そしてこの『文学的絶対』を読む中で、日本近代文学における絓秀実のロマン主義分析(批判)も、この本が翻訳される前に、かなり似た議論をしていたということも確認できた。絓は『日本近代文学の〈誕生〉』(太田出版)の中で、近代文学を「俗語」と「雑」という概念で分析するが、これはロマン主義の「断片性」とその「散文性」に相当する。絓は日本近代文学における「現前性」という「透明性」が、逆説的に「雑」によってなされるとするが、これこそがロマン主義の「イロニー」が存在して初めて成立する構造であり、この中心には dichten としての構想力の問題があるわけだ。もちろん絓は本書が翻訳されなくとも、ヘーゲルやデリダ、ベンヤミンの著作などを通してこの結論を導き出していたと思うのだが、この本が翻訳されたことで、その同時代性を確認することができてよかった。そういう意味で日本の文芸批評も、ナンシーやラクー=ラバルトたちと同じような時期に「文学的絶対」と対峙していたわけである。特にこれは1930年代の「日本浪曼派」の分析などにも有効だろう。
ともかくも『文学的絶対』を読むうちに、分析の対象となっているロマン主義のテクストを読んでみたいと強く思わせられた。古本屋で買ったが、長い間読み止しになっているノヴァーリスの『花粉』とかもきちんと読もうか、と思う。またこれはまだ何の確証もない考えではあるが、「批評(性)」とはこの「断片」と「雑」それ自体のことだとするならば、今ちまちま読んでいる『失われた時を求めて』のテクストというのはものすごい「雑」であり、社交界なんて「雑」そのものであり、その意味で、プルーストはまさしく「批評」を書いたのだな、と思うようになった。ロマン主義をきちんと考えるきっかけとなった大著であった。











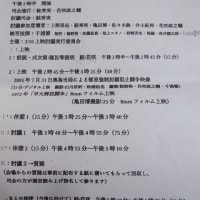








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます