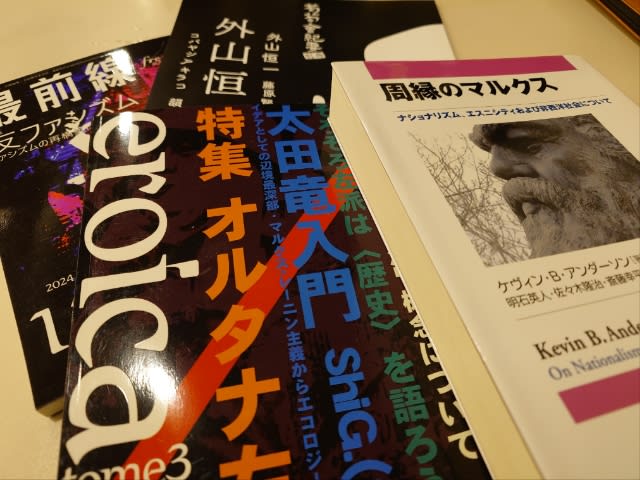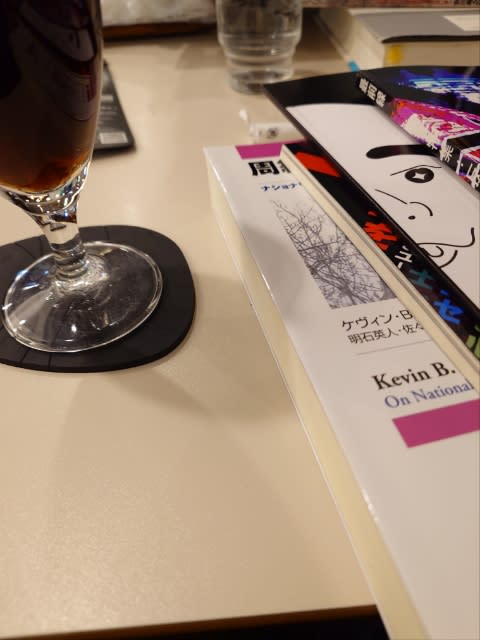台風一過、過ぎた直後の夕方は本当に「涼しい」という時間帯があり、秋らしいというのは、虫の声でもわかる。しかし、まだまだ暑い。しばらく日記を書いてなかったので、お盆の帰省のことを少し書いてみたい。前回も書いたように、自宅で人工透析をしている親族が盆に腹膜炎になり、その入院手続きをしたが、透析患者は障害者手帳や給付の書類などが多く、入院手続きでは、それらの書類をそろえて出さなくてはならない。そして最後の関門として、マイナンバー付きの保険証が登場する。窓口からマイナンバーカード付きが必要だが、ナンバーは見せるなとか見せろとか、今思い出せないことを言われ、少し逡巡していると、窓口の人が察したように、これまでの紙の証書があったらそれで大丈夫ですといわれ、事なきを得た。僕自身はフリーランスではないので、今のところマイナンバーカードは作っていなくとも不自由していない。時折聞いたりネットの記事でも見るが、マイナンバーのシステムがきちんとしていないため、いらない手間がかかる。こういう一歩間違えると命に関わったり、医療費が高額な場合は不安感が大きい。かつて、人工透析の患者は社会保障費を無駄遣いしている、だからお国のために「察しろ」のような、優生思想に相当することを発言したアナウンサーがいたが、人工透析を親族が受けている身とすれば、自宅で透析ができる環境が揃えられるのは、医療・福祉の環境としては非常に助かっている。ある時スポーツ新聞系のネットニュースで、腹膜透析をしている患者が出す家庭用の排水が、下水管を痛めている、というような、暗に透析を非難する論調の文章を載せていた。これは、高齢者の交通事故を大々的に扱うメディアの手法と同じで、高齢者をコストカットする世論を盛り上げるキャンペーンだと思う。本当にろくでもないな、と親族に高齢者が増えてくると、敵意すら感じることが多くなる。高齢者を大事にしない社会は、必然的に子供や若者も大事にしない社会だと思っている。実際この三十年で、コストカットのリストラは、中高年のコストカットだけではなく、若者のコストカットでもあったことで分るだろう。若者のために高齢者をコストカットするというのは、安直に考えるとそれっぽく考えられるように思うが、実際は同じように弱いところを切り捨てる、ということにしかならない。例えば僕の頃より、子供への公教育の環境は貧弱になっているのではないか?
教育で思い出したが、僕には小学生の甥がいて、義妹とその甥の「教育」について話した。甥は、田舎に育ちながらも、その両親はかなり手厚く教育をしており、習い事や塾、運動までお金をかけている。つまりお金を掛けられる環境ではある。忙しそうな甥を見ると、僕自身はそろばんとフィリピン戦線の生き残りの老人から数学と英語を教わった以外はほとんど何もしておらず、甥も忙しそうで大変だな、という思いがある。ただ、先ほども書いたように、教育できる環境なのは、良いのかもしれない。その義妹が「お兄さん、今の教育は「課金」と同じです」という話をし始めたのだった。どういうことかというと、小学校の体育の「水泳」のことである。僕は小学校入学したころは「かなづち」で、いつも泳げる人とは別のコースで「特訓」を受けていた。そもそも僕は水に顔をつけるのさえ苦手で、泳ぐことなど絶対にできなかった。当時の小学校の教員はかなり厳しく、そういうわけでプールの時間が本当に嫌だった。その「特訓」の効果もあるのだろうか、5人くらいの僕の「仲間」も、徐々に減っていく。最終的には僕一人が泳げないし、顔も水に付けられない状態のままで、取り残されてしまった。そのような苦い思い出を思い浮かべながら、甥のプールの時間の話を聞くと、「今の小学校のクラスは、30人中半分くらいが泳げませんよ」という話であった。僕は小学生時代の泳げない最後の一人になったことを思い出しながら、驚いて「半分も!?」という反応になった。今の学校は泳げないのを無理やり泳がせないので、泳げない人は泳げないままなのだという(「泳げない」にもグラデーションはあろう)。そしてその時義妹が言ったのは「そこでお兄さん、課金ですよ」という言葉だった。要は、学校に任せていても泳げない人は泳げない。だから「課金」する事でスイミングスクールに通わせられる子は、泳げるようになり、事情は様々だが「課金」をしなかった子供は泳げないままだというのだ。要はゲームで「課金」をして「無双」するか、無課金で何とかするかの状態が、小学校の公教育でもあるのだという。しかも「課金」という言葉が義妹から自然に出るのだ。それはゲームの「課金」と形式的には同じなのだと思う。泳げない子や、様々な事情で困難な子を、規律訓練することで泳げるようにするというのは、「暴力」であり、「ハラスメント」と今だといわれるし、それは泳げず、プールに顔をさえ付けられなかった「当事者」として、あの夏の憂鬱を、今の教育は「配慮」し「ケア」するというのは、それなりの理があるとは、僕も判断する。そういう配慮は必要だろう。しかし、「課金」しなければ泳げないが、「課金」すれば泳げるというのは、かつての「暴力」や「ハラスメント」を内在させた規律訓練より、暴力的ではないのだろうか。公教育のそれは「配慮」や「ケア」と同時に、みんなを同じ能力にする規律訓練自体のコストカットとしても機能してしまっているのではないか。学校は何も規律訓練しないのだから、「課金」で規律訓練を外部委託するのである。これは公教育のコストカットそのものだろう。勿論、相対的に「当事者」に対する「配慮」や「ケア」になり得るのは、全員が泳げなくとも大丈夫な社会を作ることである。しかし、現状は公教育の新自由主義的な「配慮」と「ケア」を隠れ蓑としたコストカットにしか見えない。泳げない僕を叱りながら特訓させる暴力と「課金」の暴力はどちらが「まし」なのか。
自戒も込めて言うと、教師が信頼されないのは「課金」を遠回しに推奨するような教育改革を容認しているくせに、生徒や学生の味方をしているふりをしているところだろう。最近ネット上で学費値上げの反対について、学生が大学に抗議しようとしたら、ある教員から大学に抗議しても無駄だ、文科省に言うべきだというふうにいわれて、学生が「たらいまわし」にされるといって憤っている場面が目に止まった。学生が怒るのも無理ない。教員がやっていることは「矛先」が自分に向かないように誘導しているとしか見えないからである。確かに、大学の構造上の問題は、文科省や行政の問題だと、僕も言いたくなるし、実際そういう部分は多くある。しかし、大学の運営や学費の値上げ自体に関しては、教員は経営側にいる。これは数年前のブログにも書いたが、学費値上げ阻止で学生と教員が共闘するというのは、少なくとも現代の大学を見る上で僕にはリアリティがない(ただ、値上げ反対を理解はしている)。むしろ、学費を下げろという学生の抗議に関しては、僕は教員と利益が相反すると思うからだ。そういう意味では、学生の抗議は教員にとって恐怖の対象となっているはずである。その意味で教員が共感する学費値下げ運動は駄目だろう。この利益の相反を誤魔化してしまうから、抗議は文科省へ、ということになるのだろう。抗議の本丸が教員(と教員が理想としている大学)でないことを示すためである。やはり給料は下げられたくない。勿論、現在のガバナンス改革ばかりしている大学経営が悪いのであって、大学は行政に物申すべきというのも、その通りである。それならば、労働運動として教職員は大学の民主化などで動くべきではないかと思う。一般企業もそうだが、大学の組合の組織率はひどい状態である。まずはそういう場面を教員もきちんと作って抗議を常態化すべきだろう。学生に世話を焼いている場合ではない。
そんな甥の夏のキャンプに保護者という体で付き添った。これはとある「団」が主催しているキャンプだ。地元のキャンプ場の川で泳いだのだが、救命胴衣には「日本財団」のロゴがしっかりと入っていた。これも一種の「課金」といえるのかもしれない。

虻に刺されながら、実家ではこの前書いた萬屋錦之介『柳生新陰流』だけではなく、同じく錦之介の『破れ奉行』を見た。これは錦之介が「深川奉行」という架空の奉行となって、深川という「番外地」を守るという話で、劇の終盤で悪を成敗するのに、何故か毎回高速の捕鯨船に乗って対決の場所まで行き、銛で敵と闘うという、メルヴィル『白鯨』を彷彿とさせるものであった。また、田中邦衛版『岡っ引どぶ』は、田中扮する「どぶ」が、京都御所に忍び込んで「仁孝帝」と一緒に碁を打つというもので、天子様には護衛がいないんだ、という「どぶ」の言葉のうちに、尊皇にも大逆にも振れかねない可能性を垣間見ながら、僕は遠い関東の空の下を思い浮かべるのであった。
教育で思い出したが、僕には小学生の甥がいて、義妹とその甥の「教育」について話した。甥は、田舎に育ちながらも、その両親はかなり手厚く教育をしており、習い事や塾、運動までお金をかけている。つまりお金を掛けられる環境ではある。忙しそうな甥を見ると、僕自身はそろばんとフィリピン戦線の生き残りの老人から数学と英語を教わった以外はほとんど何もしておらず、甥も忙しそうで大変だな、という思いがある。ただ、先ほども書いたように、教育できる環境なのは、良いのかもしれない。その義妹が「お兄さん、今の教育は「課金」と同じです」という話をし始めたのだった。どういうことかというと、小学校の体育の「水泳」のことである。僕は小学校入学したころは「かなづち」で、いつも泳げる人とは別のコースで「特訓」を受けていた。そもそも僕は水に顔をつけるのさえ苦手で、泳ぐことなど絶対にできなかった。当時の小学校の教員はかなり厳しく、そういうわけでプールの時間が本当に嫌だった。その「特訓」の効果もあるのだろうか、5人くらいの僕の「仲間」も、徐々に減っていく。最終的には僕一人が泳げないし、顔も水に付けられない状態のままで、取り残されてしまった。そのような苦い思い出を思い浮かべながら、甥のプールの時間の話を聞くと、「今の小学校のクラスは、30人中半分くらいが泳げませんよ」という話であった。僕は小学生時代の泳げない最後の一人になったことを思い出しながら、驚いて「半分も!?」という反応になった。今の学校は泳げないのを無理やり泳がせないので、泳げない人は泳げないままなのだという(「泳げない」にもグラデーションはあろう)。そしてその時義妹が言ったのは「そこでお兄さん、課金ですよ」という言葉だった。要は、学校に任せていても泳げない人は泳げない。だから「課金」する事でスイミングスクールに通わせられる子は、泳げるようになり、事情は様々だが「課金」をしなかった子供は泳げないままだというのだ。要はゲームで「課金」をして「無双」するか、無課金で何とかするかの状態が、小学校の公教育でもあるのだという。しかも「課金」という言葉が義妹から自然に出るのだ。それはゲームの「課金」と形式的には同じなのだと思う。泳げない子や、様々な事情で困難な子を、規律訓練することで泳げるようにするというのは、「暴力」であり、「ハラスメント」と今だといわれるし、それは泳げず、プールに顔をさえ付けられなかった「当事者」として、あの夏の憂鬱を、今の教育は「配慮」し「ケア」するというのは、それなりの理があるとは、僕も判断する。そういう配慮は必要だろう。しかし、「課金」しなければ泳げないが、「課金」すれば泳げるというのは、かつての「暴力」や「ハラスメント」を内在させた規律訓練より、暴力的ではないのだろうか。公教育のそれは「配慮」や「ケア」と同時に、みんなを同じ能力にする規律訓練自体のコストカットとしても機能してしまっているのではないか。学校は何も規律訓練しないのだから、「課金」で規律訓練を外部委託するのである。これは公教育のコストカットそのものだろう。勿論、相対的に「当事者」に対する「配慮」や「ケア」になり得るのは、全員が泳げなくとも大丈夫な社会を作ることである。しかし、現状は公教育の新自由主義的な「配慮」と「ケア」を隠れ蓑としたコストカットにしか見えない。泳げない僕を叱りながら特訓させる暴力と「課金」の暴力はどちらが「まし」なのか。
自戒も込めて言うと、教師が信頼されないのは「課金」を遠回しに推奨するような教育改革を容認しているくせに、生徒や学生の味方をしているふりをしているところだろう。最近ネット上で学費値上げの反対について、学生が大学に抗議しようとしたら、ある教員から大学に抗議しても無駄だ、文科省に言うべきだというふうにいわれて、学生が「たらいまわし」にされるといって憤っている場面が目に止まった。学生が怒るのも無理ない。教員がやっていることは「矛先」が自分に向かないように誘導しているとしか見えないからである。確かに、大学の構造上の問題は、文科省や行政の問題だと、僕も言いたくなるし、実際そういう部分は多くある。しかし、大学の運営や学費の値上げ自体に関しては、教員は経営側にいる。これは数年前のブログにも書いたが、学費値上げ阻止で学生と教員が共闘するというのは、少なくとも現代の大学を見る上で僕にはリアリティがない(ただ、値上げ反対を理解はしている)。むしろ、学費を下げろという学生の抗議に関しては、僕は教員と利益が相反すると思うからだ。そういう意味では、学生の抗議は教員にとって恐怖の対象となっているはずである。その意味で教員が共感する学費値下げ運動は駄目だろう。この利益の相反を誤魔化してしまうから、抗議は文科省へ、ということになるのだろう。抗議の本丸が教員(と教員が理想としている大学)でないことを示すためである。やはり給料は下げられたくない。勿論、現在のガバナンス改革ばかりしている大学経営が悪いのであって、大学は行政に物申すべきというのも、その通りである。それならば、労働運動として教職員は大学の民主化などで動くべきではないかと思う。一般企業もそうだが、大学の組合の組織率はひどい状態である。まずはそういう場面を教員もきちんと作って抗議を常態化すべきだろう。学生に世話を焼いている場合ではない。
そんな甥の夏のキャンプに保護者という体で付き添った。これはとある「団」が主催しているキャンプだ。地元のキャンプ場の川で泳いだのだが、救命胴衣には「日本財団」のロゴがしっかりと入っていた。これも一種の「課金」といえるのかもしれない。

虻に刺されながら、実家ではこの前書いた萬屋錦之介『柳生新陰流』だけではなく、同じく錦之介の『破れ奉行』を見た。これは錦之介が「深川奉行」という架空の奉行となって、深川という「番外地」を守るという話で、劇の終盤で悪を成敗するのに、何故か毎回高速の捕鯨船に乗って対決の場所まで行き、銛で敵と闘うという、メルヴィル『白鯨』を彷彿とさせるものであった。また、田中邦衛版『岡っ引どぶ』は、田中扮する「どぶ」が、京都御所に忍び込んで「仁孝帝」と一緒に碁を打つというもので、天子様には護衛がいないんだ、という「どぶ」の言葉のうちに、尊皇にも大逆にも振れかねない可能性を垣間見ながら、僕は遠い関東の空の下を思い浮かべるのであった。