映画『ゲバルトの杜』(代島治彦監督)はまだ見ていないが、『映画芸術』の絓秀実+亀田博+花咲政之輔による「映画批判」の座談会は読み、そしてこの映画の原作?となっている樋田毅『彼は早稲田で死んだ 大学構内リンチ殺人事件の永遠』(文芸春秋)は発売当初に読んでおり、ツイッターでは、何故か以前から「『ゲバルトの杜 ~彼は早稲田で死んだ~』公式」にフォローされて、不思議に思っていたが、ツイッターで花咲さんさんにフォローされているからかもしれない。ともかくも、映画は観ていないが、『映画芸術』の座談会を読み、そして樋田の本を読んだ時の感想は、その座談会が「批判」していたことと重なる部分があった。映画は近々見ておきたい。
まだ映画は観ておらず、座談会と、原作?の樋田の著書を読んでの感想とはなるが、僕も一番違和感を覚えたのは、座談会の批判の一つの的となっている、映画と樋田の著書にある早稲田大学の「奥島総長」への「評価」だろう。僕自身は「奥島総長」が任期のど真ん中に学生であり、「革マル」の排除と大学の「浄化」、そして早稲田祭の中止を経験していた。僕の記憶では(記憶違いの可能性はある)、それまで大学は24時間、一日中出入り自由だったが、僕の入学前にどうやら、22時が閉門の時間になったようで、それへの学生の不満がくすぶる形で伝わっていたように思う。その頃、学生会館の革マルによる支配の排除が大学から宣言されており、早朝に大学に行くと、公安や機動隊が来ていて、学生会館に突入というのが何度もあった。マスクとサングラスで顔を覆い、帽子をかぶった公安が写真機片手に正門で写真を撮りまくっていたのは、「日常」といっても差し支えなかったと思う。
それはともかく、大学に入ったばかりの僕は、教室中がビラで埋め尽くされ、講義開始前は必ず革マルの活動家が演説し、時には「当局」側の教員とつかみ合いの喧嘩になっているのは、これも「日常」であったが、怖いとかそういう違和感は持たなかった。大学というのはそういう所なのだろう、と漠然と思っていた。ただ、教室内にビラが散乱し、壁にはビラが重ね張りしてあるのが普通の環境だと、ビラを自分で作って撒くということに、全く抵抗感がなかったのは、良かったのかもしれない。僕自身は政治的にも学問的にも鋭敏な存在ではなかったが、革マルと大学の対立の中にいると、自然と政治的な話題が多くなり、その革マルと大学の対立問題について話の合う友人と、今思うと稚拙な自己主張の枠を出ないビラを作って、何度か撒いていた。政治的にも学問的にも鋭敏ではなかったが、ビラが教室中に撒き散らしてあって、壁にも張りまくられていると、ビラでも撒いてみるか、という気持ちには自然になって、僕と友人はビラを作って、革マルのビラ配りと鉢合わせになると厄介かもしれないと思って、校門が開くと一目散に校舎に入って、講義が始まる前の教室の机の上に無造作に置いていった。ビラの内容は原稿が残してあるが、「好意的に見れば」、資本主義批判にはなっていた、とは思う。
友人とそのような何の目的かわからない内容のビラを作り、何度かビラまきをしていたある日、 警備員に止められて、「君たちの気持ちはわかるが、これからは撒けなくなるよ」と言われ、恐らく革マルに間違われたのかもしれないが、まだその時点では強い制止ではなかったが、ビラが撒けなくなりつつあるのを感じる状況が成立し始めたのである。それが「奥島総長」の革マル排除に伴う、大学の「浄化」であったのだ。勿論、大学というものは常に「浄化」されてきたものであるので、奥島以前が自由であったとは思わないが、ビラすら撒けなくなる大学の端緒は、このくらいの頃にあったのだろうと思う。友人と僕もその制止以来、気持ちが萎えたのか撒かなくなったと記憶する。それからビラの数が減り、構内のタテカンが減っていったように思う。しかし、それに対して僕らとは違って長く抵抗していた人たちは、勿論存在した。
そのビラまきを一緒にした友人は、その後も大学当局による早稲田祭中止に抗議して活動をしていた。僕は直接それには関わっていなかったが、その友人とは議論をしていて、友人の立場が「つらい状態」になっていたことを知った。これは入学以来複数の教員が言っていたことだが、「革マルと大学当局」は裏では結託しており、大学の治安維持を共に図っていた、というのは公然の秘密だった。それは「当局」側の教員も発言していた。そしてその頃いわゆる68年世代の人に聞いても、当然の事実だということになっており、では何のために革マルを排除するのか学生の頃はよくわからなくなったが、その「排除」に「戦略」があったことは、大学における生権力や生政治の問題を考えれば理解でき、それは座談会でも語られているし、『ネオリベ化する公共圏』(明石書店)を見てもわかる。つまり友人は大学祭の継続と学生の自治による学祭の成立を主張したため、大学側からも恨まれ、そして革マル側からも追われるようになっていたのだった。要は大学は大学の自治というよりは、学祭を大学によってコントロールし、新自由主義的広報活動としてプロモートするつもりで、大学の学生による自治などは考えておらず、友人はそこで大学側とも対立し、革マル側から見れば、「味方」になるならばいいが、所謂革マルとは違う学生自治を唱える友人は、取り込むか排除するかのどちらかで対処しようとされていたのだろう。そして、大学による早稲田祭の中止は、早稲田祭からの革マルの排除(当時学祭は「パンフレットを購入する」という事実上の入場料制で、それが政治資金になっていた)ということになっていたが、所謂一般学生にとっても「ショック・ドクトリン」になっており、大学による「学生自治」(それが幻想であっても)の破壊と、その後の「更地」を新自由主義化するきっかけとなったのだといえる。
友人とは学祭について議論はしていたが、徐々に会う機会が減り、友人は学生自治による学祭復活の立場として大学当局からも敵視され、革マルからも追われ、検証できるという意味での事実かどうかはともかく、電話の「盗聴」を疑っており、僕との電話も警戒していたのを覚えている。友人は次第に大学に来なくなり、最後に会ったのは、議論後に友人が大学はやめたといって去って行った時であった。その後学祭は「大学の学祭」となり広報活動の一環になったのではないかと思う。「奥島総長」はこのような僕のような、政治的にも学問的にも鋭敏でなかった個人的な学生生活の中でも、「ショック・ドクトリン」と新自由主義的大学経営と管理コントロールの生権力と結びつく。だから「奥島総長」による大学からの革マルの排除を樋田の本のように喜べないし、友人が学祭に関しては当局と革マルの「共闘」によって苦しんだのを見ると、絓秀実のいう大学の生政治と革マルの生政治が重なり合って大学を支配し続けているという主張の方が、リアリティがあるわけである。とにかく『ゲバルトの杜』を見て見ないことには。
さて、読書記録をしておこう。『失われた時を求めて』は第6巻に突入。「ソドムとゴモラ」である。デリダの『ジャック・デリダ講義録 時を与えるⅡ』(藤本一勇訳、白水社)と『フィヒテ全集4』(隈元忠敬+阿部典子+藤沢賢一郎訳、晢書房 )の「初期知識学」を読んでいる。特にフィヒテ、これがヘーゲルの精神現象学の、ある意味での元ネタか、と思って読んでいる。
まだ映画は観ておらず、座談会と、原作?の樋田の著書を読んでの感想とはなるが、僕も一番違和感を覚えたのは、座談会の批判の一つの的となっている、映画と樋田の著書にある早稲田大学の「奥島総長」への「評価」だろう。僕自身は「奥島総長」が任期のど真ん中に学生であり、「革マル」の排除と大学の「浄化」、そして早稲田祭の中止を経験していた。僕の記憶では(記憶違いの可能性はある)、それまで大学は24時間、一日中出入り自由だったが、僕の入学前にどうやら、22時が閉門の時間になったようで、それへの学生の不満がくすぶる形で伝わっていたように思う。その頃、学生会館の革マルによる支配の排除が大学から宣言されており、早朝に大学に行くと、公安や機動隊が来ていて、学生会館に突入というのが何度もあった。マスクとサングラスで顔を覆い、帽子をかぶった公安が写真機片手に正門で写真を撮りまくっていたのは、「日常」といっても差し支えなかったと思う。
それはともかく、大学に入ったばかりの僕は、教室中がビラで埋め尽くされ、講義開始前は必ず革マルの活動家が演説し、時には「当局」側の教員とつかみ合いの喧嘩になっているのは、これも「日常」であったが、怖いとかそういう違和感は持たなかった。大学というのはそういう所なのだろう、と漠然と思っていた。ただ、教室内にビラが散乱し、壁にはビラが重ね張りしてあるのが普通の環境だと、ビラを自分で作って撒くということに、全く抵抗感がなかったのは、良かったのかもしれない。僕自身は政治的にも学問的にも鋭敏な存在ではなかったが、革マルと大学の対立の中にいると、自然と政治的な話題が多くなり、その革マルと大学の対立問題について話の合う友人と、今思うと稚拙な自己主張の枠を出ないビラを作って、何度か撒いていた。政治的にも学問的にも鋭敏ではなかったが、ビラが教室中に撒き散らしてあって、壁にも張りまくられていると、ビラでも撒いてみるか、という気持ちには自然になって、僕と友人はビラを作って、革マルのビラ配りと鉢合わせになると厄介かもしれないと思って、校門が開くと一目散に校舎に入って、講義が始まる前の教室の机の上に無造作に置いていった。ビラの内容は原稿が残してあるが、「好意的に見れば」、資本主義批判にはなっていた、とは思う。
友人とそのような何の目的かわからない内容のビラを作り、何度かビラまきをしていたある日、 警備員に止められて、「君たちの気持ちはわかるが、これからは撒けなくなるよ」と言われ、恐らく革マルに間違われたのかもしれないが、まだその時点では強い制止ではなかったが、ビラが撒けなくなりつつあるのを感じる状況が成立し始めたのである。それが「奥島総長」の革マル排除に伴う、大学の「浄化」であったのだ。勿論、大学というものは常に「浄化」されてきたものであるので、奥島以前が自由であったとは思わないが、ビラすら撒けなくなる大学の端緒は、このくらいの頃にあったのだろうと思う。友人と僕もその制止以来、気持ちが萎えたのか撒かなくなったと記憶する。それからビラの数が減り、構内のタテカンが減っていったように思う。しかし、それに対して僕らとは違って長く抵抗していた人たちは、勿論存在した。
そのビラまきを一緒にした友人は、その後も大学当局による早稲田祭中止に抗議して活動をしていた。僕は直接それには関わっていなかったが、その友人とは議論をしていて、友人の立場が「つらい状態」になっていたことを知った。これは入学以来複数の教員が言っていたことだが、「革マルと大学当局」は裏では結託しており、大学の治安維持を共に図っていた、というのは公然の秘密だった。それは「当局」側の教員も発言していた。そしてその頃いわゆる68年世代の人に聞いても、当然の事実だということになっており、では何のために革マルを排除するのか学生の頃はよくわからなくなったが、その「排除」に「戦略」があったことは、大学における生権力や生政治の問題を考えれば理解でき、それは座談会でも語られているし、『ネオリベ化する公共圏』(明石書店)を見てもわかる。つまり友人は大学祭の継続と学生の自治による学祭の成立を主張したため、大学側からも恨まれ、そして革マル側からも追われるようになっていたのだった。要は大学は大学の自治というよりは、学祭を大学によってコントロールし、新自由主義的広報活動としてプロモートするつもりで、大学の学生による自治などは考えておらず、友人はそこで大学側とも対立し、革マル側から見れば、「味方」になるならばいいが、所謂革マルとは違う学生自治を唱える友人は、取り込むか排除するかのどちらかで対処しようとされていたのだろう。そして、大学による早稲田祭の中止は、早稲田祭からの革マルの排除(当時学祭は「パンフレットを購入する」という事実上の入場料制で、それが政治資金になっていた)ということになっていたが、所謂一般学生にとっても「ショック・ドクトリン」になっており、大学による「学生自治」(それが幻想であっても)の破壊と、その後の「更地」を新自由主義化するきっかけとなったのだといえる。
友人とは学祭について議論はしていたが、徐々に会う機会が減り、友人は学生自治による学祭復活の立場として大学当局からも敵視され、革マルからも追われ、検証できるという意味での事実かどうかはともかく、電話の「盗聴」を疑っており、僕との電話も警戒していたのを覚えている。友人は次第に大学に来なくなり、最後に会ったのは、議論後に友人が大学はやめたといって去って行った時であった。その後学祭は「大学の学祭」となり広報活動の一環になったのではないかと思う。「奥島総長」はこのような僕のような、政治的にも学問的にも鋭敏でなかった個人的な学生生活の中でも、「ショック・ドクトリン」と新自由主義的大学経営と管理コントロールの生権力と結びつく。だから「奥島総長」による大学からの革マルの排除を樋田の本のように喜べないし、友人が学祭に関しては当局と革マルの「共闘」によって苦しんだのを見ると、絓秀実のいう大学の生政治と革マルの生政治が重なり合って大学を支配し続けているという主張の方が、リアリティがあるわけである。とにかく『ゲバルトの杜』を見て見ないことには。
さて、読書記録をしておこう。『失われた時を求めて』は第6巻に突入。「ソドムとゴモラ」である。デリダの『ジャック・デリダ講義録 時を与えるⅡ』(藤本一勇訳、白水社)と『フィヒテ全集4』(隈元忠敬+阿部典子+藤沢賢一郎訳、晢書房 )の「初期知識学」を読んでいる。特にフィヒテ、これがヘーゲルの精神現象学の、ある意味での元ネタか、と思って読んでいる。














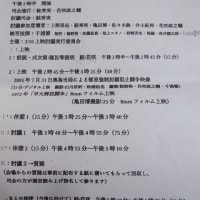





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます