第10次『早稲田文学』が休刊されたというニュースが流れた。その「経緯」は「公式」のURLで発表されている 。
主な休刊の理由は、「カリキュラム改革」によって『早稲田文学』を早稲田大学の学科コースのテキストとして使用しなくなった関係上、学費や税金を原資としている大学からの早稲田文学編集室への補助金が廃止されることによるようだ。「公式」の見解が出ているように、雑誌の内容や編集の問題ではなく、「カリキュラム改革」即ち「教育」の問題が大きいというのはその通りだろう。私自身熱心な『早稲田文学』の読者ではなかったが、ヌーボー・ロマン特集や大西巨人の記事、あるいは絓秀実の批評などが頻繁に掲載されていた時は、買いもしたし、図書館でもコピーした記憶がある。無料であった『WB』も何冊かは持っている。最近の『早稲田文学』も読んではいたが、内容として少なくとも文学部の学生に「教育」を目的として読ませても良いのではないかと思う。ただ、文芸誌が学科の「テキスト」や教科書となること自体が必ずしも良いとは思わないが。
最近思うのは、大学の資本が特に文化、学術の側面において、相対的に大きくなっていることだ。文化・学術出版業界は「不況」の中で大学の資本に頼るようになっている。勿論、出版資本の相対的自立性は高度成長期からバブルまでのかりそめのものだとは思うが、その自立性が弱まった結果、大学資本が前面に押し出されてくるようになった。最近「批評の衰退」がネットで議論されていたようだが、批評の相対的自立性も、その出版資本の自立性と軌を一にしていたわけなので、大学資本が前景化されてくる中で、出版における批評なるものが退いていってしまうのも当然なのかもしれない。大学資本による批評の包摂ということになるだろう。『早稲田文学』もこのような流れの中にあるのではないか。早稲田文学編集室は、大学から補助金を受けながらも、相対的に自立していたはずである。休刊をめぐる「公式」の発表の行間を読むと、その自立性を維持するための、編集発行に関わった教員や学生、それらを含んだ編集員の尽力や献身という名の低賃金労働があったのだと推測される。これらは雑誌の自立性と関わることだろう。大学に資金は出させるが口は出させない、というのを維持するためには、補助金を何とか必要最低限とする必要があるからだ。むしろ僕は大学は金は大いに出して口は一切出さないというのが、出版における言論の自由に資するやり方ではないかと思っている。大学とは本当はそういう役割なのではないのだろうか。
しかし、2022年4月に早稲田大学が「早稲田文学」を「商標登録」したとあるように、大学資本による出版の包摂が進んでいく。これは『早稲田文学』が担ってきた、創作と批評の蓄積が大学へ包摂されていく過程である。「カリキュラム改革」の結果、『早稲田文学』の「テキスト」としての役割を終えたというが、そもそもその「カリキュラム改革」とは何か?という問題がある。早稲田大学の文芸を扱うコースで、『早稲田文学』的な創作や批評性が必要でなくなる「教育」とは何なのだろうか。それにも拘らず大学は「早稲田文学」を自らのために商品化することには余念がないのだ。これは『早稲田文学』を大学のための文化的商品として作り変えることである。そのような大学による文芸誌の商品化の先に、言論の自由というのはあるのだろうか。そこでは大学の掲げる(資本主義が掲げる)コンプライアンスとリベラルな道徳主義的言論しか許容されないのではないかという懸念しかない。
大学自体は文部科学省によって補助金による統制を受け、常に企業のように利益を上げることを要求され、内部留保を蓄積するよう暗に指令されている。そのような文科省による統治によって大学も、学内においては自らが文科省的な動きをせざるを得ない。文科省が大学にやっている統治を、大学は早稲田文学編集室におこなわざるを得ないのである。前に、大学は金を出すが口は出さないことが理想だといったが、文科省も金は出しても口を出すべきではないのだ。
僕は「商標登録」の文字を見ながら、『早稲田文学』を創刊した坪内逍遥に大学はきちんと断りを入れたのだろうか、と思った。早稲田大学(文学学術院)よりも逍遥の批評性の方が当然〈偉い〉はずだろう。
主な休刊の理由は、「カリキュラム改革」によって『早稲田文学』を早稲田大学の学科コースのテキストとして使用しなくなった関係上、学費や税金を原資としている大学からの早稲田文学編集室への補助金が廃止されることによるようだ。「公式」の見解が出ているように、雑誌の内容や編集の問題ではなく、「カリキュラム改革」即ち「教育」の問題が大きいというのはその通りだろう。私自身熱心な『早稲田文学』の読者ではなかったが、ヌーボー・ロマン特集や大西巨人の記事、あるいは絓秀実の批評などが頻繁に掲載されていた時は、買いもしたし、図書館でもコピーした記憶がある。無料であった『WB』も何冊かは持っている。最近の『早稲田文学』も読んではいたが、内容として少なくとも文学部の学生に「教育」を目的として読ませても良いのではないかと思う。ただ、文芸誌が学科の「テキスト」や教科書となること自体が必ずしも良いとは思わないが。
最近思うのは、大学の資本が特に文化、学術の側面において、相対的に大きくなっていることだ。文化・学術出版業界は「不況」の中で大学の資本に頼るようになっている。勿論、出版資本の相対的自立性は高度成長期からバブルまでのかりそめのものだとは思うが、その自立性が弱まった結果、大学資本が前面に押し出されてくるようになった。最近「批評の衰退」がネットで議論されていたようだが、批評の相対的自立性も、その出版資本の自立性と軌を一にしていたわけなので、大学資本が前景化されてくる中で、出版における批評なるものが退いていってしまうのも当然なのかもしれない。大学資本による批評の包摂ということになるだろう。『早稲田文学』もこのような流れの中にあるのではないか。早稲田文学編集室は、大学から補助金を受けながらも、相対的に自立していたはずである。休刊をめぐる「公式」の発表の行間を読むと、その自立性を維持するための、編集発行に関わった教員や学生、それらを含んだ編集員の尽力や献身という名の低賃金労働があったのだと推測される。これらは雑誌の自立性と関わることだろう。大学に資金は出させるが口は出させない、というのを維持するためには、補助金を何とか必要最低限とする必要があるからだ。むしろ僕は大学は金は大いに出して口は一切出さないというのが、出版における言論の自由に資するやり方ではないかと思っている。大学とは本当はそういう役割なのではないのだろうか。
しかし、2022年4月に早稲田大学が「早稲田文学」を「商標登録」したとあるように、大学資本による出版の包摂が進んでいく。これは『早稲田文学』が担ってきた、創作と批評の蓄積が大学へ包摂されていく過程である。「カリキュラム改革」の結果、『早稲田文学』の「テキスト」としての役割を終えたというが、そもそもその「カリキュラム改革」とは何か?という問題がある。早稲田大学の文芸を扱うコースで、『早稲田文学』的な創作や批評性が必要でなくなる「教育」とは何なのだろうか。それにも拘らず大学は「早稲田文学」を自らのために商品化することには余念がないのだ。これは『早稲田文学』を大学のための文化的商品として作り変えることである。そのような大学による文芸誌の商品化の先に、言論の自由というのはあるのだろうか。そこでは大学の掲げる(資本主義が掲げる)コンプライアンスとリベラルな道徳主義的言論しか許容されないのではないかという懸念しかない。
大学自体は文部科学省によって補助金による統制を受け、常に企業のように利益を上げることを要求され、内部留保を蓄積するよう暗に指令されている。そのような文科省による統治によって大学も、学内においては自らが文科省的な動きをせざるを得ない。文科省が大学にやっている統治を、大学は早稲田文学編集室におこなわざるを得ないのである。前に、大学は金を出すが口は出さないことが理想だといったが、文科省も金は出しても口を出すべきではないのだ。
僕は「商標登録」の文字を見ながら、『早稲田文学』を創刊した坪内逍遥に大学はきちんと断りを入れたのだろうか、と思った。早稲田大学(文学学術院)よりも逍遥の批評性の方が当然〈偉い〉はずだろう。
















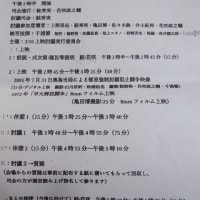



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます