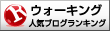およねは、一年前働き者の亭主を亡くした。無口だが頼りがいのある優しい男だった。二度流産して子供の産めない身体になっても、亭主の兼蔵はおよねを、羽根でかばうようにいたわるところがあった。間もなく四十になるおよねは一人ぽっちになった。
ある日、注文先に内職の仕上り物をを届けて帰ると、裏店の井戸端に倒れている人の影をみてゾッとした。男は、名を忠吉といい十九歳の桶職人だった。聞けば、仕事にありつくために、人を探しているという。空腹をごまかそうと、水を飲もうとして気を失ったと、顛末を話した。飯を出してやると見苦しいほどがつがつ食べたが、汚れた着物に似合わず、きっちり両膝を揃えて座り、言葉遣いも丁寧な、礼儀正しい好青年に見えた。聞けば、 今晩泊まるところが無いという。
およねは気の毒に思い、仕事が見つかるまで忠吉を家に置いてやろうと思った。これまでは亭主に頼りきった生活をしていた自分が、誰かに頼られるということが気持ち良かった。亭主が死んで以来笑いを忘れていたおよねの顔に笑顔が蘇った。自分でも気づかない微かな笑いだった。
半月ほどたって、忠吉の仕事が見つかった。「当分おいてくれ」という忠吉のたのみを受け入れて、およねはまた忠吉と過ごすことになった。そのうち養子にとって、何処からか嫁をむかえてやろうとさえ夢想した。ある日、それを忠吉に告げると「少し考えさせてもらうよ」と答えるばかりだった。
それからしばらくたって、夜中、およねは誰かに胸を押えられる感じがしで眼が覚めた。忠吉だった。「嫁なんかいらないよ、おばさんだけいればいいよ」と胸に顏を入れてきた。
およねは、必死に抗った。だが男の力にかなわなかった。寝間着の紐がすべて抜き取られて、およねは力を抜いた。
およねの肌が見違えるように艶やかになった。当然、裏店の女房達の噂になった。だがおよねは幸せだった、それでいいと思っていた。
ところがある日、この裏店に若い女が現れた。尻軽女で知られる十九歳の大工の娘だった。その娘と忠吉が、暗がりの井戸端でこそこそと話をしているところをおよねは目撃した。時を同じくして忠吉のおよねに対する態度がぞんざいになった。そして、ついに喧嘩になって、忠吉は家を出て行った。およねはまた以前のような年老いた女になってしまっていた。 「時雨みち」より
・およねは、死んだ亭主が下駄職人だったので、鎌倉河岸にある履物屋羽生屋から下駄、草履の緒を作る内職をもらい、細ぼそと暮らしている。
・およねが三島町の裏店の近くまで来たのは、六ツ半(午後7時)ころだった。
・鍋町の通りを横切って、家に近くなると、およねは足どりをゆるめて、のろのろと歩いた。・・およんねは今度正月を迎えると四十になる。
・数日前に、深川の瓢箪堀のあたりで火事があったことは、およねも耳にしている。三間町から元町の一帯にかけて、30軒ほどの家が焼ける大火事であった。
小説の舞台:深川 地図:国会図書館デジタルコレクション江戸切絵図「日本橋内神田両国浜町」 タイトル写真:万世橋