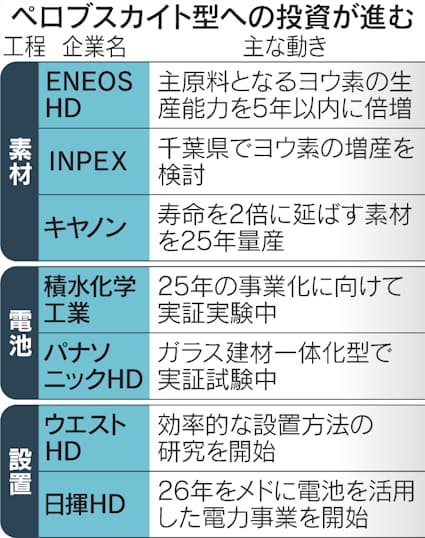米大手投資ファンドのカーライル・グループが、日本企業の大型買収に向けて4000億円規模のファンドを立ち上げた。
5月には1300億円で日本KFCホールディングスを買収する方針を明らかにした。2023年に同社最高経営責任者(CEO)に就任したハービー・シュワルツ氏は「日本事業の投資リターンの高さは驚異的だ」と指摘する。(聞き手は金融部長 河浪武史)
――5月下旬に日本で5番目となる企業買収ファンドを立ち上げました。規模は4号ファンドの1.7倍です。今、なぜ日本投資なのですか?
「直近の日本投資のファンド(第4号)のネット投資リターン(IRR=内部収益率)は28%と、ほかのファンドと比べかなり好成績だ。驚異的といってすらいいのではないか
。カーライルは4250億ドル(約67兆円)の運用資産があるが、地域密着のアプローチで国際展開しており、その成果が出てきた」
――日本は大企業が非中核部門の売却を進めています。商機でしょうか。
「4号ファンドは2020年に立ち上げて高い投資リターンを得たが、現在の環境はさらにもう一段異なる。
数十年にわたって来日の機会を持ってきたが、日本の政策や市場の環境をみると、あらゆる好条件がそろってきたように思える」
「日本ではハイテクや通信、消費ビジネス、メディアなどをカバーしている。日本市場には多様な産業に投資できる余地があるので、さらなる商機があると考えている」
――投資ファンドからみて政府の資産運用立国構想は評価に値しますか。
「非常に計画的かつ適切な手法で、さらに非常に丁寧なペースでビジネス活動を後押ししている。
政策というのは、投資ファンドにとって良いものかどうかというよりも、ビジネスにとって良いものか、価値創造にとって良いものかが大事だ。そうであれば、経済成長にとって良いものになるだろう」
――とはいえ日本の成長率自体は低く、円安のように不確定要素も多いですよね。日本投資は長期的なものですか、あるいは短期的なものなのでしょうか。
「カーライルが日本に進出してから2025年で25年になる。日本での評価を高めるための努力を積み重ね、日本で強力なブランドを確立してきたからこそ、今回の資金調達があったし、それは一時的なものではない。
地政学はもちろん考慮するが、常に何らかの投資機会があるものだ。企業投資には地域密着のアプローチが必要で、資本を投じて企業の成長を支援するということに尽きる」
――世界的に資金環境が厳しくなる中で、投資ファンドはドライパウダーと呼ぶ待機資金をなお多く抱えていますよね。
「カーライルには約700億ドルのドライパウダーがある。投資ファンド業界には潤沢な待機資金があるが、重要なのは利用可能な資本がそこにあるということだ」

ハービー・シュワルツ 米カーライル・グループCEO
Harvey Schwartz シティコープ(現シティグループ)などを経て、1997年ゴールドマン・サックス入社、最高財務責任者(CFO)や社長兼共同COOを歴任。23年からカーライルCEO。23年の報酬パッケージは1億8700万ドル(294億円)。
――その待機資金を使って、カーライルなど投資ファンドは「プライベートクレジット」と呼ぶ企業への直接融資も広げていますね。いまなぜ融資なのですか。
「プライベートクレジットは15年間にわたって伸びてきたが、その最大の理由は2008年の金融危機とその後の銀行規制だ。(商業銀行の規制が強まったため)我々のような投資ファンドが最も効率的に資金を提供できる主体となった」
「プライベートクレジット(私的融資)という言葉は、単なるクレジット(融資)に進化しなければならない。投資適格級の融資から非投資適格級、さらには流動資産担保融資まで、いずれもカーライルの事業の中で最も成長している部門のひとつだ」
――商業銀行の融資に比べて金利は高いですよね。それでも企業がプライベートクレジットを使う利点は何なのでしょう。
「誰が最も効率的に資金を提供できるのかという問題だ。コスト、条件、パートナーシップ、さまざまな要素がある。
企業は銀行と組むこともできるし、カーライルと組むこともできる。企業にとっては最も効率的に資金を調達するための柔軟性が高まったということだ。これがマクロシステムにとって最も重要なことだ」
――あなたは2018年までゴールドマン・サックスの共同COO(最高執行責任者)でした。銀行と投資ファンドの違いは何でしょうか。
「我々は投資ファンドは(年金や保険などの)受託者に代わって資金を投資・運用するビジネスだ。例えばカーライルは2200人の社員で4250億ドルの資産を管理している。
JPモルガン・チェースの資産規模は3兆〜4兆ドルくらいだろう。我々の富裕層向けのビジネスは急成長しているが、我々は預金も扱っていないし支店もない。商業銀行とは資本配分の方法が大きく異なるのだ」
――米国は政策金利が5%を超えているにもかかわらず、経済は引き続き堅調です。なぜですか?
「理由の一つは、米国の住宅ローン市場の構造にある。米国では住宅ローンの大半が固定金利であり(金利上昇は)住宅所有者にむしろ恩恵をもたらす。
今もし住宅を購入すれば7%超のローン金利を支払わなければならないが、2年前なら2.5%だ。固定金利による住宅所有者の(潜在的な)恩恵は5000億ドル規模なのではないか」
「もう一つの理由は連邦政府の構造的な財政赤字だ。かつて財政赤字の幅は(国内総生産比で)3%だったが、24年度は6%、25年度は7%になりそうだ。財政支出によって経済を刺激する要因が多くあり、データセンターなど国内で巨額の設備投資が進んでいる。
第三の理由として、そもそも金利上昇と景気減速に備えて企業がコスト削減などを進めてきたこともある」
日本はラストリゾートに(聞き手から)
巨大投資ファンド首脳の来日ラッシュである。インタビューでは各トップとも対日投資の大幅増額を口にするが、その受け答えはどうしてもきれい事になりがちだ。
ファンド勢に本音を問うと「世界を見渡すと日本くらいしか投資先が残っていない」。プライベートエクイティ(PE=未公開株)ファンドの2023年の投資回収額は過去10年で最低となった。米欧は利上げでLBO(借り入れで資金量を増やした買収)の効率が下がり、中国への投資は控えざるを得ない。低金利で借り入れによるレバレッジが効かせやすい日本は、ファンド勢の最後のよりどころとなる。
もっとも、ファンドの対日投資は日本経済に活力をもたらす。カーライルによる日本KFCの買収は、PBR(株価純資産倍率)を高めたい
三菱商事が非中核部門の切り離しに動いたためだ。ファンドを起点に産業再編が一気に進むようなら、低生産性という日本経済の長年の悩みを打破する材料になる。
【関連記事】
日経記事2024.06.17より引用