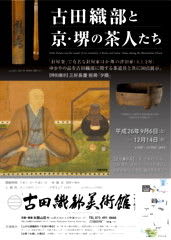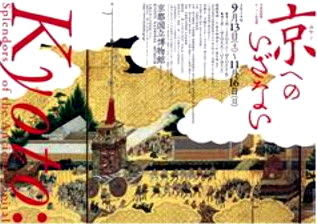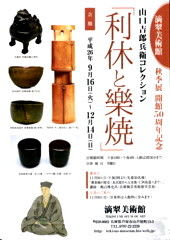名古屋

桑山美術館

所蔵茶道具展 侘び茶とその展開
期間:9月6(土)~12月7(日)

色紙 一休宗純筆
金銀泥の料紙に「雲はやみふりくる雨のあし引きの わたるひとこゑ山ほととぎす」の歌と山々を書いた作品。
箱書きは小堀遠州筆。
竹一重切花入 千利休作
つやのある肌で姿は末広がりで安定感がある。裏に利休のケラ判が朱書きされており、脇に「利休作」と孫の宗旦が添書きしている。
三島茶碗
縄目のような文様がぐるりと廻る茶碗。面白いのが半分に割れたためか金繕いをし、さらに底には鎹をうっているところ。姫路藩主・酒井宗雅の箱書きあり。
法語 春屋宗園筆
臨済宗の開祖・臨済禅師が弟子に与えた4つの喝「臨済四喝」を書いた墨蹟で、俗人の男(一俗漢)に与えたそうです。
春屋宗園は臨済宗の僧。茶人とも親しく利休は孫の宗旦を春屋に預けているし、織部の「金甫」や遠州の「孤篷」 も春屋に授けられたものです。
その他、茶杓では利休・道安・少庵の千家父子のものがありました。利休作は蟻腰と櫂先の造形が強調されているもので、道安作はやや細身、逆に少庵作がやや大ぶりでした。
桑山美術館、はじめて訪れましたが小さな美術館ながら過不足無く道具が揃っていると感じました。
またこちらの美術館は庭園も見所のようで「庭園散策ガイド」なる冊子も用意されています。

織部形燈籠
別名キリシタン燈籠

利休形燈籠

珠光形燈籠
この他様々な形の燈籠を鑑賞することが出来ます。

桑山美術館

所蔵茶道具展 侘び茶とその展開
期間:9月6(土)~12月7(日)

色紙 一休宗純筆
金銀泥の料紙に「雲はやみふりくる雨のあし引きの わたるひとこゑ山ほととぎす」の歌と山々を書いた作品。
箱書きは小堀遠州筆。
竹一重切花入 千利休作
つやのある肌で姿は末広がりで安定感がある。裏に利休のケラ判が朱書きされており、脇に「利休作」と孫の宗旦が添書きしている。
三島茶碗
縄目のような文様がぐるりと廻る茶碗。面白いのが半分に割れたためか金繕いをし、さらに底には鎹をうっているところ。姫路藩主・酒井宗雅の箱書きあり。
法語 春屋宗園筆
臨済宗の開祖・臨済禅師が弟子に与えた4つの喝「臨済四喝」を書いた墨蹟で、俗人の男(一俗漢)に与えたそうです。
春屋宗園は臨済宗の僧。茶人とも親しく利休は孫の宗旦を春屋に預けているし、織部の「金甫」や遠州の「孤篷」 も春屋に授けられたものです。
その他、茶杓では利休・道安・少庵の千家父子のものがありました。利休作は蟻腰と櫂先の造形が強調されているもので、道安作はやや細身、逆に少庵作がやや大ぶりでした。
桑山美術館、はじめて訪れましたが小さな美術館ながら過不足無く道具が揃っていると感じました。
またこちらの美術館は庭園も見所のようで「庭園散策ガイド」なる冊子も用意されています。

織部形燈籠
別名キリシタン燈籠

利休形燈籠

珠光形燈籠
この他様々な形の燈籠を鑑賞することが出来ます。