アビダンマの際だった特徴
アビダンマは、哲学的な解説方法を厳密に順守するということの他にも、いくつかの注目すべきやり方で体系化作業を進めている。その一つは、アビダンマ・ピタカの主要な巻において、mātikā(「論母」)(カテゴリーのマトリクスと一覧)を体系全体の青写真として使っていることである。このマトリクスは、Dhammasangani(法集論)の最初に記載されており、アビダンマ・ピタカ自体の序となっており、アビダンマ方法に特有の122の分類モードが掲げられている。これらのうち、三法(tika)(基本的なダンマを三句ワンセットで表したもの)が22個、残りの100は二法(duka)(分類の基礎として使われる二句ワンセット)である。[3] このマトリクスは、ダンマの目的にそって決められた原則に従って、複雑な経験世界を整理するのに役立っている。
たとえば三法では、善、悪、どちらとも言えないの三状態がワンセットであり、楽な感覚、苦しい感覚、中立的な感覚の三状態、カンマ(業)の結果、カンマの結果から生じた、どちらでもないの三状態がワンセットとなる。二法は、原因である、原因でないの二状態、原因に付随する、付随しないの二状態、条件付けられている、条件無しの二状態、世俗的、超俗的の二状態などがワンセットとなる。このようにカテゴリーを選択することで、マトリクスは現象全体を包含し、哲学、心理、倫理の多様な角度から現象の性質を照らし出す。
















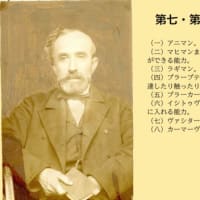

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます