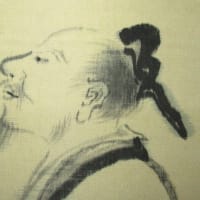練上(平)茶碗 松井康成作
共箱 高台内に「康成」のサインあり
サイズ:口径150*高さ55*高台径

練上茶碗を購入しました。
早速、一服
脇のお菓子の乗せた皿はお気に入り・・明治以降のもので花紋様に訳の分からない蔦か文字、いいですね~欠けがあったので金繕いしました

ん~、いいか悪いかと言われると微妙かな~
高台内の胎土が薄すぎて、持っているとお湯の熱さが伝わり過ぎます。

平茶碗に白い釉薬もお茶が残り目立ちすぎ・・これは新発見
練上という技法でいい作品を製作していますので、私がどうのこうのと批評することは出来ませんが、高名な作家のすべての作品がいいものとは限らないのです
では買わなければいいではないかと思うでしょうが、使ってみないと解らないことが多いのです・・
お茶碗は満点でなくてはならない要素が高い器です。景色が良くてもお茶が立てづらい、飲みづらいではNGです。
口を近づけた時、飲むときの感触も大切です・・・微妙なのです・・・お茶碗は
でも綺麗ですよ


最近は作品が気に入らなくて返品が多く嫌気がさしていましたが、これは所有することにしました
松井 康成:まつい こうせい、1927年(昭和2年)5月20日 - 2003年(平成15年)4月11日)は、日本の陶芸家。
国の重要無形文化財「練上手(ねりあげ)」保持者(人間国宝)。本名、美明。 長野県北佐久郡本牧村(現:望月町)生まれ。
10歳代後半の戦時中に茨城県笠間町(現:笠間市)に疎開する。旧制神奈川県立平塚工業学校、明治大学文学部文学科卒業。30歳の頃には同市内の古刹月崇<げっそう>寺の住職となりました。
3年後には境内に窯を築いて中国や日本の古陶磁器研究を本格的に始め、やがて練上の技法に研究の的をしぼって、日本伝統工芸展や個展を中心に作品を発表しました。
そして、1993年にはこの「練上手という技法を集大成し、伝統技術を基盤にした現代の個性豊かな陶芸のあり方を提示した。「練上手」<ねりあげで>の技術保持者として重要無形文化財(人間国宝)の認定を受けるに至っています。
共箱 高台内に「康成」のサインあり
サイズ:口径150*高さ55*高台径

練上茶碗を購入しました。
早速、一服

脇のお菓子の乗せた皿はお気に入り・・明治以降のもので花紋様に訳の分からない蔦か文字、いいですね~欠けがあったので金繕いしました


ん~、いいか悪いかと言われると微妙かな~

高台内の胎土が薄すぎて、持っているとお湯の熱さが伝わり過ぎます。

平茶碗に白い釉薬もお茶が残り目立ちすぎ・・これは新発見

練上という技法でいい作品を製作していますので、私がどうのこうのと批評することは出来ませんが、高名な作家のすべての作品がいいものとは限らないのです

では買わなければいいではないかと思うでしょうが、使ってみないと解らないことが多いのです・・

お茶碗は満点でなくてはならない要素が高い器です。景色が良くてもお茶が立てづらい、飲みづらいではNGです。
口を近づけた時、飲むときの感触も大切です・・・微妙なのです・・・お茶碗は

でも綺麗ですよ



最近は作品が気に入らなくて返品が多く嫌気がさしていましたが、これは所有することにしました

松井 康成:まつい こうせい、1927年(昭和2年)5月20日 - 2003年(平成15年)4月11日)は、日本の陶芸家。
国の重要無形文化財「練上手(ねりあげ)」保持者(人間国宝)。本名、美明。 長野県北佐久郡本牧村(現:望月町)生まれ。
10歳代後半の戦時中に茨城県笠間町(現:笠間市)に疎開する。旧制神奈川県立平塚工業学校、明治大学文学部文学科卒業。30歳の頃には同市内の古刹月崇<げっそう>寺の住職となりました。
3年後には境内に窯を築いて中国や日本の古陶磁器研究を本格的に始め、やがて練上の技法に研究の的をしぼって、日本伝統工芸展や個展を中心に作品を発表しました。
そして、1993年にはこの「練上手という技法を集大成し、伝統技術を基盤にした現代の個性豊かな陶芸のあり方を提示した。「練上手」<ねりあげで>の技術保持者として重要無形文化財(人間国宝)の認定を受けるに至っています。