〈リバイバル・アーカイブス〉2021.9.20.~10.4
原本:2016年9月16日

じないまち富田林(とんだばやし) 山中田(やまちゅうだ)坂
江戸期、じないまちの出入り口をなす四坂のひとつです。この後、石川を渡り千早街道・観心寺道として、東部・東南部への交通の要でした。

葛城山(写真)、金剛山、二上山などが、横の展望広場から見渡せ、見晴らしがとてもいいです。というのも、この崖が河岸段丘崖にあたり、下は石川の氾濫原、上の街区は河岸段丘面です。

近くで見るといまにも動き出しそうな石垣ですが、崩れたりしたことがないそうです。

お城の石垣を思わせる石積み

すぐ近くの石川の石が使われています。(1) 花崗岩・和泉砂岩・チャートのほか、ごくまれに「汐の宮火山岩(安山岩)」(2)が含まれています。
(1):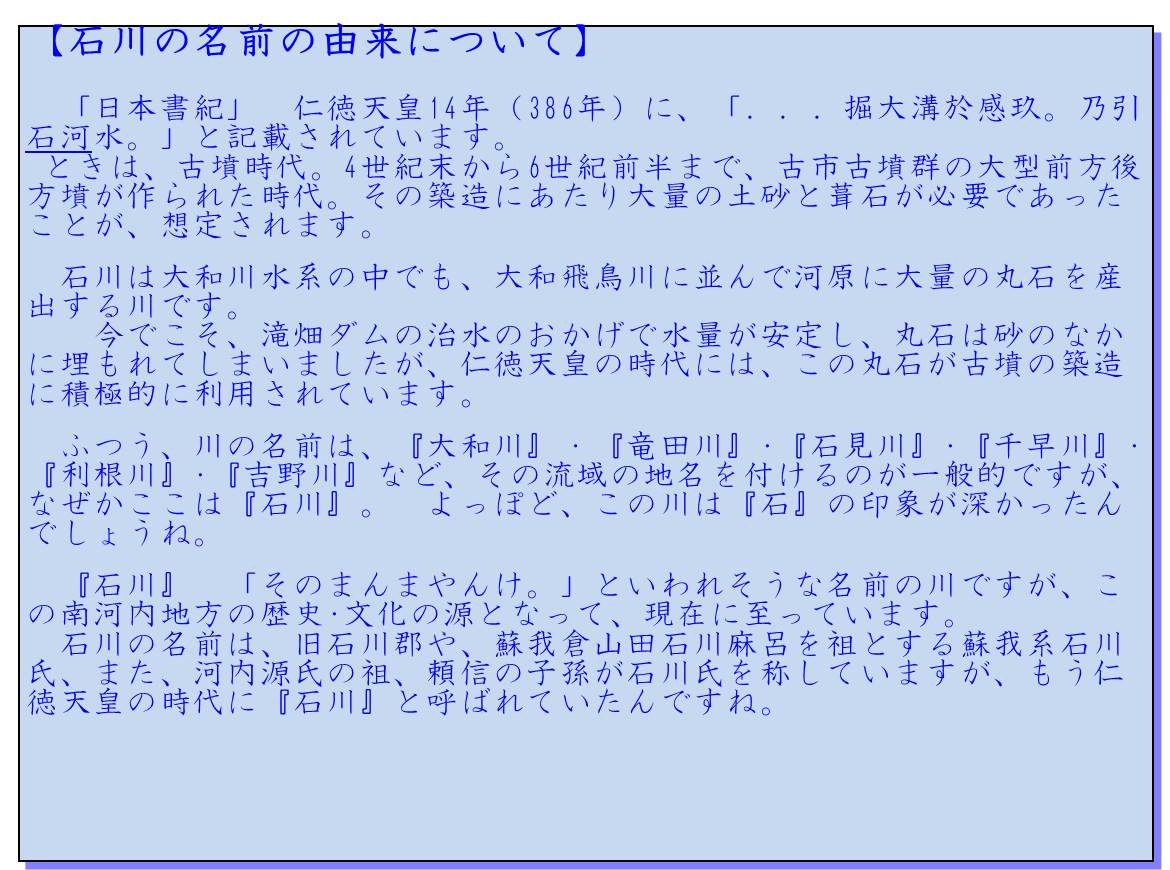
(2):私の富田林百景+ 「 横山潮湧石 」 2013.10.4.

明治時代の一時期、旧郡役所跡の石垣

お城の石垣のように見えます。

じないまち四坂のひとつ、向田(こうだ)坂横の勝間家住宅(旧 南杉山家住宅)の石垣
江戸末期の建築。 明治期の一時的、石上露子(杉山 孝(タカ))さんが住んでおられたことがあります。有名な『小板橋』の詩歌はここで創作されたようです。

ていねいに造られた石垣
坂のところは1mくらいですが、横の崖の部分は3mくらいはある石垣です。

街の中心、城之門筋御坊町 御坊さん、興正寺別院(国の重要文化財)

ここも石川の丸石を利用して石組みが見られます。

花崗岩・砂岩・チャートの配合は、石川の石の組成そっくりです。

寺内町四坂のひとつ、亀が坂

ここは堺筋。明治期に新たに寺内町から石川へ降りる新道がつくられた部分の側道です。
上が新道、下が先ほどの山中田坂を降りた街道の側道。

ここにも一部石垣が残っています。急階段ですね。

その反対側 上が堺筋

すごい石垣です。

山中田坂の背割井路
底も石組みされています。坂を下る前のところなので、井路底浸食防止のためでしょうか。

東筋出口横の背割井路
江戸期は「悪水」(生活用水)を流した水路。今は下水になっていますので、雨水以外はあまり流れません。
深い谷になっています。煉瓦塀がみえますが、街中にもいくつか明治期の煉瓦塀が残っています。

興正寺別院の向かい、真宗本願寺派 妙慶寺の石垣

造った時代が違うのかもしれません。打ち込み接ぎと切り込み接ぎ

こちらは、切り込み接ぎ

こちらは、融通念仏宗 浄谷寺の石垣

ここも、2種類の石垣が見られます。浄谷寺は江戸・明治期とだんだん西側に境内が整備されたようです。

じないまちには、街中にもけっこう石垣があるんですね。
 関連記事:路傍の石 - 富田林じない町 2015.6.28.
関連記事:路傍の石 - 富田林じない町 2015.6.28.
2016.9月16日 (HN:アブラコウモリH )



























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます