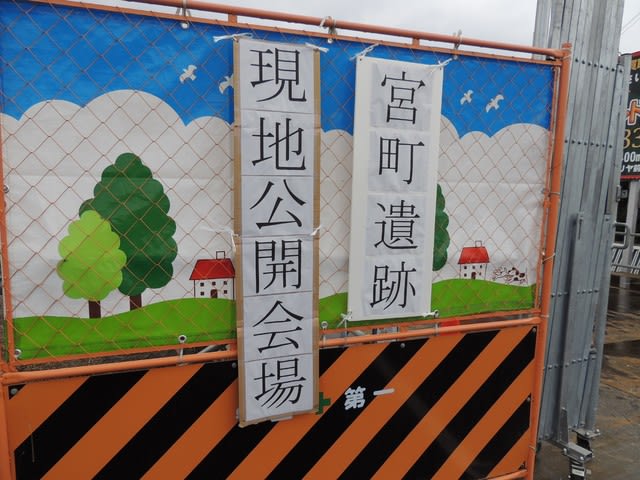今回は通法寺に関連して、「壺井八幡宮」についてご紹介いたします。河内源氏は頼信・頼義・義家と三代にわたり、この地から各地へ出陣して大功をたて、武将としての地位を不動のものにしました。 . . . 本文を読む
暖かくなってきました。今回は八尾市にある「しおんじやま古墳」を訪れました。八尾市の東部山麓にある全長160mの前方後円墳です。5世紀前半、古墳時代中期に作られた、北・中河内最大の古墳で、この地域一帯を治めた人物の墓と考えられています。墳丘は、前方部の頂上まで上がることができ、河内平野が一望できます。 2019/3/18 訪問 辰じいです . . . 本文を読む
先日訪れた「近つ飛鳥博物館」の発行誌「大阪府立近つ飛鳥博物館だより (44号 03.2016)」の中にあった「近つ飛鳥風景」の記事が目に留まり、3月29日、記事の「層塔」を探索に行きました。当日は、叡福寺の桜も満開状況の中、あちこち目を奪われながら&地元の方に訪ねながらカメラ片手にシャッターを切ってきました。辰じいです。 2018.3.29 AM撮影 . . . 本文を読む
,先週の暖かい日(2/14)、公民館講座が終わってから野中寺と津堂城山古墳他を訪ねました。 津堂城山古墳は、2月11日に「富田林市きらめき創造館」で受講した「南河内郷土探訪~世界遺産登録をめざして」の 講座の中で紹介されました。4月上旬になると内濠部北側の草花園では、菜の花・桜が、秋にはコスモスが咲くそうです。 . . . 本文を読む
先日の公民館館内講座で紹介のあった、舟渡池へ行ってきました。舟渡池公園は初めての訪問です。次いで、「みはら歴史博物館」と「黒姫山古墳」へ。「みはら歴史博物館」では、「特別展 河内鋳物師(かわちいもじ)の誇りⅣ」 が開催されており(1月28日まで)また、常設展示室では黒姫山古墳等からの出土品(鉄製甲冑類や埴輪他)が展示されています。いづれも、実物だそうです。65才以上は入館無料(年齢確認があります)。 一度、行って見られては! 2018.1.25 辰じい でした。 . . . 本文を読む
先日、ご紹介いただいた「宮町遺跡現地公開・説明会」に参加しました。百景メンバーも数名来られていました。当日は雨も上がり、少々地面がぬかるんでいましたが、スタッフに支えられ約1時間、ゆっくり見学できました。 感謝!紹介メール、ありがとうございました。 辰じいです。小生も参加いたしましたので、リレーし追加いたします。1月6日(土)11時~12時まで、文化財保護課主催で現地説明会が開催された。当日は小寒に入り寒さ厳しい状況の中、たくさんの方々が参加されました。宮町遺跡は、古墳時代から奈良・平安時代の集落跡です。当該近郊地域には、喜志・粟ヶ池・桜井・中野・新堂・畑ケ田遺跡等、東高野街道沿いに多くの遺跡が発掘調査されております。本日は現地説明会の状況を紹介します。 . . . 本文を読む
観光map片手に、葉室地区周辺を巡ります。いつでも来れるがなかなか行けず今頃になってしまいました。今回は、愛用の電チャリで自宅スタート、約3時間の行程です。敏達天皇陵から科長神社・小野妹子の墓他を巡ります。Photo 2017年9月21日 辰じいです。 . . . 本文を読む
太子四つ辻バス停から北へ約10分進むと通法寺(国史跡)に至る。通法寺は、1043(長久4)年に河内源氏の祖源頼信が子の頼義とともに小堂を建て前九年合戦のとき、頼義が浄土教に帰依し、阿弥陀仏を本尊としてから河内源氏の菩提寺となった。 その後、南北時代および戦国時代の兵火で再三焼失、1700(元禄13)年、江戸幕府五代将軍徳川綱吉のときに、子孫の多田義直の上表を受け大僧正隆光や柳沢吉保らにより、壷井八幡宮・壷井神社とともに再建された。 しかし、明治時代初期の廃仏毀釈により廃寺となった。今回は、その通法寺跡・源氏三代の墓・壷井神社を巡ります。辰じいです。 . . . 本文を読む
「久宝寺寺内町の歴史は、450年以上前、戦国時代にまでさかのぼります。文明二年(1470年)に本願寺第八世蓮如上人が久宝寺で布教した際、「帰するもの市の如し」といわれるほど帰依するものが多かったので、文明十一年(1479年)この地に西証寺を建立しました。後に西証寺は顕証寺と寺号を改め、天文十年(1541年)頃にこの御坊を中心として久宝寺寺内町が誕生しました。久宝寺は地理的に要衝の地にあり、中・南河内の門徒集団を束ねる拠点として多くの門徒衆が集まり住むとともに、商工業者も集まって活発な商業活動が行われるようになりました。 江戸時代以降は、農村部における商業の中心-在郷町-として発展しました。久宝寺は旧大和川(現在の長瀬川)の船運の要衝として、また堺から八尾街道を経て京都に至る主要幹線の中継点として栄えました。しかし慶長年間に本願寺の東西分派にともなって久宝寺の一部の住人が分離独立して八尾寺内町を建設し、宝永元年(1704年)に大和川付け替えが行われると、それ以降地域の中心は八尾寺内町に移っていったのです。」(八尾市まちなみセンターリーフレットから) By 辰じい . . . 本文を読む