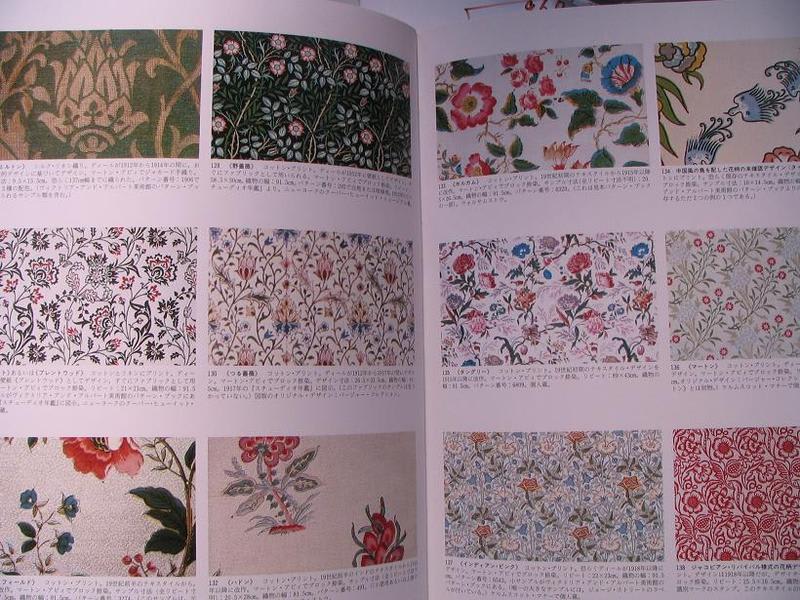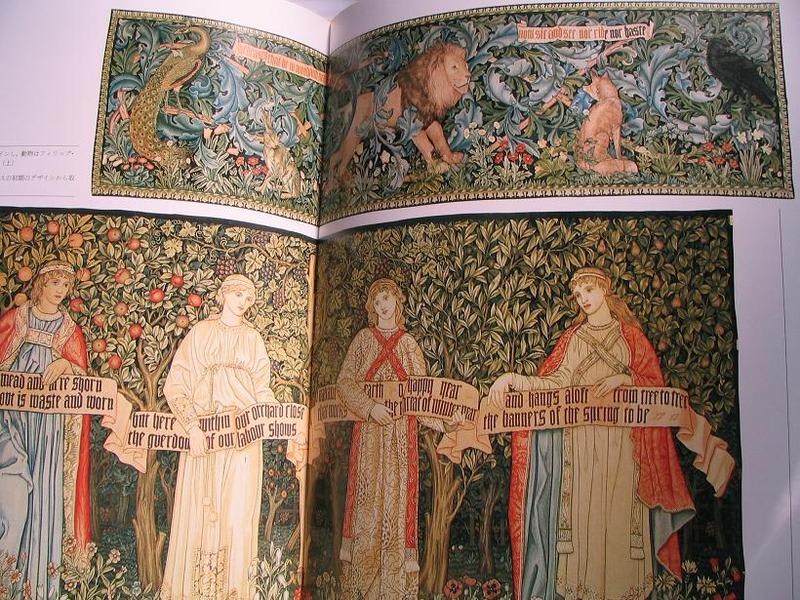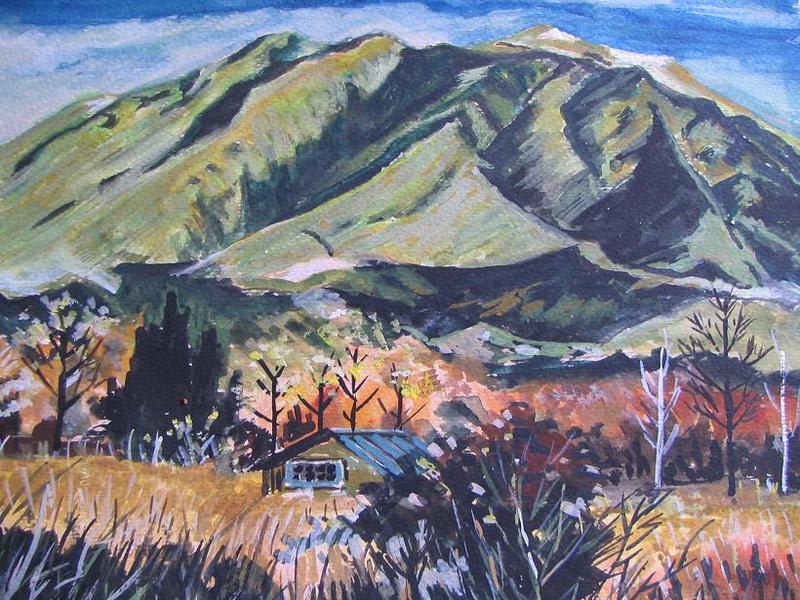わぉ~~、カッコいいではないか!
これは私です!と言いたいけれど、チガイマス。
先日の農大収穫祭の最終日、買い物をしたあと立ち寄った
馬事公苑で大学馬術部の障害物レースが開催されていたのだ。
全国の大学からチームや個人でエントリーしているらしい。
一緒に行った動物好きの例の人(妻)は、またしても大興奮!
まさに目の前を馬が疾走していくので、時にはバラバラと馬が
蹴った土が頭上に降ってくるほどだが、そんなことはモノトモセズ
柵にかじりついて離れない。
いい顔をしている。
中には女子もいたが、
なかなか決まっていた。
妻は「わ~っ、オスカルかユリウスみたい~」とうっとり状態だ。
では、美しい馬たちをご覧ください。
おぉ!
あぁ!
はぁ!
「人馬一体」とはまさにだな、と感じる光景を幾度となく目にした。
タイミングをミスして障害の前で立ち往生してしまう馬。
コースを間違えて「アレ?」という表情の馬。
片っ端から障害を落として騎手に気合を入れられる馬。
レース途中で失格になってションボリと引き返す馬。
ミスをしても集中して盛り返してくる馬。
ノーミスでクリアして意気揚々と戻る馬。
それぞれ騎手たちが叱咤したり、なだめたり、褒めたり、
喝を入れたりしている。
息が合わなければ到底いい成績は出せないな、と思った。
馬具以外にも美しい馬の写真や、
アクセサリー、ステーショナリー、
その他雑貨などすべて馬がモチーフで、覗くだけでも楽しい。
近くの方は是非一度立ち寄ってみてください。
傍らで妻が「はあ~~~っ」とため息。
「馬が障害を飛ぶたびに一緒に力んでたら
ものすご~く疲れちゃった…」と言う。
オマエ様もちょっと並足でも
されて気を静められよ。」
と馬が…。
結局、3時間あまりの
立ち通し観戦に私も付き合わされてしまったのだった。
(観覧席もあるのだが、カブリツキじゃなければダメなんだ
なあ、例の人は…)