縄文から古墳時代まで富山にはヒスイ加工遺跡が多いのだが、富山の考古学の先生方から「出土品のヒスイは糸魚川産だけでなく、富山沖にヒスイの鉱床があり、朝日町の海岸に打ち上がった富山産の可能性がある」という話を何度か聞いている。
「富山沖のヒスイ鉱床」について、何を根拠にしているのかと不審に思っていたのだが、ついに記述のある専門書を見つけた。

「富山沖に想定されるヒスイ鉱床」と記述はあるが、なんと本にも根拠の記述は無かった!
山から崩落して河川で砕かれ、海の波で丸められた原石を「海ヒスイ」と呼ぶが、山ヒスイ、川ヒスイ、海ヒスイはそれぞれ大きさや形状に特徴を持つ。
遺跡から出土する原石は大きくても赤ん坊の頭サイズとそれほど大きくなく、丸みもあることから山や河川で拾ったヒスイではなく、海岸で採取したヒスイというのが考古学的な一般見解のハズ・・・。
海底の鉱床から打ちあがったヒスイにはその過程がない訳だから、でっかくてゴツゴツしたヒスイ原石が富山の海岸に打ち上がっているのか?
そんなことはない。
ヒスイ拾いをする人なら誰でも知っていること。

糸魚川市の須沢海岸(ラベンダービーチ)から姫川方面(東側)を望む。
最寄りの海岸までまっすぐにヒスイが打ち上がるという考え方も変で、海流に運ばれてもっと広範囲に分布しないのは変じゃないの?

同じく須沢海岸から富山方面を望む・・・糸魚川は海岸段丘が発達しており、素潜りして確認した限りでは海底も同じく段丘が発達しているようだが、沖合から岸に向かって重たいヒスイが打ち上がるには段丘を幾つも越えてこないとねぇ~。
隣りの県だし、海の中に県境が引かれている訳でもないのだから、何も富山産の可能性とまで産地に拘らなくてもいいようだが、おらがクニの自慢にしたいのだろうか。
先日、糸魚川での講演でその事を話したら、聴衆から「そんなこと言うなら県境に防波堤を作ってヒスイが富山に流れないようにしろ!」と、私も知っている鉱物方面の大御所が怒っていたと聞いて笑ってしまったが、私にとっては講演で笑いを取れる有難いネタでもある。
地学や鉱物の専門家に聞いても私と同じ見解だったが、富山にも地質学者や鉱物学者はいるだろうに、考古学者と同じ見解なのだろうか?
富山沖に蛇紋岩帯が露頭しているという発見でもあれば、私も聴く耳は持つ。
例えば遮光器土偶は宇宙人である!と同じレベルで、可能性だけなら何でもありだ。












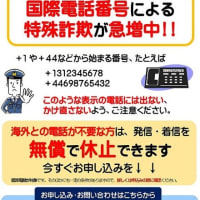







日本海沿岸の海底については調査自体は進んでいないが、これまでの地質分布図等から富山の海底にも翡翠を含む地質があるであろうという予想は別におかしくもない話で、宮崎・境海岸の位置する朝日町役場等が海底から打ち上げられたのではないかという説に言及するのはお国自慢という訳でもないだろう。
そもそも翡翠海岸の翡翠の由来が海底かあるいは川上かに関わらず産地は富山になる訳で、これを糸魚川産だと強弁するのはいささか無茶であり科学的な立場に立った人間の発言とは思えない。(産地と由来はまた別の話だからだ。)気に入らないなら本当に川を封鎖するか翡翠海岸の海底を調べあげれば良いのであって、専門家ならば地質図を元に翡翠が産するか産しないかを確かめてからあれこれ述べるのが科学的には正しい態度であろう。
故に翡翠の産地を語る際には【糸魚川とその周辺に産する翡翠】という表現を用いる。
できもしないことを大御所とやらが言ったと笑い話にするなど、本当に公演をする、あるいは参加する様な人間ならば恥をかくまえにやめた方がよろしかろう。そもそも海流の知識もないのに門外漢がまっすぐに流れるのは云々等と勝手に語って欲しくないが、例えば日本海学推進機構では、宮崎・境海岸と東の糸魚川につながる海岸で翡翠原石が取れるとしており、富山側が翡翠の唯一の産地を強弁している訳でもないだろう。
(富山県民生涯学習カレッジ本部
第3回 縄文人へのおくりもの 小島 俊彰より一部引用)
「ヒスイは、深い海底下の地殻の一部が低温で高い圧力を受けて誕生した。蛇紋岩がこのヒスイを取り込んで地下の20キロも30キロも深い所から上昇して、姫川の支流小滝川や青海川の上流に運び上げた。母岩から剥離したヒスイは、転石となって川を下りおち、一部は再び海に戻る。波に流される漂石は、親不知・子不知を越え、一部が宮崎の海岸に打ち上がる。入善町の海岸に達するものもあるという。宮崎浜の護岸工事の際に、一抱えはあるヒスイの大礫までも発見されている。自然の力の偉大さを見る思いがする。海底に産地があるのではと推定する人もある。
日本海に突き出た能登半島と深い富山湾、この両者が作りだした宮崎の浜の東から西への強い流れがヒスイを浜に呼び寄せたのだ。宮崎浜のヒスイが、富山湾の贈り物というのは、この意味でもある。」
(糸魚川ジオパーク地質めぐり 竹内誠より引用)
「糸魚川市及びその周辺には日本有数のヒスイ産地があり」
(飛騨外縁帯糸魚川-青海地域の熱水作用によるヒスイ輝石岩の形成年代 日本岩石鉱物鉱床学会 椚座圭太郎 より参考)
所謂ヒスイは飛騨外縁帯に含まれるという認識ですが、これら飛騨外縁帯については富山にも分布しており同じ高圧変成鉱物の存在が推測されうる。
少なくとも、遮光器土偶が宇宙人である等というオカルト話的な妄想(そもそも遮光器土偶はその発展の系譜は既に明らかにされているため疑問の余地はない)とイコールではないのは明らか。
まぁ名前から察するに、やたら地域にこだわりがあるようだが、日本各地にヒスイ産地は存在し(兵庫、鳥取、岡山等)、そもそも一部は5億年前に地中深くで形成されたものである。ヒスイは一ヶ所にまとまっているというより同じ地質帯のものが各地に分散したり、違う形成を経たもの等多様性があるため、富山産の大礫の例等、少なくとも一定の根拠があって富山沖海底由来の原石の可能性を指摘して述べられているのだろう。(もちろん過去の海流運動で石器時代とは地形や鉱床の分布も変化しており多角的な研究が求められるだろうが)
自称専門家が分かりもしない遮光器土偶宇宙人説を持ち出して可能性ガーと笑っているのは滑稽という他ない。ならばビッグバンにしろ進化論にしろ可能性だから信じるに値しないとでも言えばよい。もちろん科学の世界では通用しないだろうが仲良しクラブの大御所学者とやらはうなずいてくれるかもしれない。
まぁ、ネットの個人のブログでこれ以上言った所で無駄であろうがね。
富山にヒスイが露頭した渓谷があり、河で拾えるなら話は別ですが、ご存知なら教えてください。
また出土ヒスイが糸魚川産であるとされている考古学的定見の根拠は、京大の藁科教授の蛍光X線分析結果報告によるものですが、残念ながら蛍光X線分析では産地特定には無理があり過ぎるとする鉱物学的な見解もあります。硬玉ヒスイは多結晶鉱物なので、糸魚川市内で拾ったヒスイですらチャートは一致しませんし、同じ原石であっても調べる場所が違うと一致しない可能性があります。
しかし文献史学や考古学の長年の研究を総合的に判断すると、出土ヒスイは糸魚川を流れる姫川水系と青海川水系産であることは疑いようがないというのが現在の考古学の定説。
糸魚川の古名がヌナカワであったのも、古語においてヌは輝く玉であり、ヌナカワとはヒスイなす川であるとする古事記や万葉集、出雲國風土記を研究した文献史学の解釈もありますが、富山県内にヌナカワの類似地名や神話、文献があったら教えてください。
もの凄い長文コメントを書くだけの根気と知見がおありなようですので、私のようなヒスイ職人の与太話に付きあうより、論文をお書きになって考古学会の定説に一石を投じてみたらいかがでしょうか?