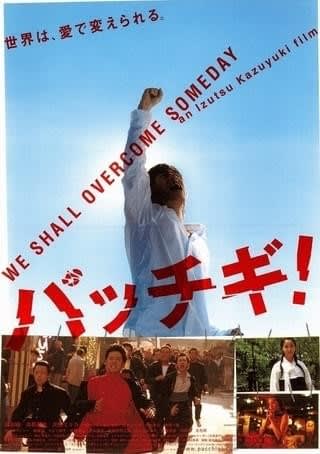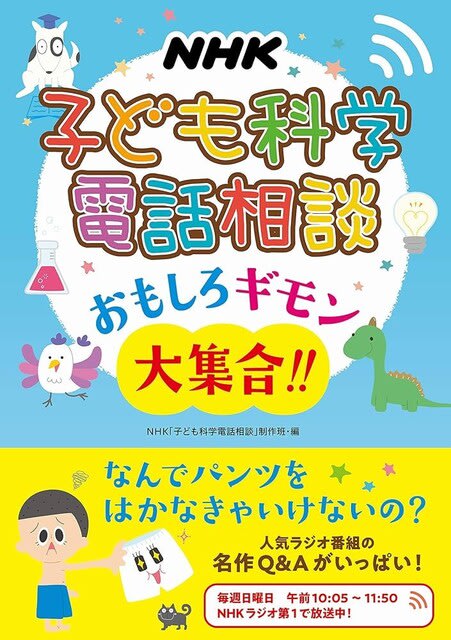沖縄戦を史実に忠実に描いた映画の代表ですよ。

皇国史観のナショナリストは「自虐史観」というだろうが、自説に都合の悪い情報に触れるのも大事。
脚本は新藤兼人、監督が岡本喜八で、製作陣も俳優も戦争体験者ばかりの東宝映画だから、「永遠のゼロ」のようなファンタジー映画とは次元のちがう硬質リアリティ。軍部と沖縄県民の板挟みになった県職員の苦悶も丁寧に描かれている。
将兵の回顧録を読むとほぼ一致した内容だが、司令部は民間の娼婦を高級参謀用の従軍慰安婦として徴用して、食料がなくなると艦砲射撃の真っただ中に放り出した目撃談が書かれている。
映画には描ききれなかった悲惨なできごとことは沢山あり、いろんな立場の人の情報を網羅してこそ史実が浮かびあがるのだ。
映画に描かれているが、わたしが知らなかった史実もある。「白襷隊」の存在だ。
「ゴールデンカムイ」にも描かれているが、日露戦争の「旅順要塞戦」では、ロシア軍は地雷原と鉄条網を何段構えにした高地要塞から、大砲やマシンガンを乱射して日本兵を寄せつけなかった。

日本軍は打開策として夜陰にまぎれた白兵戦「切り込み」を決行したが、将兵は戦国時代よろしく敵味方の識別に白襷をしていた。決死の決意という意味もあったのだろう。俗に「白襷隊」と呼ばれているが、逆に夜目に目立ってマシンガンの的になり壊滅してしまった。
日本軍は同じことを沖縄戦でやっていたことが映画に描かれている。むろん全滅。
連合軍将兵は日本軍の命知らずの「切り込み」の不条理さにノイローゼになったりもしたが、インパール戦のころから隠しマイクで事前に察知し、対人レーダー照準でマシンガンで掃討する対策をしていたので、ほとんど成功する見込みはなかった。
マシンガンが乱射する銃弾にむかって日本刀と銃剣で突撃させられた将兵の絶望と遺族の無念・・・「白襷隊」には現地徴兵の少年もいた。
要するに沖縄戦の「白襷隊」は死ぬことが目的の「一億玉砕」の先駆けであり、それを沖縄県民に強要したのが沖縄戦だ。
保守政党のサポーターに質問しても知らなかったネ。あまりにもの勉強不足。
わたしの記憶では・・・と不確かな情報を元に歴史修正をしたがる保守政党国会議員よ、もっと勉強しろ!