柔道が初めて正式競技に採用された1964年の東京五輪で、無差別の金メダルを獲得したオランダ人のアントン・ヘーシンク氏が27日、オランダ・ユトレヒトの病院で死去した。76歳だった。
1メートル98の巨体で「オランダの巨人」と称されたヘーシンク氏は、オランダ代表として東京五輪の柔道無差別に出場。決勝で日本の神永昭夫氏(故人)と対戦し、けさ固めで一本勝ちを収め、優勝した。柔道の母国・日本にとって、地元開催だった五輪での最重量級で外国人選手に金メダルを奪われたことは、当時大きな衝撃として受け止められた。
その後プロレスラーに転向し、73~78年まで全日本プロレスで活躍。引退後は国際柔道連盟(IJF)理事、国際オリンピック委員会(IOC)委員などを歴任した。現在国際試合で着用されている、青色の「カラー柔道着」を提唱したことでも知られる。97年10月にIJFから初の名誉十段を授与され、2003年にはIJFの柔道殿堂入りも果たした。
〔読売新聞 2010年8月28日の記事より〕
* * * * *
来月9日から、世界柔道選手権が競技発祥国である我が日本の首都・東京で開催されます。しかし、柔道界のビッグイベントの開催を前に、世界を代表する偉大な柔道家がこの世に別れを告げました。その人物とは、1964年東京五輪の柔道無差別級の金メダリストであるオランダのアントン・ヘーシンク氏です。
オランダのユトレヒトで生まれたヘーシンクは13歳で柔道を始めます。建設作業員だった20歳を過ぎた頃、ヘーシンクはある日本人指導者と出会い、師事を受けます。その人物とは『生涯無敗』を誇った柔道家で、欧州の柔道普及に尽力した名伯楽である道上伯という柔道家です。道上の指導を徹底的に受けてメキメキと上達し、更に気弱だったヘーシンクは人格的にも変貌を遂げます。また、当時としては先進的な筋力トレーニングを体力作りに用い、柔道だけでなく様々なスポーツをトレーニングに取り入れていたそうです。更に、ヘーシンクはオランダでの稽古に飽き足らず、来日して数年間、講道館や天理大学を中心に武者修行。その成果もあり、ヘーシンクはまず欧州の頂点に立ち無敵を誇りました。
その後、ヘーシンクは、当然の如く世界の頂点を目指します。だが、最初のうちは柔道の本家の日本人選手には中々勝てませんでした。しかし、1961年にパリで開催された世界選手権で、ヘーシンクは神永昭夫、古賀武、曽根康治の3人の日本の精鋭を続けて破り、外国人選手としては初となる大会制覇を成し遂げます。ちなみに、この当時の柔道の大会はまだ体重で区分けした階級制ではなく、無差別級のみの時代でした。つまり、この敗北は外国人に最強の称号を奪われたことを意味し、柔道の母国としては許容し難い屈辱でした。同時にヘーシンクの戴冠は、3年後に迫った1964年東京五輪で全階級制覇を至上命令とされた日本に対する“黒船来襲”でもありました。
そして、開幕した東京五輪。柔道が初めて五輪の正式種目となった東京五輪では、4階級を実施しました。天敵ヘーシンクは無差別級にエントリーします。それに対し、日本は猪熊功と神永の2人のどちらかをぶつけるかで悩みました。ちなみに、猪熊は過去に1度もヘーシンクとは対戦したことがありません。しかし、来日したヘーシンクを天理大学で指導した経験を持つ日本の松本安市監督は、「神永の方がヘーシンクに勝てる可能性が高い」と判断し、重量級には猪熊、神永は無差別級に出場させることを決定。自国で覇権奪還を信じて疑わない国民は神永がヘーシンクに復讐することに期待してました。しかし、ヘーシンクの実力を熟知していた松本監督は、誰をぶつけても勝てないことを悟っていたので、これは苦渋の決断でもありました。
柔道の母国の真髄を発揮した日本は、軽量級で中谷雄英、中量級で岡野功、重量級で猪熊が圧倒的な強さを見せて順当に優勝します。そして、最も重要な階級である無差別級が、柔道競技の最終日である1964年10月23日に実施されました。無差別級には9ヶ国から9人しかエントリーしておりませんでした。当時のルールは現在のトーナメント方式とは大幅に異なり、3人が3組ずつに分かれて予選リーグを戦い、各組1位の選手は準決勝に進出。各組2位の選手は敗者復活リーグに回り、そこで1位の選手だけが準決勝に進む形式でした。なんと、この予選リーグで神永はいきなり優勝候補のヘーシンクと対戦。6分間フルで戦いますが、神永は決勝に備えて必殺技の体落としを封印したこともあり、ヘーシンクが優勢勝ちして1位通過。しかし、2位となった神永は敗者復活リーグで2試合余分に戦うことを余儀なくされました。
その後、両者は順当に決勝に進出。五輪の為に新設された東京・北の丸の日本武道館には、15000人の満員の大観衆が固唾を呑んで2人の対決を見守りました。決勝は10分間で行われました。ヘーシンクは198cm、120kg。一方、神永は179cm、90kgだったので、体が2回りも違ったそうです。試合序盤は膠着状態になり、神永はヘーシンクの誘いには決して応じません。5分過ぎに、神永の一瞬の隙を衝いたヘーシンクは支え釣り込み足で倒して押さえ込みに入りますが、なんとか神永は逃れます。7分には逆に神永が左体落としで攻勢を掛け、ヘーシンクの体は傾くものの不発。そして、試合開始から8分過ぎ。神永が技を掛けにヘーシンクの懐に入ろうとしますが、逆にヘーシンクが待ち構えたように得意の寝技に持ち込み、その巨体で神永を押さえ込みます。神永は必死に抵抗するも逃れることが出来ず、ついに9分22秒、主審がヘーシンクの一本勝ちを宣告。同時に、日本のお家芸の“柔道”が“JUDO”に屈した瞬間でもあり、国民に計り知れない衝撃を与えました。
ところが、試合終了直後、日本武道館の大観衆は予想外の行動を目にします。柔道の発祥国の日本の選手を破った事に対し、オランダの関係者が狂喜乱舞。畳の上に駆け上がって母国の英雄に抱き付こうとしました。しかし、ヘーシンクは押さえ込みの体勢のまま右手を挙げ、同僚が畳に上がるのを制しました。そして、主審の「一本」の声を聞いた後、ゆっくりと立ち上がり、神永への礼を尽くして畳を降りました。この時のヘーシンクの行動は、対戦相手を敬い、「礼に始まり礼に終わる」という柔道精神を具現化した行為として、現在でも高く評価されてます。なお、この1964年10月23日とは、女子バレーの“東洋の魔女”がソ連を倒して金メダルを獲得し、ボクシングでもバンタム級で桜井孝雄が現時点で日本唯一となる金メダルを獲得した日でもあります。日本人にとっては、悲喜交々となった日となりました。
実は柔道は東京五輪だけの実施種目であり、次回の1968年メキシコ五輪では外されてました。その後、欧州を中心に柔道の人気が上がって競技人口が増え、レベルも上昇。東京五輪から8年後の1972年ミュンヘン五輪で柔道は再び正式種目に復帰し、現在に至ってます。今考えると、東京五輪で日本が全階級制覇していたら、もしかしたら復活は厳しかったのかもしれません。なので、ヘーシンクが日本の全階級制覇を阻んだからだとも、言えなくも無いです。また、東京五輪の敗北を「体格とパワーで負けたのであって、技術で負けてない」と負け惜しみを日本の関係者が語ってましたが、この言い訳もミュンヘン五輪では通用しないことになります。
というのも、ミュンヘン五輪の日本の無差別級代表の篠巻政利は、身長185cm、体重125kgと、外国勢にも見劣りしない体格を有し、世界選手権もこの階級で2連覇してましたが、肝心の本番では予選で敗退。一方、ミュンヘン五輪で2階級制覇を果たしたヘーシンクの母国の後輩である“赤鬼”ウィリエム・ルスカは、身長190cm、体重110kgだったので、参加選手中でも決して大きい訳ではありませんでした(ちなみに、篠巻はルスカに2戦2勝でした)。「柔よく剛を制す」の基本理念を忘れた日本が五輪の無差別級を制覇するのは、その4年後の1976年モントリオール五輪の上村春樹(ちなみに、身長174cm、体重103kg)まで待たなければなりませんでした。奇しくも、上村を育てたのが、東京五輪でヘーシンクに涙を飲んだ神永でした。
東京五輪の翌年の世界選手権を制した後、ヘーシンクは柔道を引退。一時期、日本でプロレスラーに転向しますが、正直あまり大成したとは言えませんでした。その後、柔道の指導者に転身。更に、国際柔道連盟(IJF)の役員や国際オリンピック委員会(IOC)の委員を務めます。カラー柔道着の導入を提唱したのが、実はヘーシンクです。当初、日本はカラー柔道着は反対します。しかし、日本人が受け入れられやすい色として青を取り入れたのは、言うまでも無くヘーシンクが日本を熟知していたからに他ならないです。拡大一辺倒だった五輪も、新世紀に入ってからは縮小均衡の時代に変化します。テレビ映りを意識してイメージの向上を図る為にカラー化を率先して導入したのであれば、ヘーシンクは相当の先見の明の持ち主だと思います。
たしかに、ヘーシンク氏は日本にとって黒船のような存在でしたが、礼節の大切さや、改革の必要性を教えてくれるなど、その時々で柔道の母国である日本人に何かを問いかける大切な存在でもありました。
謹んでヘーシンク氏のご冥福を心よりお祈りいたします。
☆東京五輪・無差別級の決勝戦で神永昭夫を袈裟固めで一本勝ちして優勝
☆全日本プロレスに参戦してジャイアント馬場とタッグを組んだヘーシンク
1メートル98の巨体で「オランダの巨人」と称されたヘーシンク氏は、オランダ代表として東京五輪の柔道無差別に出場。決勝で日本の神永昭夫氏(故人)と対戦し、けさ固めで一本勝ちを収め、優勝した。柔道の母国・日本にとって、地元開催だった五輪での最重量級で外国人選手に金メダルを奪われたことは、当時大きな衝撃として受け止められた。
その後プロレスラーに転向し、73~78年まで全日本プロレスで活躍。引退後は国際柔道連盟(IJF)理事、国際オリンピック委員会(IOC)委員などを歴任した。現在国際試合で着用されている、青色の「カラー柔道着」を提唱したことでも知られる。97年10月にIJFから初の名誉十段を授与され、2003年にはIJFの柔道殿堂入りも果たした。
〔読売新聞 2010年8月28日の記事より〕
* * * * *
来月9日から、世界柔道選手権が競技発祥国である我が日本の首都・東京で開催されます。しかし、柔道界のビッグイベントの開催を前に、世界を代表する偉大な柔道家がこの世に別れを告げました。その人物とは、1964年東京五輪の柔道無差別級の金メダリストであるオランダのアントン・ヘーシンク氏です。
オランダのユトレヒトで生まれたヘーシンクは13歳で柔道を始めます。建設作業員だった20歳を過ぎた頃、ヘーシンクはある日本人指導者と出会い、師事を受けます。その人物とは『生涯無敗』を誇った柔道家で、欧州の柔道普及に尽力した名伯楽である道上伯という柔道家です。道上の指導を徹底的に受けてメキメキと上達し、更に気弱だったヘーシンクは人格的にも変貌を遂げます。また、当時としては先進的な筋力トレーニングを体力作りに用い、柔道だけでなく様々なスポーツをトレーニングに取り入れていたそうです。更に、ヘーシンクはオランダでの稽古に飽き足らず、来日して数年間、講道館や天理大学を中心に武者修行。その成果もあり、ヘーシンクはまず欧州の頂点に立ち無敵を誇りました。
その後、ヘーシンクは、当然の如く世界の頂点を目指します。だが、最初のうちは柔道の本家の日本人選手には中々勝てませんでした。しかし、1961年にパリで開催された世界選手権で、ヘーシンクは神永昭夫、古賀武、曽根康治の3人の日本の精鋭を続けて破り、外国人選手としては初となる大会制覇を成し遂げます。ちなみに、この当時の柔道の大会はまだ体重で区分けした階級制ではなく、無差別級のみの時代でした。つまり、この敗北は外国人に最強の称号を奪われたことを意味し、柔道の母国としては許容し難い屈辱でした。同時にヘーシンクの戴冠は、3年後に迫った1964年東京五輪で全階級制覇を至上命令とされた日本に対する“黒船来襲”でもありました。
そして、開幕した東京五輪。柔道が初めて五輪の正式種目となった東京五輪では、4階級を実施しました。天敵ヘーシンクは無差別級にエントリーします。それに対し、日本は猪熊功と神永の2人のどちらかをぶつけるかで悩みました。ちなみに、猪熊は過去に1度もヘーシンクとは対戦したことがありません。しかし、来日したヘーシンクを天理大学で指導した経験を持つ日本の松本安市監督は、「神永の方がヘーシンクに勝てる可能性が高い」と判断し、重量級には猪熊、神永は無差別級に出場させることを決定。自国で覇権奪還を信じて疑わない国民は神永がヘーシンクに復讐することに期待してました。しかし、ヘーシンクの実力を熟知していた松本監督は、誰をぶつけても勝てないことを悟っていたので、これは苦渋の決断でもありました。
柔道の母国の真髄を発揮した日本は、軽量級で中谷雄英、中量級で岡野功、重量級で猪熊が圧倒的な強さを見せて順当に優勝します。そして、最も重要な階級である無差別級が、柔道競技の最終日である1964年10月23日に実施されました。無差別級には9ヶ国から9人しかエントリーしておりませんでした。当時のルールは現在のトーナメント方式とは大幅に異なり、3人が3組ずつに分かれて予選リーグを戦い、各組1位の選手は準決勝に進出。各組2位の選手は敗者復活リーグに回り、そこで1位の選手だけが準決勝に進む形式でした。なんと、この予選リーグで神永はいきなり優勝候補のヘーシンクと対戦。6分間フルで戦いますが、神永は決勝に備えて必殺技の体落としを封印したこともあり、ヘーシンクが優勢勝ちして1位通過。しかし、2位となった神永は敗者復活リーグで2試合余分に戦うことを余儀なくされました。
その後、両者は順当に決勝に進出。五輪の為に新設された東京・北の丸の日本武道館には、15000人の満員の大観衆が固唾を呑んで2人の対決を見守りました。決勝は10分間で行われました。ヘーシンクは198cm、120kg。一方、神永は179cm、90kgだったので、体が2回りも違ったそうです。試合序盤は膠着状態になり、神永はヘーシンクの誘いには決して応じません。5分過ぎに、神永の一瞬の隙を衝いたヘーシンクは支え釣り込み足で倒して押さえ込みに入りますが、なんとか神永は逃れます。7分には逆に神永が左体落としで攻勢を掛け、ヘーシンクの体は傾くものの不発。そして、試合開始から8分過ぎ。神永が技を掛けにヘーシンクの懐に入ろうとしますが、逆にヘーシンクが待ち構えたように得意の寝技に持ち込み、その巨体で神永を押さえ込みます。神永は必死に抵抗するも逃れることが出来ず、ついに9分22秒、主審がヘーシンクの一本勝ちを宣告。同時に、日本のお家芸の“柔道”が“JUDO”に屈した瞬間でもあり、国民に計り知れない衝撃を与えました。
ところが、試合終了直後、日本武道館の大観衆は予想外の行動を目にします。柔道の発祥国の日本の選手を破った事に対し、オランダの関係者が狂喜乱舞。畳の上に駆け上がって母国の英雄に抱き付こうとしました。しかし、ヘーシンクは押さえ込みの体勢のまま右手を挙げ、同僚が畳に上がるのを制しました。そして、主審の「一本」の声を聞いた後、ゆっくりと立ち上がり、神永への礼を尽くして畳を降りました。この時のヘーシンクの行動は、対戦相手を敬い、「礼に始まり礼に終わる」という柔道精神を具現化した行為として、現在でも高く評価されてます。なお、この1964年10月23日とは、女子バレーの“東洋の魔女”がソ連を倒して金メダルを獲得し、ボクシングでもバンタム級で桜井孝雄が現時点で日本唯一となる金メダルを獲得した日でもあります。日本人にとっては、悲喜交々となった日となりました。
実は柔道は東京五輪だけの実施種目であり、次回の1968年メキシコ五輪では外されてました。その後、欧州を中心に柔道の人気が上がって競技人口が増え、レベルも上昇。東京五輪から8年後の1972年ミュンヘン五輪で柔道は再び正式種目に復帰し、現在に至ってます。今考えると、東京五輪で日本が全階級制覇していたら、もしかしたら復活は厳しかったのかもしれません。なので、ヘーシンクが日本の全階級制覇を阻んだからだとも、言えなくも無いです。また、東京五輪の敗北を「体格とパワーで負けたのであって、技術で負けてない」と負け惜しみを日本の関係者が語ってましたが、この言い訳もミュンヘン五輪では通用しないことになります。
というのも、ミュンヘン五輪の日本の無差別級代表の篠巻政利は、身長185cm、体重125kgと、外国勢にも見劣りしない体格を有し、世界選手権もこの階級で2連覇してましたが、肝心の本番では予選で敗退。一方、ミュンヘン五輪で2階級制覇を果たしたヘーシンクの母国の後輩である“赤鬼”ウィリエム・ルスカは、身長190cm、体重110kgだったので、参加選手中でも決して大きい訳ではありませんでした(ちなみに、篠巻はルスカに2戦2勝でした)。「柔よく剛を制す」の基本理念を忘れた日本が五輪の無差別級を制覇するのは、その4年後の1976年モントリオール五輪の上村春樹(ちなみに、身長174cm、体重103kg)まで待たなければなりませんでした。奇しくも、上村を育てたのが、東京五輪でヘーシンクに涙を飲んだ神永でした。
東京五輪の翌年の世界選手権を制した後、ヘーシンクは柔道を引退。一時期、日本でプロレスラーに転向しますが、正直あまり大成したとは言えませんでした。その後、柔道の指導者に転身。更に、国際柔道連盟(IJF)の役員や国際オリンピック委員会(IOC)の委員を務めます。カラー柔道着の導入を提唱したのが、実はヘーシンクです。当初、日本はカラー柔道着は反対します。しかし、日本人が受け入れられやすい色として青を取り入れたのは、言うまでも無くヘーシンクが日本を熟知していたからに他ならないです。拡大一辺倒だった五輪も、新世紀に入ってからは縮小均衡の時代に変化します。テレビ映りを意識してイメージの向上を図る為にカラー化を率先して導入したのであれば、ヘーシンクは相当の先見の明の持ち主だと思います。
たしかに、ヘーシンク氏は日本にとって黒船のような存在でしたが、礼節の大切さや、改革の必要性を教えてくれるなど、その時々で柔道の母国である日本人に何かを問いかける大切な存在でもありました。
謹んでヘーシンク氏のご冥福を心よりお祈りいたします。
☆東京五輪・無差別級の決勝戦で神永昭夫を袈裟固めで一本勝ちして優勝
☆全日本プロレスに参戦してジャイアント馬場とタッグを組んだヘーシンク
















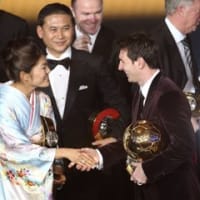


相手に何が何でも3連勝’などという記事を垂れ流してますが連敗中の下位チームと対戦した時に自分のチームがローテの谷間で相手はエースというマッチアップでも同じ事を言います。
どんな弱いチームでも たまには勝つこともありますし、ましてやエースと谷間の投手では順位は関係ないというのをマスゴミは忘れているようです。
その思考パターンで論ずると柔道発祥の地で
ある日本が金を取れないほうがおかしい的な論調がありましたけど、ヘーシンクが日本が最も欲しかった無差別級のタイトルを取ったおかげで五輪種目に復帰できたという事です。
だから韓国の独壇場だったテコンドーが公開競技から抜け出すのに苦労したのもテコンドーが韓国選手の独壇場になっていたというのも大きいでしょう。
考えてみればラグビー&サッカーはイングランド発祥の地ですが、彼らはロングボールを打ち込むだけでパスサッカーのブラジルやスペイン&オランダらの後塵を拝してます。
だから発祥の地というだけで自分達のスタイルを押し付けてしまえば、世界には広まらないという事でしょう。
ちなみにヘーシンクが主張したカラー柔道着ですが、本来なら赤を着る選手がいるのではないかと思いきや青になったのはヘーシンクのおかげだという事になっています。
ちなみに、野球とソフトの次に五輪競技から除外対象の噂がもっぱら高いテコンドーですが、
実は五輪とアジア大会では同一国から全階級に選手が出場が出来ないルールになってます。
(北京では男女合計8階級中、最大で4階級のみまで)
言うまでも無く、このルールを撤廃したら発祥国の韓国の寡占状態になるからです。
なので、“自主規制”することによって、世界に普及が遅れていることを隠す役割を担ってます。
実際に北京では、韓国は出場した4人全員が金メダルを獲ってます。
また、あのアフガニスタンの選手がメダルを獲っているように、このルールが無ければメダルが世界に拡散しないと思うので、
まさに「苦肉の策」ですね。
一方、柔道の場合は、ロンドンからは出場選手を世界ランキングによって選抜するほど、
世界各地に普及してレベルが上がってます。
それに、現在の日本が全階級でメダル獲得なんてまずあり得ないし、
むしろ史上初の全階級出場すら危ぶまれるほどです。
なので、テコンドーのような規制を必要としないほど、世界に広く普及してます。
なにせ、日本の柔道の競技人口は、フランスよりも少ないですから。
たしかに、柔道発祥国の日本人にとっては歯痒い状況なのかもしれませんが、
世界に広く普及した上で勝たなければ、タイトルの価値は低く思われますね。
サッカーにしても、母国イングランドはW杯に参加するどころか、
一時期FIFAも脱退していたほど、宗主国の意地もあって“光栄ある孤立”を貫いてました。
しかし、W杯に初参加した1950年のブラジル大会では格下の米国に番狂わせをされたり、
1953年には当時世界最強だったハンガリーに聖地ウェンブリーで惨敗を喫して、強い衝撃を受けたそうです。
なので、歴史を振り返っても、その競技を世界的に普及&発展させるには、
宗主国を地元で負かすことが一番なのは間違いないですね。
ヘーシンクに負けた日本の柔道もそうですが、負けたことによって、
自分達が井の中の蛙だということに気づきますから。