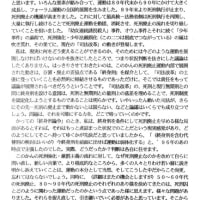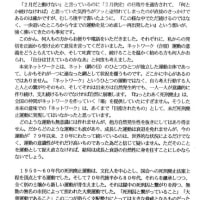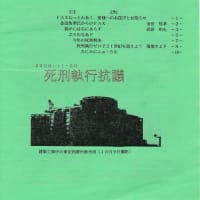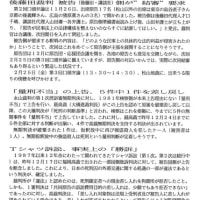永山則夫元支援者の武田和夫さんが、永山から追放された後、発行された『沈黙の声』という会報を冊子にまとめたものです。『沈黙の声』13号の記事を、以下に載せます。
『沈黙の声』第13号(85年8月15日発行)
「死刑と反省―更正しない凶悪犯への判決をめぐって」
6月17日、青森地裁(裁判長守屋克彦)は.昨年9月、旅館の女主八と通行人の二人を刺殺したとして強盗殺瓦と殺人罪に問われたS氏(57歳)に死刑判決を下した。全国紙(東京版)ではこの判決は、いずれも10数行~20数行で報道されたにすぎないのと対象的に地元紙の東奥日報は五段ヌキの見出しのもとに、この判決を大々的に報じた。
われわれは、これらの、新聞報道という極めて一面的な情報によって事実の一端を知るに卞ぎないが、それによるとS氏は昭33年岐阜県大垣市での強殺事件により無期(当時30歳前後)の判決をうけ、昭和51年仮出所、52年北海道函館市で「無銭宿泊」により逮捕され、58年9月.再び仮出所、59年9月9日、青森市の旅館で経営者の女性(当時61歳)から金を奪おうと包丁をつきつけて脅したが抵抗されたため刺殺、逃げる家族を追って外に出、通行中の男性(当時62歳)をも刺殺したという。

東奥日報は更に、このS氏が判決言い渡し後「控訴しません」と答えたこと、公判中も精神鑑定を自ら拒否したりで死刑を望む発言をくり返し、「カッとなれば徹底してやる」「遺族は恨んでいるだろうな。申し訳ないと言ってもどうにもならない」 「やる気でやっているんだから」などの冷酷な供述」や「もう、どうでもええわ」と捨てばちな発言」をくり返していたと報じている。東奥日報の、これらの記事の見出しは『「更生せず凶悪」』 『動揺の色も見せず』等々であり、インタビューをうける被害者遺族の大写しの写真の下には『「死刑は当然」2人の遺族 新たな怒りと悲しみ』とある。
公判は昨年11月8日の初公判から6ヵ月で結審というスピード審理であり、「控訴しません」というS氏に代わり弁護人が控訴期限の7月1日、仙台高故に控訴したが、S氏は2日、控訴の取り下げ書を提出、裁判所がこれを受理したため死刑が確定した。「若いころから窃盗などの犯行を重ねてきた」というS氏が、どの様な生い立ち、経緯から「犯罪」を行なうようになったのか、あるいは無期刑での仮出所後の社会での生活状況はどうであったのか等、具体的によく分らない点は多いが、少なくともいえる事は、それらの結果、S氏は「生きようとは思っていない」という事である。そしてそれは、もはや裁判で助かる見込がないと考える故の捨てばちな態度、というだけでは説明しつくされないものであることが、新聞報道の端々から感じられる。
S氏が旅館での強盗に失敗した揚句の殺人行為の後、行きずりの通行人を殺した時、「『バカにされている』と思い込みメッタ突きに」したという。この事件は二度目の仮出所の一年後であり、その前の「無銭宿泊」も最初の仮出所の翌年であった。また、今回の裁判で弁護士が精神鑑定を申請すると、S氏は精神鑑定をうけると「刑務所でバカにされる」と自分でそれを拒否している。 生きようと思っていない、それ以前に、この人は刑務所でもシャバでも生きてゆけない。
刑務所とは、たとえ死刑を回避されそこに戻っても、その様な自分をバカにする。弱肉強食の社会の縮図でしかない。シャバでは身柄引受人のいない仮出所中の無期受刑者として「保護鑑察所を転々」(東奥日報の表現)とする境遇を脱け出すことは出来ず、その生活はいずれも一年で破綻しているのである。 「裁く」立場から見れば、彼は一切の反省を拒否したふてぷてしい凶悪犯であり、被害者もこれでは全く浮かばれず、一生きていてもしょうがないIという事になろう。この様な無反省な死刑囚を「助け」る事に動揺を覚える「死刑廃止論者」も多いことと思う。
数年前、「朝日新聞」は「死刑存廃 高まる論議」という特集記事(記者 植竹伸太郎)のなかで、死刑をのぞむ被告を「改しゅんの情明らか」とのべたてたことがある。してみると。同じ死刑を求めても、このS氏のような捨てばちな態度ではなく、裁判所に対し神妙な態度でないと「改しゅんの情」ありとはされず、結局裁判所に対する態度如何、という事なのだろう。
ところで、われわれのいう〈反省〉はこれとどう区別されるべきであろうか。 裁判所の死刑判決に従順に従うことが本当の反省ではないのと同様、一切の反省の言葉もなくことさら死刑を求める言動をくり返すことが、本当の無反省ということでもない。
まず、生きようとは思わない状態では、〈反省〉ということも元々ありえない。
生きようとする中ではじめて、自らのそれまでの〈生〉が問い直され、以降の生き方につながる。
現在の反省が可能となる《反省》とは、ある時点で完了する行為のことではなく、その生涯をかけて担っていくものである。
「命で償う」という考え方は、個人が専制的な支配者の所有物であった時代、個人の生が、その人自身に属さず支配者の専横の手段であり「モノ」であった時代の 「生命」観の名残りに、ブルジョア社会の「賠償」の観念が結合したものである。この「賠償」の考え方には、「反省」の度合いといった発想が付随し、慰籍の量といった形で裁判に反映する。
然し真人民が望むべきは、モノとしての「命」や数量化された反省の証しではなく人間そのものでなければならない。
そしてそれは、相互の新たな関係性として得られるものである。
だからこそわれわれは、死刑囚の仲間を〈生〉かそうとするのである。 東奥日報は、殺された被害者の遺族へのインタビューを大うつしの写真とともに掲載し、「死刑は当然ごと語らせている。
「犯人がいくら死刑になっても、おばの命は戻らない、当然の判決とはいっても、その意味で複雑な心境だ」 「死刑は当然だ。しかし、以前にも殺人で無期懲役を受けた人間を仮出所させたことが、いまだに納得できない。もし、事前に何らかの手立てがあれぱ、叔父は殺されずにすんだと思うと…」
ではどうすればよかったろうか。S氏が、刑務所でもシャバでも、自分を生きれなくするもの、自分を「バカにする」人間達の背後に濳んでいるものの正体を知ることが出来ぬかぎり、彼は社会とそこでの自分に絶望し、あるいはそれが絶望という状態であるという事すら分らず、それに身をまかせてただ衝動的に「生」きるしかないであろう、「死刑は当然」という前に、この様な人が、何の救いもなく放置されたならば「殺人をおかしても当然」ということがまず考えられなくてはならないだろう。
われわれの「死刑」との斗いは、たんに死刑という制度だけとの斗いではなく、このS氏のような仲間達が、いまの社会の生存条件の下で肉体と精神を収奪されつくした果てに様々な形で「殺」されていく、その究極的な在り方としての「死刑」、それとの斗いである。遺族は「死刑は当然」という。しかしそれは、結局のところ、一昨年に横浜で「中学生」らに虐殺された「浮浪者」たちの様な形で殺されるならばよく、それは「当然として黙殺する」という事につながるのだと思う。その様にではなく、S氏はこの様な形で、他者を殺し、自らを殺すという形で「殺」されるのだ。
S氏は〈何〉に殺されたのか。そして被害者は、本当は〈何〉に殺されたのか。―それは決してS氏を含む「犯罪」者とも、被害者とも外在的な、社会制度や権力一般にのみ求められるものではない。然しながら今の社会で疎外されきったS氏が、自分が人間であると感じ、それによってはじめて真の罪の自覚を生きる為には、社会批判は不可欠の前提である。そしてそれは「反省」の端緒となるものだ。そして、自己の罪の自覚は。いまの社会とその中での自己史をとらえ返す中で、真剣な自己変革と、その自己を規定する外界の変革への実践をうながすだろう。
そしてその実践の中でこそ、自己と世界への正しい認識が深まり、それに応じて、更に己れをむなしくして仲間全体のために〈生〉き斗おうとする意志を強めるだろう。それが真の生きた反省であって、だから「反省」や 「認識」のみが切り離され、固定化されて評価の対象となること自体が、ひとつの「疎外」された存り方でしかないのである。
われわれが、死刑を課せられた仲間を生かそうとするのは、こうした意味においてであり、われわれが彼らに、この様な真の反省を要求できるのは、われわれ白身が、S氏達を殺し、被害者を殺すものと自己との関係を、コトバのつみ重ねの上だけでなく、自分自身が真剣に〈生〉きようとする中での具体的な反省のなかで、それをふまえた斗いの実践のつみ重ねのなかで、より主体的に理解しえたその度合いに応じてである。
そしてそれこそが、被害者遺族にも、「死刑は当然」という怒りをどこへ向けるべきかをはっきりと示すことが出来、加害者か被害者かの堂々めぐりの中でなく、生きた弁証法のなかで、即ち真に人間を生かす斗いのなかで、両者は究極的には連帯していけるという、真の解決への途を切り拓くことになるのである。そして、人間社会の疎外が物質化されたものとしての「犯罪」の、この様な解決をつうじて、われわれは未来の社会を形づくる新たな人間観をわがものとすることができるのである。
「死刑」法廷への更なる結集を!!
昨年11一月、強行されんとし、事件自体に疑問ありとして新しく着任した弁護団の訴えにより延期された晴山氏への弁論が、さる7月4日行なわれたが、この期日は、まだ補充書追加の準備中であるにもかかわらず、その前に設定されたものであり、あくまで早期形式審理という基本姿勢を最高裁が捨てていない事を示すものである。
しかもこの弁論において検察側は、無実を訴えている事件に対して「被害者の感情」を云々するという倒錯しきった意見書陳述を平然と行なっているのである。我々は、今迄衆人の目の届かぬ密室で仲間達を殺してきたのであろうこの様な不条理極まる裁判が、人民監視の中でもくり返されるなら決して黙過しないであろう。
一昨年の永山裁判最高裁差し戻し以降、個々の 一つ一つの死刑裁判が、死刑存廃をめぐる全状況を反映させるものとして、存在している。
司法権力の基本姿勢は、問題を個々の裁判の個別利害に分断し、「慎重」を期して人民勢力とのまさつを極力避けつつ可能な限りの強権をふるい「死刑制度」だけは維持せんとするにある。これに対するわれわれの姿勢は、かかる状況を正しくふまえ、個々の裁判を「死刑」総体との斗いと結びつけて、斗っていくことでなくてはならない。
わずか数名の傍聴に対し40名の公安・警備を動員しなければ死刑判決を下せないという最高裁の現状が何を意味するのかを、正確に理解せよ!!
(抜粋以上)