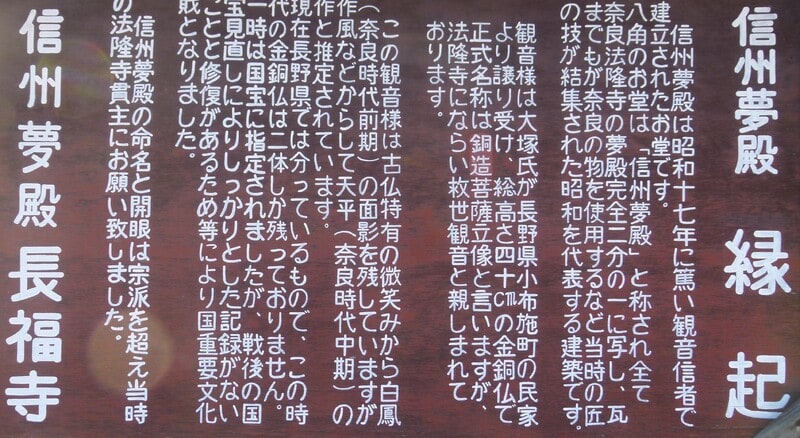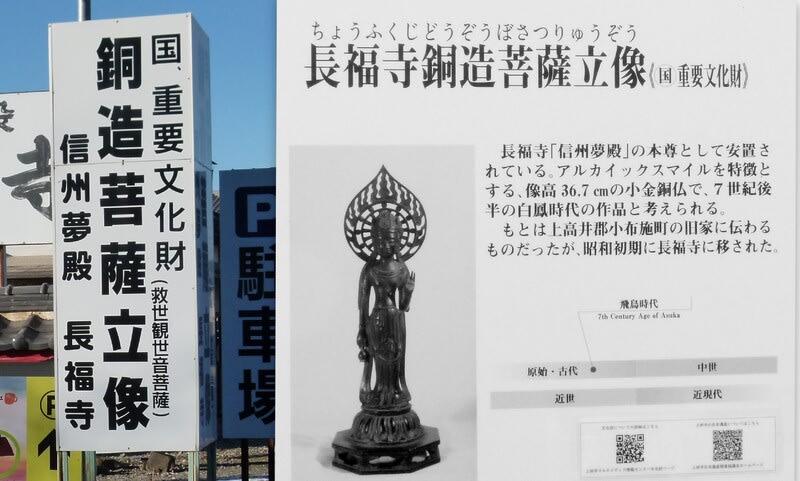信州上田の・・・六文銭の写真帳
今日のプチドライブ・・・上田市丸子から依田川の谷へ、佐久平の立科町へ、国道142号線を佐久市に向かい臼田あたり。龍岡城五稜郭址、新海三社神社の三重塔、貞祥寺の三重塔を訪ねる予定。新海三社神社の三重塔・・・佐久市田口宮代。1515年建造、国重要文化財。
神社に三重塔? 明治以前までは神仏混交、新海三社神社の別当・・・新海山上宮本願院神宮密寺の伽藍であった。明治の廃仏毀釈のころ、神社の宝庫という理屈を並べて解体を免れたという。氏子の中に知恵者がいたのだ。それを許した明治政府側の関係者も知ってて知らぬ顔をしたんだろうな。



日本の近世以前の三重塔は102(うち国宝が13)。信州には10(うち国宝が2、重要文化財が3)あります。
残存の理由は戦乱が少なかったからです・・・信州にお出での際はぜひ見に来てください。
※撮影日は1月28日。
※コメント欄オープンにしています。・URL無記入のコメントは削除します。