ゴンゾのぼくらのの制作プロデューサー、永井氏から、ある日次のような申し送りがありました。
「森田さん、血は黒く塗ってください」
何の話か分からず、そのあと1、2時間議論になったのですが、テレビアニメーションでは血を見せてはいけないというルールが放送局にあるらしいのです。映画のテレビ放映やドラマの放送では、血ぐらいよく出てくると思われるのですが、アニメーションの番組枠は「子供向けの枠」に入るので、ドラマや映画より基準が厳しいそうです。作品中にどれだけ大人向けのテイストが含まれていてもあくまで「子供向け」扱いだそうです。
なるほど、それは分かるとして、では血を黒く塗るってどういうことしょう?
「同じ赤でも黒っぽく塗っておけば、視聴者から『子供に血を見せるとは何事か』と苦情が来ても、『赤くないから血を見せた(効果を狙った)ことにはならない』と反論できる」
と言うのが永井さんの説明でした。
とても難しい理屈です。しかし、私がどう思おうと、永井さんの言うことは、アニメ界では常識でした。永井さんは、その常識を私に伝えたに過ぎません。
話は戻りますが、つまりこういうことです。番組の内容に問題があった時、視聴者から電話などで苦情が寄せられる。局は、お客様である視聴者に責任ある対応をしなければならない。苦情を受け入れて番組を改めるか、きちんと反論し視聴者の理解を得るか、そのどちらかしかないわけです。そのせめぎ合いが煮詰まっていった結果、
「この黒い液体は血には見えない」
という、反論がまかり通るようになった、と。これはよく理解できる話です。
作る側も、血が流れるシーンは暗い場所を設定して、影色の解釈で血を黒く描く。作り手と局にとって都合のいい落としどころな訳ですね。
「ぼくらの」をテレビアニメーションとして作っているつもりの私は、テレビ局とその視聴者を信じています。この、とても神経質な議論にも、しっかりと内実があるはずだと考えるのです。
私なりに出した結論はこうです。
「血を黒く塗る」という、対策の結論だけに目を向けても、テレビで血を描いてはいけない本当の理由は分からない。それを知る方法は、血を描いて最初に問題になった作品を見ること。テレビ局の自主規制が視聴者の苦情に始まるのが普通ならば、「赤い血」が問題になった、その最初の番組があるはず。「血を描いてはいけない理由」の秘密は、その作品の中に見つかるはず。
たとえば、テレビ放送では「一秒間に三回以上の光の明滅は禁止」というルールがあります。こういうルールを突きつけられると、なんで一秒間に三回がダメで二回ならいいのか?などと気になりますが、そんなことになんら意味はありません。また、光の明滅による芸術性を解き、表現の自由を主張してみたところでそれはおかど違い。そのことが私に分かるのは、この光の明滅禁止ルールが登場した時、すでに私はアニメーターになっており、このルールが作られる切っ掛けになった事件もリアルタイムで知っているし、問題視されたその作品も見ていました。
その事件とは、テレビアニメ「ポケットモンスター」を見た子供が全国で多数倒れるという事件で、原因は光の明滅による演出効果でした。この時、朝日新聞がこの事件の背景を「ハイテクの落とし穴」と題して論評していることに状況の混乱ぶりがよく表れていました。ストロボ効果のどこがハイテクでしょうか? 古きフィルム時代からある技法で、最近のデジタル技術とはなんら関係ありません。むしろ正しい背景は「テレビアニメーションはスケジュールや予算が少なく、微妙な色の効果や、物語性による表現を発揮できない。結果的に、安上がりで、刺激の強い表現が増え、クライマックスにおいてのストロボ効果の多様のような事態を招いた」ということになります。つまり、粗雑な表現が招いた事件だということです。
話を戻しますが、光の明滅禁止ルールは番組を見た子供たちが倒れないようにすることのみが目的という、きわめて分かりやすい話です。そして事件の発端は、安上がりで粗悪な作品作りが原因、というのも、参考になります。このようなことは、事件をリアルタイムで見聞きしていれば、簡単に分かる。先の血の件も、このようにすっきり整理して考えたいと私は思います。
しかし、血を描いてはいけないルールを生む切っ掛けになった作品がなんなのか、そこまでは永井さんも私も勉強していません。周囲に尋ねても誰も知らないのです。忙しくてこれからそれを調べる暇もないし。ですから、仕方なく、その問題になった作品を想像してみるのですが、ポケモン事件を参考に、「安易な強い刺激を求めた映像」という点で、この血の問題は想像がつきます。おそらく、血の表現の問題とは、「赤い血の刺激」と、「血が流れるどぎついバイオレンス」が問題になるのだろうと思うのです。たとえばナイフでザクっと人を刺したりして、その刺し口がショッキングで、ドキッとさせられるとか、そんなことだろうなと。ホラー映画なんかだと、針で目をひと突きにしたりするじゃないですか。あの、目を背けたくなるような刺激、ショックが問題なのでしょう。
それにしても、、テレビの自主規制がこれほど分かりにくく、難しいとはお思いませんでした。今まで何にも知らなかったな、と反省しています。
(つづく)
「森田さん、血は黒く塗ってください」
何の話か分からず、そのあと1、2時間議論になったのですが、テレビアニメーションでは血を見せてはいけないというルールが放送局にあるらしいのです。映画のテレビ放映やドラマの放送では、血ぐらいよく出てくると思われるのですが、アニメーションの番組枠は「子供向けの枠」に入るので、ドラマや映画より基準が厳しいそうです。作品中にどれだけ大人向けのテイストが含まれていてもあくまで「子供向け」扱いだそうです。
なるほど、それは分かるとして、では血を黒く塗るってどういうことしょう?
「同じ赤でも黒っぽく塗っておけば、視聴者から『子供に血を見せるとは何事か』と苦情が来ても、『赤くないから血を見せた(効果を狙った)ことにはならない』と反論できる」
と言うのが永井さんの説明でした。
とても難しい理屈です。しかし、私がどう思おうと、永井さんの言うことは、アニメ界では常識でした。永井さんは、その常識を私に伝えたに過ぎません。
話は戻りますが、つまりこういうことです。番組の内容に問題があった時、視聴者から電話などで苦情が寄せられる。局は、お客様である視聴者に責任ある対応をしなければならない。苦情を受け入れて番組を改めるか、きちんと反論し視聴者の理解を得るか、そのどちらかしかないわけです。そのせめぎ合いが煮詰まっていった結果、
「この黒い液体は血には見えない」
という、反論がまかり通るようになった、と。これはよく理解できる話です。
作る側も、血が流れるシーンは暗い場所を設定して、影色の解釈で血を黒く描く。作り手と局にとって都合のいい落としどころな訳ですね。
「ぼくらの」をテレビアニメーションとして作っているつもりの私は、テレビ局とその視聴者を信じています。この、とても神経質な議論にも、しっかりと内実があるはずだと考えるのです。
私なりに出した結論はこうです。
「血を黒く塗る」という、対策の結論だけに目を向けても、テレビで血を描いてはいけない本当の理由は分からない。それを知る方法は、血を描いて最初に問題になった作品を見ること。テレビ局の自主規制が視聴者の苦情に始まるのが普通ならば、「赤い血」が問題になった、その最初の番組があるはず。「血を描いてはいけない理由」の秘密は、その作品の中に見つかるはず。
たとえば、テレビ放送では「一秒間に三回以上の光の明滅は禁止」というルールがあります。こういうルールを突きつけられると、なんで一秒間に三回がダメで二回ならいいのか?などと気になりますが、そんなことになんら意味はありません。また、光の明滅による芸術性を解き、表現の自由を主張してみたところでそれはおかど違い。そのことが私に分かるのは、この光の明滅禁止ルールが登場した時、すでに私はアニメーターになっており、このルールが作られる切っ掛けになった事件もリアルタイムで知っているし、問題視されたその作品も見ていました。
その事件とは、テレビアニメ「ポケットモンスター」を見た子供が全国で多数倒れるという事件で、原因は光の明滅による演出効果でした。この時、朝日新聞がこの事件の背景を「ハイテクの落とし穴」と題して論評していることに状況の混乱ぶりがよく表れていました。ストロボ効果のどこがハイテクでしょうか? 古きフィルム時代からある技法で、最近のデジタル技術とはなんら関係ありません。むしろ正しい背景は「テレビアニメーションはスケジュールや予算が少なく、微妙な色の効果や、物語性による表現を発揮できない。結果的に、安上がりで、刺激の強い表現が増え、クライマックスにおいてのストロボ効果の多様のような事態を招いた」ということになります。つまり、粗雑な表現が招いた事件だということです。
話を戻しますが、光の明滅禁止ルールは番組を見た子供たちが倒れないようにすることのみが目的という、きわめて分かりやすい話です。そして事件の発端は、安上がりで粗悪な作品作りが原因、というのも、参考になります。このようなことは、事件をリアルタイムで見聞きしていれば、簡単に分かる。先の血の件も、このようにすっきり整理して考えたいと私は思います。
しかし、血を描いてはいけないルールを生む切っ掛けになった作品がなんなのか、そこまでは永井さんも私も勉強していません。周囲に尋ねても誰も知らないのです。忙しくてこれからそれを調べる暇もないし。ですから、仕方なく、その問題になった作品を想像してみるのですが、ポケモン事件を参考に、「安易な強い刺激を求めた映像」という点で、この血の問題は想像がつきます。おそらく、血の表現の問題とは、「赤い血の刺激」と、「血が流れるどぎついバイオレンス」が問題になるのだろうと思うのです。たとえばナイフでザクっと人を刺したりして、その刺し口がショッキングで、ドキッとさせられるとか、そんなことだろうなと。ホラー映画なんかだと、針で目をひと突きにしたりするじゃないですか。あの、目を背けたくなるような刺激、ショックが問題なのでしょう。
それにしても、、テレビの自主規制がこれほど分かりにくく、難しいとはお思いませんでした。今まで何にも知らなかったな、と反省しています。
(つづく)










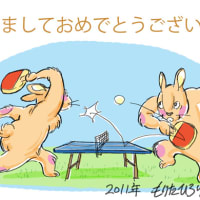
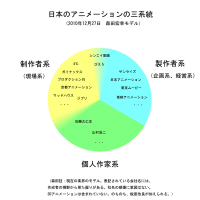


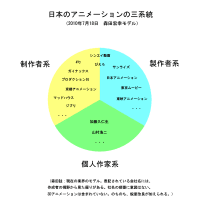










知らなくて当然だと思いますよ、局の自主規制。
言葉や表現に関して、門外不出の規制マニュアルも、
各局独自に存在しますが、
門外不出だから内部にいないと判らない。
自分がその存在を知ったのは、
以前、ゲームを製作している時でした。
ゲームシナリオに取り掛かった時に、
当時のプロデューサーから「これに目を通して、表現や台詞で書いちゃいけないものを把握して下さい」と言って渡されたのが、
もう角も擦れて長年使い込まれたような、
A4コピー用紙にして3~4cmはあろうかと言う、
分厚いマニュアル。
みると、なるほど現在では放送出来ない言葉や表現が、
なぜそうなったのかの経緯とともに、
細かに指定してありました。
そして件のプロデューサーは、
「コレの存在は、他言無用で」とも付け加えられました。
マスに向けて発表される作品には、
どうしてもついて回る問題ですが、
しかしその元を知りたいと思う気持ちも凄く判ります。
ただ、今回の血の表現についての代行策の余りの馬鹿馬鹿しさには、
呆れる他は無いんですけどね。
(永井氏のせいばかりではないのは理解してます)
(ん~、でも板野一郎作監の時は赤かったかな・・?)
やはり、ポケモンの事件がアニメの自主規制のハードル
を全体的に上げてしまったということは言えるのでしょうね。
私も仕事では、昔、アクションゲームに関わったときに
血の色について面白い経験をしたことがあります。
刀で斬りあうゲームなのですが、国内向けでは血は赤でも
問題なし、ということだったのですが、国外向けでは
なんと、「白」ということでした。
プログラムで国内バージョンと国外バージョンにディップ
スイッチで切り替えられるという仕様でした。
子供番組に対する規制ではアメリカ等の方が厳しいそう
ですので、アニメの場合は合作などの影響でそうなって
しまったのかもしれないですね。
海外市場に展開するとなると色を塗りなおすのも手間
でしょうし、はじめから黒く塗っておこうということで
一般的になってしまったのかもしれません。
ただ、まあ血の色はともかく、ボンズの鋼の錬金術師の
7話など、よくこれでチェック通ったなぁ・・とある意味
感心させられる作品もあるので、うまくすき間を見つけて表現の幅を広げていくしかないのでしょうね。
制作者、テレビ局、表現規制を求める視聴者、表現規制に反対する視聴者が対等に意見を交換する場がほとんど無いのが問題ではないでしょうか。
私もシナリオライターをやってるもので、自主規制についてはそれなりにわかっているつもりです。
経験上、そうしたものはかなりのていど、外せると私は思います。ただし、そのための労力たるや半端ではないし(一時間や二時間の議論では済まない)、そんな手間など、実作者の仕事の範疇ではないとも思います。
けっきょく、現場の兼ね合いで決めていくしかないのですが、森田監督は実力のある方なので、なんと申しますか、理由を見つけて諦める、という姿勢は取って欲しくないな、なんてことは思ったります。ディレクターとプロデューサーの間にもうひとつ、なにか役職を挟めば面白そうだな、なんて考えたりしていますが……。
不躾な意見で失礼いたしました。陰ながら応援しております。
コエムシの声にはボイスチェンジャーをつけた方がいいんじゃないかなーと思ってましたが、最近、慣れてきました。うーん、面白いですね。
今回の場合は放送局の問題なのか、「ぼくらの」が現実的な世界観と中学生が題材だからそうなのか・・・。
例えば先日放送された「クレイモア」というアニメでは普通に血がドバドバ出てこのご時世に女性の首がスパーンと切断されてましたけどね。生首を抱きしめて泣く少女の描写とかありましたし。
非常に真っ当に考えるところが森田さんらしいというか、アニメ版ぼくらのらしいですね。
表現の幅だなんだといっても、例えば森田さんも参加された「THE八犬伝新章4話」などと比べて、
規制されている以外の部分でまだ広げられていない表現の部分がいくらでもあるわけで、
なんでもかんでも規制を失くせばいいという話ではないしょう。
僕はいつも、子どもが見れるような時間帯に放送している映画やドラマで、銃撃戦・血の描写・性描写があるのに、アニメはその辺規制されまくってるのが不思議だったんですが…なるほど。アニメはあくまでも「子ども向け扱い」だったんですね。
(MBSさんは夕方でも、際どい映像描写が多いですけどね…)
しかし、WOWOWの有料放送枠は、R指定がついたりと規制が少ないようで…あれは大人向け扱いを受けているんでしょうね。
映画のキルビルは日本版は真っ赤な血もアメリカ版は黒い血でしたね。
血の描写もあり時代劇ということもあってアニメのどろろはあえてモノクロで作られたんでしたっけ?(うろおぼえ)
実写であれアニメであれ、人間を描く中で傷付いた者が赤い血を流すというあたりまえのことを描写出来ないのは釈然としない。
けど、ダメなものはダメ!というハードルは現にあるわけで。
表現者としては放送コードまみれの中でいかに「作品」をつくりあげていくか、その手腕が問われているんでしょうね。
>あくまで「子供向け」扱いだそうです。
いくらアニメを見る大人が増えたと言っても視聴者全体からすると少数派なのですよね。
また、子供向けか大人向けかよく分からない作品がアニメには多いというのも問題かと思います。
現実離れした作品で、なぜ血の色だけは現実的な赤じゃないといけないの?
大人向けテイストがほしいなら、もっとセリフや状況を練りこむべき。
それこそ、「赤い血見せりゃリアルじゃね?」なんて考えてる時点で子供向け決定!