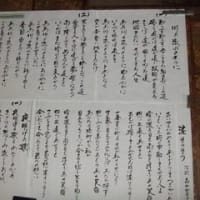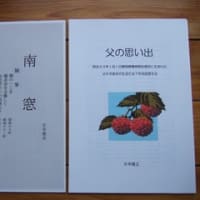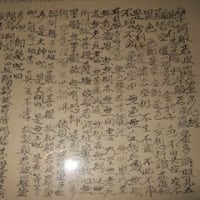今年は徳川家康が薨去して400年にあたる。そこで家康のことを調べると、彼が戦乱ののなか江戸幕府を創るにあたって、2人のブレーンを招き国家建設にあたった。その2人が「金地院崇伝」と「林羅山」で約250年続いた江戸幕府の礎を創った人物のようだ。先日は「金地院崇伝」のことを記したので今回は「林羅山」について記したい。その前に徳川家康とこの2人の年齢を調べた。 徳川家康(1543年~1616年) 林羅山(1583年~1657年)金地院祟伝(1569年~1633年)であった。家康がこの2人を招いたのは、関ヶ原の戦いに勝利した後の1606年頃であり、その年齢は家康63歳、羅山23歳、崇伝37歳、因みに南光坊天海は70歳であった。天海については別途記したい。
林羅山は京都四条新町で生れる。幼少のころから、その秀才は評判であったようだ。建仁寺で仏教を学ぶため入門するが僧籍には入らず家に戻っている。その後朱子学にのめりこみ、慶長9年(1604年)に儒学者藤原惺窩(1561~1916)に出会う。惺窩は豊臣秀吉や徳川家康にも儒学を講じており、家康からは士官を要請されていたがこれを辞退し、門弟の林羅山を推挙している。慶長12年(1607)家康の命により僧形となり道春と称して仕える。この年江戸に赴き将軍徳川秀忠に講書を行っている。
彼は、慶長19年(1614)大阪の役に際して方広寺の梵鐘に刻んだ銘文中の「国家安康」「君臣豊楽」の文言の件で、これは徳川家を呪詛しるものとして問題視する意見書を献じた。更に「右僕射源朝臣家康」を「家康を射る」ものとこじつける見解を表明している。その後寛永元年(1624)徳川家光の侍講となり、さらに幕府政治に深く関与していく。その活躍は「寛永諸家図伝」「本朝通鑑」などの伝記・歴史の編纂・校訂「武家諸法度」「諸士法度」などの撰定、外交文書の起草など多岐にわたっている。将軍家光から江戸上野忍岡に土地を与えられ、ここに私塾「学門所』を建てている。ここからは多くの門人が輩出し、後世の昌平坂学門所の基礎となっている。
彼は徳川家の家康・秀忠・家光・家綱の4代の将軍に仕えた羅山は、江戸幕府の土台作りに大きく関わり様々な制度、儀礼などのルールを定めている。学問上では儒学・神道以外はすべて廃し、儒学の官学化に貢献した。なお、林家当代の主は大学頭と称したのは羅山の孫からで以後林家は代々幕府の教学の責任者としての役割を担っていった。 このことから家康は、最初は金地院崇伝を使い、思い切った幕府の改革を行い、それを引き継いだ林羅山によって、盤石な体制を作ったことが分る。なお天海は家康より7歳上であり身近な相談相手と云ったところか?