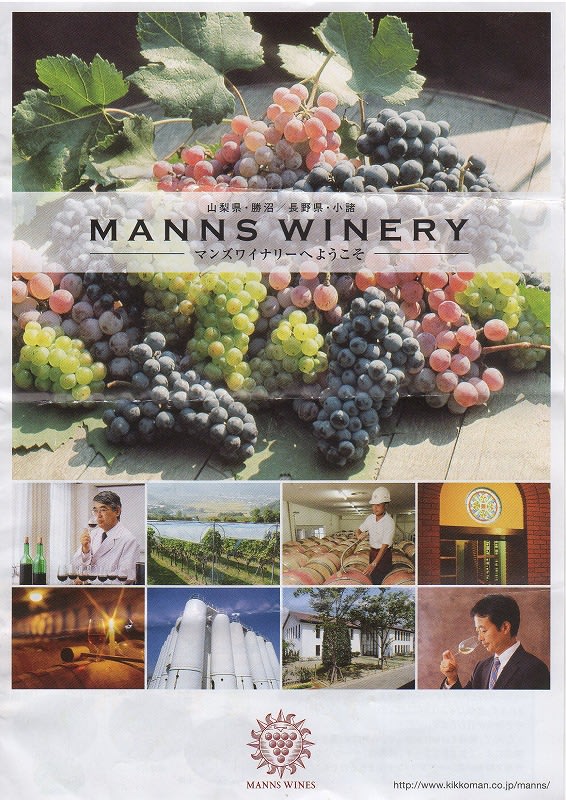「絶景の宿」がキャッチフレーズの犬吠埼ホテルに宿泊しました。ホテルは2人一室、2組で宿泊しましたが、オーシャンビューが出来、
和室の二部屋はゆったりとしていました。男性用露天風呂から太平洋と犬吠埼の灯台が見えました

このホテル、玄関横でペンギンが歓迎と見送りをしてくれます。近くの犬吠埼マリンパークから出張してくるらしい。

ここからは、日の出をよく見ることが出来ます。この日の日の出の時間は午前4時39分。ホテルの庭から撮影しました。
しかし、晴れてはいたのですが水平線には少し雲がかかっていました。
どこから日の出があるかを調べておいて、海岸に出て犬吠埼の灯台を入れて撮ればもっと良い写真が撮れたと思います。
犬吠埼は、場所によっては180度以上の展望があり、地球が丸く見えると言われています。ホテルの屋上も午前4時から開放されていました。

夕食はレストランの個室で取りました。
手前から、白魚と青菜のおひたし。江戸前にぎり寿司。お造り三種盛り(刺身)、右 金目鯛幽庵焼き、鶏肉と野菜、左 鰯のつみれ鍋

小芋、厚揚げ、椎茸、蓮根、茄子の煮物

この日のハイライト、伊勢エビの鬼殻焼き

同じく、アワビのバター焼き

茶碗蒸し

桜エビ御飯、アサリの味噌汁、香の物

デザートは、西瓜とケーキ
従業員はとても親切で雰囲気はとても良く、料理は美味しく食べられて、とても満足のいくホテルでした。