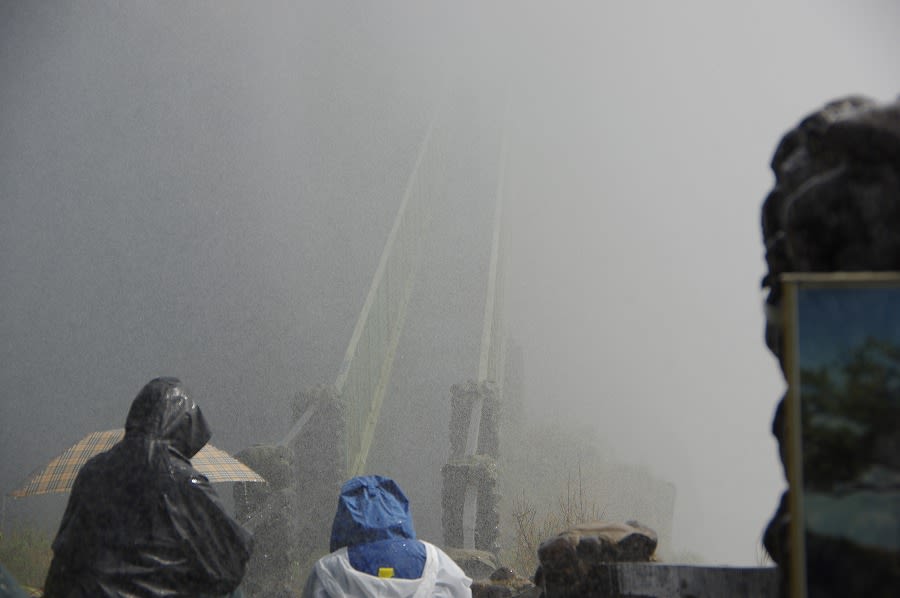私が銚子市外川を今回、訪れることになったのは、時々参加するフォトスクールの撮影会が5月中旬に外川で行われることを知り、
それならば、すぐ近くの犬吠埼で一泊し、自分だけで、ゆっくりとカメラを持って訪ねて見ようと思ったためです。

外川駅は、銚子電鉄で銚子駅から6kmほど。犬吠駅は隣の駅。外川は、もともとは銚子港として江戸の昔から栄えていました。
戦後しばらくしてから、銚子港は銚子市街の方が大きくなりました。
外川は今も漁港として残り、碁盤の目のような街並と、急な坂が独特な雰囲気を醸し出しています。

ところが、外川駅に着いてみると、ここが「澪つくし」のロケ地であったことが、思わぬ出来事となりました。
「澪つくし」は1985年(昭和60年)4月から10月に放映されたNHKの朝の連続テレビ小説。
大正末期から終戦後の昭和にかけての激動の時代、千葉・銚子の醤油醸造家を舞台に、旧家の娘・かをる(沢口靖子)と
網元の長男・惣吉(川野太郎)との純愛を軸に描かれたドラマ。フレッシュなコンビが大人気になりました。
今も「科捜研の女」などで活躍する、若き日の沢口靖子の美貌と可愛らしさは圧倒的です。
脚本:ジェームス三木。音楽:池辺晋一郎。他に桜田淳子、津川雅彦、加賀まりこ等が出演。
「澪つくし」の期間平均視聴率は44.3%、番組最高視聴率 55.3% で、それ以前に放映された「おしん」や「おはなはん」など、
には及びませんが、朝の連続テレビ小説で、それ以降の30年間に、この視聴率を超えたものはありません。
ここ10年ほど、どの番組も期間平均視聴率は、10%後半から20%前半となっています。
「澪つくし」が大ヒット作品となり、純愛ブームが巻き起こって、いかに国民が熱狂したかが、よく分かります。

駅には、撮影当時に使われていた電車がありました。
実は、この「澪つくし」の動画が、今日現在(2014年5月11日)、Yutube にスペシャル版が載っています。全5回で1回あたり1時間15分。
2013年の9月のアッフロード。
私は、このドラマを見た記憶があるのですが、ストーリーは殆ど記憶にありませんでした。銚子市・外川から帰った翌日にYutubeにあることを
知り、見始めたら、強く惹きつけられて、一気に全部を見てしまいました。
ちょっと恥ずかしいのですが、あまりの感動に涙を流してしまったことが何度もありました。
ただ、キャストが良かったのは言うまでもありませんが、その素晴らしさはジェームス三木の脚本によるところが多いと言えるでしょう。
番組の冒頭は、次のような語りから始まります。
「 恋は危険な訪問者である。人を傷つけ、鎖につなぎ、熱い涙を流させる。時には甘い顔をして 油断させ、突然、不幸の海に突き落とす。
しかし人は誰でも恋を待っている。恋に巡り会わない人生は、むなしく寂しい。」
この語りは初めは、ちょっと番組には不釣り合いの気がしたのですが、見終わった後は、「言い得て妙」と思いました。

外川の駅近く、外川の本通に面して「外川ミニ郷土資料館」がありました。「中に入ったら、声をかけて下さい」と書いてあったので
「お邪魔します」と言いました。そうしたら、女性の方が出てきて、外川の街の詳しい説明をしてくれました。
家康の利根川の東遷で銚子が河口になってから、岩盤の多い外川の周辺の海が絶好の漁場となった。
漁師は紀州(今の和歌山県など)から、すべて渡ってきて、漁で潤う豊かな街となった。
一方、醤油は関東にはなく、銚子の醤油も紀州の人が始めた。そして、高級品である醤油を将軍家に納めることになった。
その後は、日本軍の基地や御用邸などが出来て、銚子は大いに賑わう街となった。
しかし、太平洋戦争で犬吠埼の灯台を目指してアメリカの爆撃機がたびたび来襲、大空襲により銚子市街は焼け野原になってしまった。
こうした、漁港や醤油工場など、銚子市の時代背景を知ると、「澪つくし」のドラマが身近になります。
もちろん、かをるの夫となる網元の惣吉の家も、外川の地にあるという設定になっています。
実際に目にした君ヶ浜や犬吠埼の灯台、外川駅、外川の街並がドラマに出てくるので、さらに身近になりました。
また、醤油製造元の山兆の社長、坂東久兵衛(津川雅彦)の二号さんの娘である、古川かをるは、番組はじめでは銚子高等女学校の4年生。
入学が難しいため地元では超エリート。制服の袴の下に着いた白の三本線は、当時あこがれの的だったとのことです。

「澪つくし」についても、詳しく説明してくれました。スタッフが1年ほども外川に滞在していたそうです。
ロケの時のスナップ写真や解説本もあり、見せてもらいました。
「せつなく、かなしく・・・・・ 銚子を舞台に描く、鮮烈な愛のドラマ」と左側に書かれてあるのも、解説本にピッタリ。

解説本の中身、写真に写しただけで、この時はまだ、動画を見ていなかったので、本は読まなかったけれど
今なら、少々時間がかかっても、熟読させてもらったでしょう。
なお、「澪つくし」とは、小舟の航路を示し、座礁しないようにするための標識。
番組のラストシーンに近い場面で、惣吉がかをるに対して、「澪つくしのように、かをると子供達を身を尽くして守りたい」とプロボーズします。