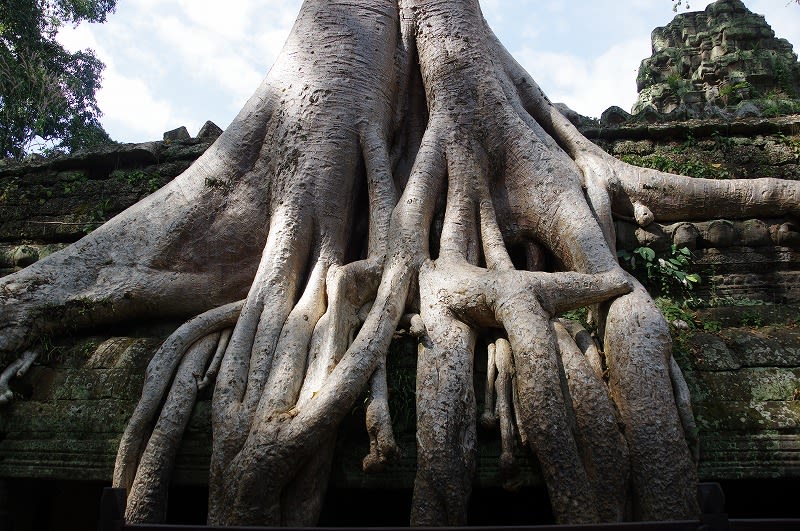台湾の旅、第3日は、南の都市、高雄から中央の山地を越えて東側に出て、海岸線を走る移動の旅となりました。
私が前回に旅した時は、まだ東側の道路は舗装もされていなくてバスで走るのはきつい旅だったようです。
遠くに、台湾第2の大きさの島、緑島が見えました。天気の良くない日は、見えないとのことでした。
夏は、レジャーの島として賑わうようですが、その昔は、政治犯や暴力団の人間の監獄があったと言うことです。

東側から西側の海岸線に抜ける時に、バスの中でガイドさんから聞いた「88水害」の話は驚くような話でした。
またバスからは、大きな「88水害の記念碑」も見えました。
2009年(平成21年)8月7日から11日にかけて、主に台湾南部で台風8号により、降った豪雨は、おおよそ3日間の間に
世界記録に匹敵する総降水量2000mmから3000mmとなりました。
このため、至る所で土砂災害などが発生し700人もの犠牲者が発生しました。
特に高雄県甲仙郷小林村では、付近の山の深層崩壊に襲われ、村がほぼ全滅し、400名もの方が亡くなりました。
台湾では、これまでの豪雨は一雨1000mm程度から、1500mm、そして今回の3000mmと増大し、降雨範囲も広くなる傾向にある
ようです。
日本では、2013年(平成25年)の10月11日に伊豆大島に甚大な被害をもたらした台風26号の土石流災害が記憶に新しいですが、
この時の総降雨量は824mm、死者・行方不明39名であることを考えると、いかに凄まじい豪雨であったことかが分かります。
何よりも、そんなにも雨が降る豪雨があるのか?というのが率直な感想でした。

東の海岸線、古くからの景勝地である三仙台。3人の仙人が岩の上で休んだという伝説があります。

こちらは、八仙洞。大小16の洞窟群。地殻の上昇の過程で波による浸食で出来ました。石器時代の住居跡が発見され、
台湾の第一史跡に指定されています。
詳しくは「めいすいの海外旅日記 台湾第3日」をご覧下さい。