日本軍兵士 吉田 裕 兵士の目線、立ち位置からとらえたアジア・太平洋戦争
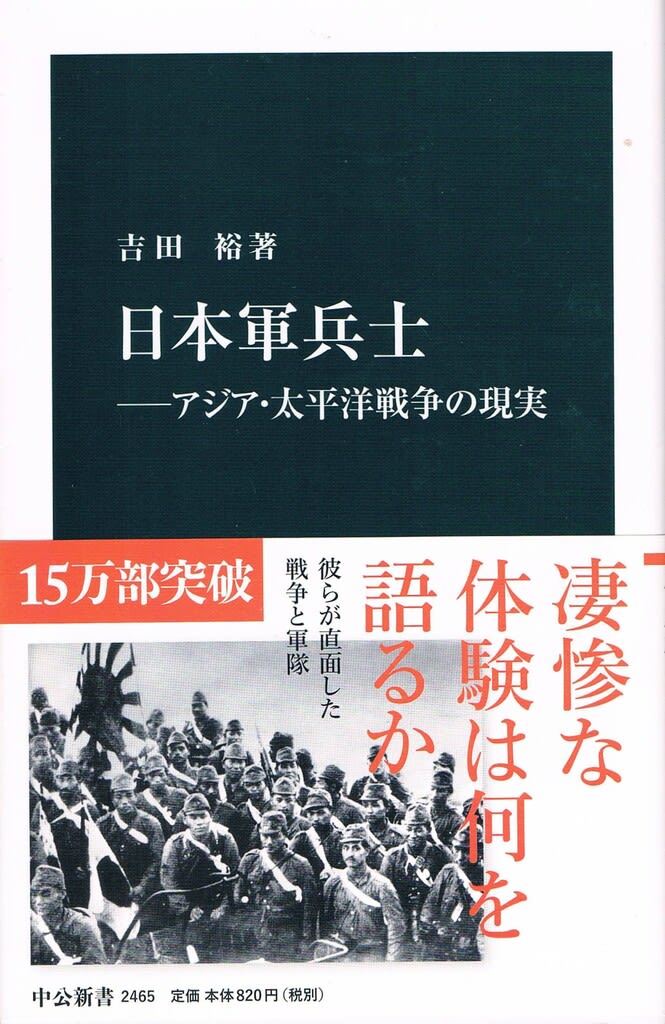
吉田裕氏は日本近現代史専攻の一橋大大学院社会学研究科特任教授。本書は2017年12月に刊行され、2018年8月には12版と版を重ねている。先の大戦を本書ではアジア・太平洋戦争と呼ぶ。戦没者は日本だけでも軍人・軍属が230万人(日中戦争期を含む)、民間人が80万人の合計310万人とされる。本書では、「三つの問題意識を重視しながら、凄惨な戦場の現実を歴史学の手法で描き出してみたい。それは、戦後歴史学を問い直すこと、『兵士の目線』で『兵士の立ち位置』から戦場をとらえ直してみること、そして、『帝国陸海軍』の軍事的特性との関連を明らかにすることである」。第一は、「戦後の歴史研究を担った第一世代の研究者が戦争の直接体験者であったために、平和意識がひときわ強い反面で、軍事史研究を忌避する傾向も根強かった」。二つ目は、「『兵士の目線』を重視し、『兵士の立ち位置』から、凄惨な戦場の現実、(中略)『死の現場』を再構成してみることである」。「三つ目の問題意識は、『帝国陸海軍』の軍事的特性が『現場』で戦う兵士たちにどのような負荷をかけたのかを具体的に明らかにすることである」。
序章は「アジア・太平洋戦争の長期化」だ。「日中戦争は、40年に入ると、行き詰まりの様相を呈していた。日本軍による大規模な進攻作戦の時代はほぼ終わりを告げ、中国各地の日本軍は占領地を防衛するための『高度分散配置』態勢に移行していた」「1940年の段階では、中国戦線(満州を除く)には約68万人の陸軍部隊が派遣されている。このうち抗日ゲリラの活動が活発な華北を例にとると、配備されている兵力は約25万人であり、警備地区1平方キロメートル当たりの兵力数はわずか0.37人、歩兵一個大隊(800人前後)の兵力で平均して2500平方キロメートルの地域(ほぼ神奈川県の広さ)を警備していたことになる」。
著者は、1941年12月の開戦以来、敗戦までを4期に分ける。第1期は42年5月までの日本軍の戦略的攻勢期。第2期は42年6月から43年2月。連合軍が反撃に転じ、日本軍との間で激戦が続いたミッドウェー海戦からガダルカナル島撤退まで。ガ島戦で、「日本軍は、多数の艦船と航空機、熟練した搭乗員を失い陸上戦でも米軍に完敗した」。第3期は、1943年3月から44年7月まで。「米軍の戦略的攻勢期、日本軍の戦略的守勢期である。この時期に戦争経済が本格的に稼働し始めたアメリカは、多数のエセックス級正規空母の就役や新鋭航空機の開発・量産などによって、その戦力を急速に充実させた。その結果、日米間の戦力比は完全に逆転し、その戦力格差は急速に拡大していった」「44年6月、米軍はマリアナ諸島のサイパン島への上陸を開始する。日本海軍の機動部隊はサイパン防衛のために出撃し、米軍の機動部隊に決戦を挑んだが、強力な反撃を受けて完敗した。(中略)7月にはサイパン島の日本軍守備隊が、8月にはグアム・テニアン両島の守備隊が全滅し、米軍はマリアナ諸島を完全に制圧した」。第4期は、「44年8月から45年8月の敗戦に至るまでの時期である。すでに敗戦必至の状況にありながら、日本軍があくまで抗戦を続けたため、戦争はさらに長期化した。絶望的抗戦期などと呼ばれる」。44年10月、米軍はフィリピン・レイテ島に上陸、45年4月には沖縄本島へ。マリアナ諸島を基地としたB29による本土空襲は44年11月に始まる。
「日本政府によれば、1941年12月に始まるアジア・太平洋戦争の日本人戦没者数は、日中戦争も含めて、軍人・軍属が約230万人、外地の一般邦人が約30万人、空襲などによる日本国内の戦災死没者が約50万人、合計約310万人である。(中略)この数字には朝鮮人と台湾人の軍人・軍属の戦没者数=5万人が含まれている」。米軍の戦死者数は約10万人、ソ連軍は約2万人、英軍が約3万人、オランダ軍が民間人も含めて約2万7600人。中国やアジア各地の人的被害は、「ある推定によれば、中国軍と中国民衆の死者が1000万人以上、朝鮮の死者が約20万人、フィリピンが約111万人、台湾が約3万人、マレーシア・シンガポールが約10万人、その他、ベトナム、インドネシアなどをあわせて総計で1900万人以上になる」。
「日本人に関していえば、この310万人の戦没者の大部分がサイパン島陥落後の絶望的抗戦期の死没者だと考えられる」。日本政府はなぜか年次別の戦没者数を公表していないが、岩手県の記録によると、1944年1月以降の戦死者は87.6%。ここから推算すると1944年1月以降の戦没者は約201万人、民間人死者約80万人を合わせると死者は約281万人、比率は91%に達する。「日本政府、軍部、そして昭和天皇を中心とした宮中グループの戦争終結決意が遅れたため、このような悲劇がもたらされたのである」。
第1章は「死にゆく兵士たち」。1944年以降の絶望的抗戦期の死の実態を明らかにする。異様なのは戦病死の比率がきわめて高いことだ。日露戦争では陸軍の戦病死比率は26.3%。日中戦争では1941年の時点で、戦病死比率は50.4%。アジア・太平洋戦争ではさらに高くなる。藤原彰氏は戦没者約230万人のうち、「栄養失調による餓死者と、栄養失調に伴う体力消耗の結果、マラリアなどに感染して病死した広義の餓死者の合計は140万人(全体の61%)に達すると推定する。秦郁彦氏はこれを過大と批判し、37%という推定餓死率を提示しているが、「類を見ない異常な高率であることには変わりがない」と指摘する。「このような多数の餓死者を出した最大の原因は、制海・制空権の喪失によって、各地の日本軍の補給路が完全に寸断され深刻な食糧不足が発生したからである」。栄養失調とともに兵士が悩まされたのはマラリアだった。キニーネが効かない難治性の患者が多かった。野戦病院の軍医は「マラリア治療を困難にした第一の要因は(中略)この地域前線の日本軍全般にみられた栄養低下にあったと思われる」と書く。著書は栄養失調状態が深刻化して生ける屍のようになった「戦争栄養失調症」にも触れている。
次が海没死だ。海軍軍人・軍属が18万2000人、陸軍軍人・軍属が17万6000人。合計すると日露戦争の戦没者の4倍に達する。「多数の海没死者を出した最大の要因は、アメリカ海軍の潜水艦作戦の大きな成功による」。第二次大戦全体で、米海軍は52隻の潜水艦を失ったが、1314隻、500万2000トンの枢軸国側商船を撃沈した。1隻の損失で25隻を撃沈した計算だ。日本海軍は127隻の喪失で、撃沈商船が184隻、90万トン。1隻の喪失で、1.4隻を撃沈した。「米海軍の対日潜水艦作戦では1943年半ばが大きな画期となった。米海軍は、この頃までに(中略)魚雷の欠陥を是正しただけでなく、日本商船の暗号解読に成功した。これによって、船団に対する待ち伏せ攻撃が可能になったのである」。
著者は「特攻死」についても分析する。「航空特攻は、1944年10月に、海軍がフィリピン防衛戦で神風特別攻撃隊を出撃させたのが最初である。当初の特攻作戦の任務は、レイテ湾への突入を図る栗田艦隊を支援するために、体当たり攻撃によって、アメリカの正規空母の飛行甲板を一時的に使用不能にすることにあった。(中略)それが次第にエスカレートし、翌1945年3月末から始まる沖縄戦の段階では、特攻攻撃が陸海軍の主要な戦法となった」。航空特攻による敗戦までの戦果は次の通りだ。正規空母撃沈0、撃破26、護衛空母(商船を改造した小型空母)撃沈3、撃破18、戦艦撃沈0、撃破15、巡洋艦撃沈0、撃破22、駆逐艦撃沈13、撃破109。その他撃沈31、撃破219。戦死者は海軍が2431人、陸軍が1417人だった。「戦果があまりあがらなかった理由の一つは、アメリカ側が、フィリピン戦以降、特攻作戦に対する作戦を強化したからである。米海軍は、機動部隊の前方に大型レーダーを装備した駆逐艦などのレーダーピケット艦をいくつも配備し、早期警戒と迎撃戦闘機の誘導にあたらせた。特攻機はこの阻止線(ピケットライン)を簡単には突破できなかったのである」。
著者は戦場での自殺にも触れる。インパール作戦やほぼ全員が死亡した硫黄島攻防戦では自殺者が少なくなかった。インパールで生還した兵士には何人もの自決を記録した人がいる。硫黄島攻防戦では、生き残った兵士が「敵弾で戦死したと思われるのは30%程度、残り7割の日本兵は次のような比率で死んだと思う。6割自殺、1割他殺(お前が捕虜になるなら殺すというもの)、1割事故死」と書き残している。
あえて著者が触れているのは「戦場での処置」だ。日本軍はジュネーブ条約で傷病兵が捕虜になることを認めていたが、1939年のノモンハン事件で多数の将兵が捕虜になったときには、将校には自決を迫り、下士官兵は軍法会議で審理した。戦場で負傷兵が後送できない場合、自殺を促すか、何らかの形で殺害することが暗示された。ガダルカナルでは1943年2月、駆逐艦による撤収作戦が行われたが、その段階で7割の兵士は戦死・戦病死(その多くは餓死)、3割が生存していたが、身動きのできない兵士は毒で自殺させ、単独歩行可能な者だけを撤退させた。5月にはアッツ島で守備隊が全滅しているが、「最後の総攻撃(いわゆる『万歳突撃』)に参加できない傷病兵が殺害され、あるいは自決を強要された」。藤田嗣治の戦争画に「アッツ島玉砕」があるが、こうした現実を知ると言葉がなくなる。
第2章は「身体から見た戦争」だ。戦争の拡大に伴って徴兵は大幅に強化された。陸海軍兵力は太平洋戦争開戦の1941年に約241万人(陸軍210万人)だったが、1945年には719万人(陸軍550万人)と膨張する。1940年には徴兵検査基準が大幅に引き下げられた。「ちょっとした疾病異常、とくに眼、鼻、耳、手足の指等の故障のため、現役兵として入営する事のできなかった者も、今後は適材適所を選んで入営」させることになる。その結果、徴兵検査で徴用された比率は41年の54%が、44年には77%に。体格の劣る兵士が増えたうえ、知的障害者の入営も始まる。ある軍医の記録では、「『精神薄弱』が3~4%」に達したという。精神疾患を病む兵士も急増する。病院船で本土に搬送された兵士のうち、精神疾患の占める比率は41年には5.04%だったが、43年には10.14%、44年には22.32%と激増する。物資窮乏のために兵士の装備も劣悪になる。軍靴は牛革と決まっていたが、1942年には馬革や豚革が使われ、44年になると鮫革までが登場する。レイテ戦記で有名な大岡昇平はゴム底鮫皮の軍靴に、「ゴム底は比島の草によく滑り、鮫皮はよく水を通した」とその惨状を書いている。
第3章は「無残な死、その歴史的背景」だ。「第一には欧米列強との長期にわたる消耗戦を戦い抜くだけの経済力、国力を持たないという強い自覚から、長期戦を回避し、『短期決戦』『速戦即決』を重視する作戦思想が主流を占めてきた」「第二には作戦、戦闘をすべてに優先させる作戦至上主義である。そのことは、補給、情報、衛生、防禦、海上護衛などが軽視されたことと裏腹の関係にある」「第三には、日露戦争後に確立した極端な精神主義である。それは(中略)軍の機械化や軍事技術の革新などに大きな関心を払わず、日本軍の精神的優越性をことさらに強調する風潮を生んだ」。
本書には、銃で突撃する白兵戦を想定して軽量な短機関銃(サブマシンガン)の開発を怠ったため、「ジャングル内での近接戦闘」に対応できなかった、陸上戦闘では米軍が使用した75ミリ砲搭載のM4中戦車や火炎放射戦車が脅威になったことが指摘されている。輸送力も大きく後れをとっている。元陸軍中佐は、「日本陸軍は『馬の軍隊』であり、『人力の軍隊』であった」と酷評している。工兵分野でも大きな差があった。ソロモン諸島やニューギニアでは、「米軍がブルドーザーやパワーシャベルなどの土木機械を駆使して必要な地点に一週間内外で飛行場を建設したのに対し、日本軍は人力主体の設定方式に依存し、飛行場の完成までに1カ月から数カ月もかかった」。通信機器はさらに大きな差があった。「陸軍は通信の必要性に関する認識がきわめて低く、(中略)師団通信隊が編成されるようになったのは、日中戦争以降」「陸上通信には有線通信と無線通信の二つがあったが、問題は陸軍があくまで有線通信を重視したことである」「44年9月から11月にかけて戦われたペリリュー島攻防戦でも、米軍の艦砲射撃と銃爆撃によって、早い段階で通信連絡組織が寸断された。その結果、各部隊は島内各地に『健在』しているにもかかわらず、『その統一組織を喪失してあたかも全身不随』」となった。
著者は最後に、近年目立つ陸海軍礼賛に強い警鐘を発する。「1990年前後から日本社会の一部に、およそ非現実的で戦場の現実とかけ離れた戦争観が台頭してきた」と批判、ここ数年は「日本礼賛本」がブームになっていると指摘する。「そんな風潮が根強く残っているからこそ、戦場の凄惨な現実を直視する必要があるのだと思う」と書く。評者には、1942年6月、フィリピン沖で海没死した海軍下士官の伯父(父の弟)がいる。命日近くになると、仏壇に白い軍装の遺影が飾られたのを思い出す。本書には300万人を超える戦没者の痛切な無念が刻まれている。著者が靖国偕行文庫やアジア歴史資料センターなどに収蔵されている部隊史などの一次史料を丹念に読み解き、本書をまとめあげたことに敬意を表したい。本書とともに「失敗の本質 日本軍の組織論的研究」(中公文庫)、ドキュメンタリー映画「東京裁判」(小林正樹監督)などを参照すると、さらに戦争の実相が立体的に浮き彫りになるはずだ。









