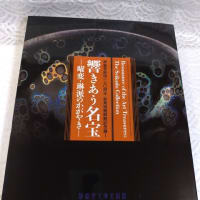<初出:2008年の再掲です>
巻三の三 信長、小牧山城へ移ること。ならびに元
康、修羅の道に入ること
永禄六年(一五六三)夏、織田上総介信長は先だ
って手を付けた「於久地城攻略」につき、家臣から
の「早く攻城戦を」との意見を抑え、まずは今期の
稲の生育状況を丹羽長秀・柴田勝家に聞く。彼らは
松井有閑・木下藤吉郎の報告をもとに「今年の作柄
は非常に良好」と上申する。どういうことかという
と、作柄不良の場合は米単価が安くなるため秋口に
コメを販売して稼げる利益が少なくなり、美濃への
進軍のための戦費がなくなるという理屈である。費
用もないのに軍を起こしては、国が疲弊し民を豊か
にすることはできない。
信長は、五郎左衛門と黒田城:和田定利との情報
交換により、「直接於久地城を攻めなくとも、織田
一行が城替えするだけで連中は驚いて退城するだろ
う」という確定に近い予想を得ていた。七月小牧山
城へと城替えをおこなうと、敵勢は予想通りそれを
見ただけで驚き、降参退城の上犬山城へと移動した
のであった。まるで『源平盛衰記』に出てくる「平
家の聞き逃げ」と同じである。
尾張方では想定通りの進行が続いていたが、三河
のほうでは信長以下が心配した通り、「軍を起こさ
ず戦費を蓄えておくべき元康」が「わけのわからな
い勝手」を行ってしまう。この年の三月、信長の女
『五徳』と元康の嫡男『竹千代(のちの信康)』の
婚約が成ったところまではよかったが、その後、信
長が小牧山城に移動しバタバタしている間に、
*今川氏真と手を切る
*松平家康に改名
と連続して進める。ここまでも、まだ悪くはないか
もしれないが、「戦費のないときに軍を起こしてし
まった軍将」は、手をつけてはいけない領域に手を
つけてしまう。すなわち、三河の産品であるきわた
(木綿)や唐納豆(麹菌を使った粘らない納豆)・
志都呂焼き・甲斐の紙・伊豆江川の酒など、各農家
や各商家が売買をし、敬虔な信者がその儲けの一部
を寺院に寄付していたのだが、当然寺院におさめた
金額は非課税である。松平家康一派はこの商流に絡
み、松平一派を通して課税しようとしたからおさま
らない。農家・商家・武家と檀家・寺院が複雑に絡
む内戦へと発達した。これが世にいう『三河一向一
揆』の発端であり、実はこれは「宗教戦争」ではな
く「経済戦争」だったのである。
三河の戦況に関して、以前尾張の信長以下が決定
した通り、「三河での家康の動きには関知していな
い」ことを確認済みで、干渉するつもりは全くない。
尾張勢の加勢をあてにして内戦を始めてしまった家
康がこの『三河一向一揆』をおさめるのは、半年後
の永禄七年(一五六四)二月のことであった。
↓ランキングに参加中。ぽちっとお願いします
 にほんブログ村
にほんブログ村
<JR岐阜駅前の黄金の信長公像>
巻三の三 信長、小牧山城へ移ること。ならびに元
康、修羅の道に入ること
永禄六年(一五六三)夏、織田上総介信長は先だ
って手を付けた「於久地城攻略」につき、家臣から
の「早く攻城戦を」との意見を抑え、まずは今期の
稲の生育状況を丹羽長秀・柴田勝家に聞く。彼らは
松井有閑・木下藤吉郎の報告をもとに「今年の作柄
は非常に良好」と上申する。どういうことかという
と、作柄不良の場合は米単価が安くなるため秋口に
コメを販売して稼げる利益が少なくなり、美濃への
進軍のための戦費がなくなるという理屈である。費
用もないのに軍を起こしては、国が疲弊し民を豊か
にすることはできない。
信長は、五郎左衛門と黒田城:和田定利との情報
交換により、「直接於久地城を攻めなくとも、織田
一行が城替えするだけで連中は驚いて退城するだろ
う」という確定に近い予想を得ていた。七月小牧山
城へと城替えをおこなうと、敵勢は予想通りそれを
見ただけで驚き、降参退城の上犬山城へと移動した
のであった。まるで『源平盛衰記』に出てくる「平
家の聞き逃げ」と同じである。
尾張方では想定通りの進行が続いていたが、三河
のほうでは信長以下が心配した通り、「軍を起こさ
ず戦費を蓄えておくべき元康」が「わけのわからな
い勝手」を行ってしまう。この年の三月、信長の女
『五徳』と元康の嫡男『竹千代(のちの信康)』の
婚約が成ったところまではよかったが、その後、信
長が小牧山城に移動しバタバタしている間に、
*今川氏真と手を切る
*松平家康に改名
と連続して進める。ここまでも、まだ悪くはないか
もしれないが、「戦費のないときに軍を起こしてし
まった軍将」は、手をつけてはいけない領域に手を
つけてしまう。すなわち、三河の産品であるきわた
(木綿)や唐納豆(麹菌を使った粘らない納豆)・
志都呂焼き・甲斐の紙・伊豆江川の酒など、各農家
や各商家が売買をし、敬虔な信者がその儲けの一部
を寺院に寄付していたのだが、当然寺院におさめた
金額は非課税である。松平家康一派はこの商流に絡
み、松平一派を通して課税しようとしたからおさま
らない。農家・商家・武家と檀家・寺院が複雑に絡
む内戦へと発達した。これが世にいう『三河一向一
揆』の発端であり、実はこれは「宗教戦争」ではな
く「経済戦争」だったのである。
三河の戦況に関して、以前尾張の信長以下が決定
した通り、「三河での家康の動きには関知していな
い」ことを確認済みで、干渉するつもりは全くない。
尾張勢の加勢をあてにして内戦を始めてしまった家
康がこの『三河一向一揆』をおさめるのは、半年後
の永禄七年(一五六四)二月のことであった。
↓ランキングに参加中。ぽちっとお願いします
<JR岐阜駅前の黄金の信長公像>