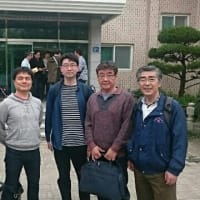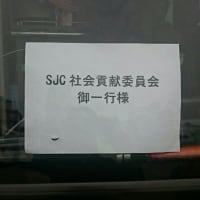今日は景福宮打令の歌詞を見ていきたいと思います。まず、この曲を聞いたことが無い方もいらっしゃると思うので、実際に我々が歌った映像をご紹介したいと思います。
本年6月22日、ソウル「芸術の殿堂」コンサートホールで開催された日韓国交正常化50周年記念コンサートでの映像です。(景福宮打令は7分42秒あたりです。)
如何ですか?勇壮な曲でしょう。ちなみに、このコンサートについては12月に刊行されるソウル日本人会会報に拙稿が掲載される予定ですが、いつかこのブログにおいても、SJCの会報とは別の切り口でご紹介しようと思います。
それでは歌詞を一つづつ、見ていきましょう。このブログをお読みの中には、韓国語に接する機会がない方もいらっしゃると思うので、分りやすさ最優先でご説明しようと思います。
남문(南門)을 열고 파루(罷漏)를 치니 계명산천(鷄鳴山川)이 밝아온다.
南大門を開いて時の鐘をつけば、にわとりが鳴いて山河が明るくなってくる。
ここで南門というのはソウルの南大門のこと。罷漏(パル)とは、朝鮮王朝時代に早朝4時に鐘を33回打って、城門を開いたことを意味します。
かってソウルは漢陽(ハニャン)と呼ばれ、都市全体が城壁で囲まれていた城郭都市でした。この鐘を合図に東西南北の大門が開かれ、夜の10時に閉門されるまで、一般人が城内、つまりソウル市内を通行できたのです。今風に言ってしまうと、夜10時から朝4時までは夜間通行禁止令が出ていたということ。
ちなみに早朝4時に城門を開くことを罷漏(パル)、一方、夜の10時に城門を閉めることは人定(インジョン)と言います。罷漏(パル)は33回。人定(インジョン)では28回、鐘をつきます。
実のところ、この罷漏(パル)の鐘は現存しており、大韓民国「宝物」第2号として国立中央博物館に所蔵されています。

ちなみに、大韓民国「宝物」第1号は東大門。大韓民国「国宝」第1号は南大門です。それじゃあ、宝物(보물ポムル)と国宝(국보クッポ)はどこが違うのでしょうか?
韓国人に聞いても誰も答えてくれないので、調べたところ、「国宝級の文化財がその分野、その時代を代表する唯一無二のものとするなら、宝物級に属する文化財はそれに類似した文化財で、大韓民国文化を代表する遺物だと言える」というのが政府の公式見解です。よう分らん、というよりサッパリ分からない説明ですが、韓国ではよくあることなので気にしないでください。
ソウル市内中央部に普信閣(보신각ポシンガク)という建物があります。現在の建物は1980年に再建されたものですが、今では除夜の鐘のイベントで有名です。イベントの様子は全国に中継放送され、私も一度、現場で聞いてみたいのですが、氷点下の夜空の中、押し合いへし合いの人ごみにもまれる気力もなく、現在に至っています。
日本で除夜の鐘というと、紅白が終わった後でNHKの「ゆく年くる年」を見ながら自宅でまったりすごすイメージですね。日本は108回ですが、韓国では33回です。なんで33回かというと、日本では寅さんの柴又で有名な帝釈天が統治されている須弥山(しゅみせん)の四方に32のお城があり、それに。帝釈天ご自身が住んでおられるという善見城を加えて三十三天と呼ぶそうです。
要は、33回鐘を突いて、その三十三天の主である帝釈天の世界と結びつき、世の太平を祈願する心が込められているとのこと。
おなじ仏教でも日本とは違いますね。


もう時間がないので、今日はこれくらいにしますが、韓国で除夜の鐘というセレモニーが始まったのは1929年(昭和4年)。つまり日本の植民地時代です。当時、南山にあった本願寺の鐘を京城放送局のスタジオに移設して放送したのが韓国における除夜の鐘の始まりであるとのこと。当時は韓国(外地)の鐘と日本(内地)の鐘を交互に打ち鳴らしていたそうです。その後、終戦によって除夜の鐘という行事そのものが無くなるのですが、1953年に復活し、今では国を挙げての年中行事となりました。
当時、朝鮮半島に住んでいた日本人はどんな思いで遥か彼方の内地の鐘の音を聴いていたのでしょうか。