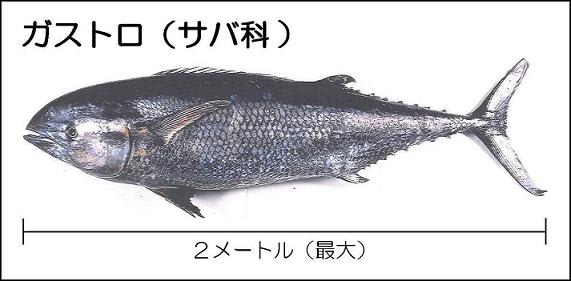暑い日が続くと、不思議と刺身や寿司よりも焼き肉や焼き鳥でビールということになる。
特に、厚切りに焼いた牛タンに「ネギ塩タレ」を乗せ、上からレモンを絞って食べると格別に旨い。

<ネギ塩ダレの作り方>
ゴマ油にひとつまみの塩とタップリの万能ネギのみじん切りを加える。
これを焼いた牛タンの上に乗せ、レモンをたっぷり絞って食べる。(お好みで白ゴマを上から散らす)
さて、この牛タンだが語源は英語で舌を意味する tongue の音からきたようだ。
日本では太平洋戦争の前にはほとんど食べられることがなく、また、牛タンは珍味の扱いで一般の家庭で牛タンを食べることはなかったようだ。
牛タンが普及したのは、1991年からの牛肉の輸入自由化で、これに伴い安価に材料が入手できるようになり、焼き肉店などから牛タンが広まったようだ。
ちなみに焼いた牛タンにレモンを絞って食べる「タン塩」は東京の六本木にある焼肉店「叙々苑」が発祥とも言われている。
この牛タンの食べ方だが、焼いて食べる調理法以外には「タンシチュー」などの煮込み料理が多い。
それは、タン先が繊維質で硬く、長時間煮込んで軟らかくしないと食べられないからだ。
実際に脂肪の付き具合の良い牛タンでもタン先は硬くて焼いて食べるには向かない。
特に牧草で育てた牛肉は、まったく脂肪がなくタン先どころか、タン全体が赤身肉で硬い。
そこで、ほとんどがひき肉にすることで、ハンバーグの増量剤などに利用されている。
この牛タンにも同じように、牛脂をインジェクションしたら美味しく食べられるのではないかと思い、テストをしてみたのだが、サーロイン同じように、赤身肉が軟らかく美味しく食べられるようになった。
下の写真が原料の牛タンだが、硬い皮つきのままだ。

このままではインジェクターの針が刺さらないので皮をカットしたのが下の写真だ。

製造方法はサーロインのインジェクションとまったく同じで、牛脂と水を乳化し、また、酵母や酵素を加えて牛タンにインジェクション(注入)する。
下の写真は実際に出来上がった牛タンのインジェクションだが、肉全体に綺麗に「サシ」が入っている。

そして、この牛タンの大きな特徴は、本来硬くて食べられなかった「タン先」まで、軟らかく食べられることだ。
工場では出来上がった商品を必ず毎回、自分で試食をしているが、今回の牛タンは「しゃぶしゃぶ」にして食べてみた。
肉は軟らかく適度に脂肪があり、あの赤身肉が原料とはまったく思えない素晴らしい出来上がりとなった。
インジェクションとしう加工法には、これからも大きな可能性があると思う。
たとえば、牛肉以外に豚肉のモモ肉(赤身肉)ラードをインジェクションすれば、トンカツにも利用できるだろう。
また、「どんぐりの香りのオイル」を一緒にインジェクションすれば、「イベリコ豚」のようになるだろうし、各種のハーブオイルを一緒にインジェクションすれば「ハーブ豚」になるだろう。
ただし、作る側は正確な「情報開示」をして、また、食べる側も、インジェクションミートだと理解した上で食べれば、インジェクションミートは加工法というより肉の調理法として食を楽しくしてくれると思う。
特に、厚切りに焼いた牛タンに「ネギ塩タレ」を乗せ、上からレモンを絞って食べると格別に旨い。

<ネギ塩ダレの作り方>
ゴマ油にひとつまみの塩とタップリの万能ネギのみじん切りを加える。
これを焼いた牛タンの上に乗せ、レモンをたっぷり絞って食べる。(お好みで白ゴマを上から散らす)
さて、この牛タンだが語源は英語で舌を意味する tongue の音からきたようだ。
日本では太平洋戦争の前にはほとんど食べられることがなく、また、牛タンは珍味の扱いで一般の家庭で牛タンを食べることはなかったようだ。
牛タンが普及したのは、1991年からの牛肉の輸入自由化で、これに伴い安価に材料が入手できるようになり、焼き肉店などから牛タンが広まったようだ。
ちなみに焼いた牛タンにレモンを絞って食べる「タン塩」は東京の六本木にある焼肉店「叙々苑」が発祥とも言われている。
この牛タンの食べ方だが、焼いて食べる調理法以外には「タンシチュー」などの煮込み料理が多い。
それは、タン先が繊維質で硬く、長時間煮込んで軟らかくしないと食べられないからだ。
実際に脂肪の付き具合の良い牛タンでもタン先は硬くて焼いて食べるには向かない。
特に牧草で育てた牛肉は、まったく脂肪がなくタン先どころか、タン全体が赤身肉で硬い。
そこで、ほとんどがひき肉にすることで、ハンバーグの増量剤などに利用されている。
この牛タンにも同じように、牛脂をインジェクションしたら美味しく食べられるのではないかと思い、テストをしてみたのだが、サーロイン同じように、赤身肉が軟らかく美味しく食べられるようになった。
下の写真が原料の牛タンだが、硬い皮つきのままだ。

このままではインジェクターの針が刺さらないので皮をカットしたのが下の写真だ。

製造方法はサーロインのインジェクションとまったく同じで、牛脂と水を乳化し、また、酵母や酵素を加えて牛タンにインジェクション(注入)する。
下の写真は実際に出来上がった牛タンのインジェクションだが、肉全体に綺麗に「サシ」が入っている。

そして、この牛タンの大きな特徴は、本来硬くて食べられなかった「タン先」まで、軟らかく食べられることだ。
工場では出来上がった商品を必ず毎回、自分で試食をしているが、今回の牛タンは「しゃぶしゃぶ」にして食べてみた。
肉は軟らかく適度に脂肪があり、あの赤身肉が原料とはまったく思えない素晴らしい出来上がりとなった。
インジェクションとしう加工法には、これからも大きな可能性があると思う。
たとえば、牛肉以外に豚肉のモモ肉(赤身肉)ラードをインジェクションすれば、トンカツにも利用できるだろう。
また、「どんぐりの香りのオイル」を一緒にインジェクションすれば、「イベリコ豚」のようになるだろうし、各種のハーブオイルを一緒にインジェクションすれば「ハーブ豚」になるだろう。
ただし、作る側は正確な「情報開示」をして、また、食べる側も、インジェクションミートだと理解した上で食べれば、インジェクションミートは加工法というより肉の調理法として食を楽しくしてくれると思う。