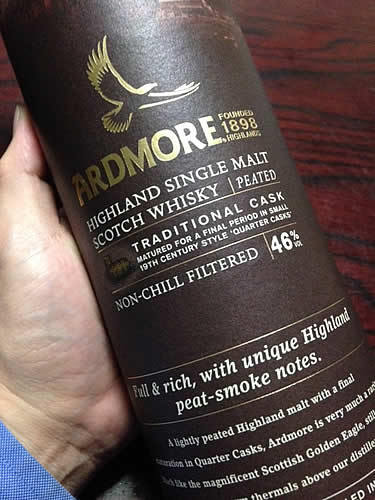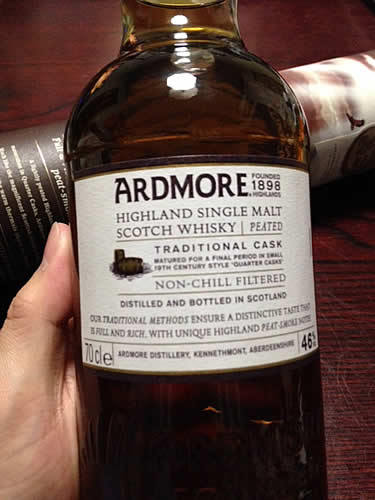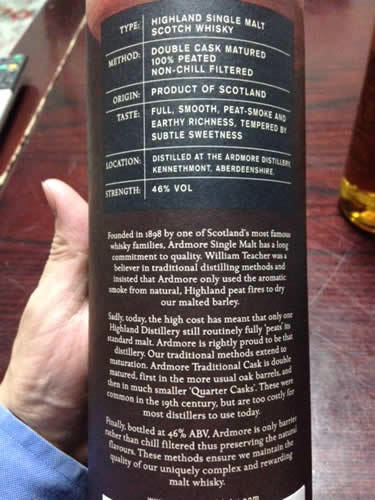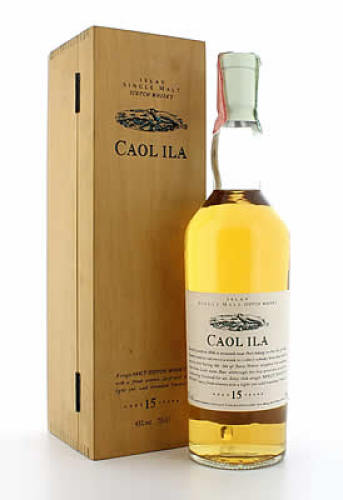最初は樽の話、2回目はブランド?の話、3回目はブレンドの
話、4回目は品質管理の話、5回目は市場の話、今回は未来の
話です。
ウィスキーの歴史が語られるとき、よく耳にする逸話は例のあれ
でしょう。17世紀から18世紀にかけてのスコットランドでの
酒税法と密造の話です。曰く「密造した酒を徴税使の目から免れ
るため、樽に詰めて山奥に隠した。年月が経って取り出してみる
と、琥珀色に変化し芳醇な香りのする液体に変わっていた」と
いうものです。
日本におけるウィスキーの歴史は、広島・竹鶴酒造の三男坊で
ある竹鶴政孝が洋酒製造に興味をもち、単身スコットランドへ
修行へ出掛けることから始まります。このときの竹鶴の身分は
摂津酒造の従業員でしたが、その後帰国しウィスキー製造を始め
ようとした時には時世が悪化し、摂津酒造にウィスキー製造を
始める余力がありませんでした(1920年)。
少し時代が下って、寿屋(現サントリー)の鳥井信治郎がウィスキー
製造に乗り出そうと考えた際、竹鶴を雇用して摂津と山城の
国境である山崎にウィスキー工場を建設します(1924年)。
10年後の1934年、竹鶴は鳥井との契約期間である10年を
満了したことから寿屋を退社し、国内でウィスキーを製造する
最有力候補地であった北海道・余市にウィスキー工場を建設
します。
さて、スコットランドでウィスキーなる蒸溜酒が作られるように
なり、また日本で四捨五入すると約100年前の当時のウィスキー
作りを考えてみると、何もかもが経験知によって製造される家内
制手工業の実態であったことは容易に想像ができます。
当時の「現代的」というのは、せいぜい産業革命によって蒸気機関
(18世紀の発明)や、鉄鋼が用いられるようになった程度です。
このため、全世界中のウィスキー工場の99%は、歴史的に牧場で
あったという背景をもつためか、酒造メーカという業種的な特徴
とは異なる理由で、現在でも牧歌的などこか懐かしい風情があり
ます。
しかし、現在一番といっていいほど最新鋭である台湾にあるカヴァ
ラン蒸溜所は、工場の建物は完全密封でITによる製造管理を
行っており、工場見学に出掛けてもガラス張りの通路を通るだけ
だそうです(すみません。私はまだ行ったことがありません)。

そうして出来上がる製品は、非常にクリアな均一感高い味のウィ
スキーに仕上がっていて、従来に比べて短期間での熟成(これも
製造管理が可能)によってコンテストで高い評価を得ています。
この業界では「ウィスキーは飲むほどに美味しくなる酒だ」という
言葉があります。長年ウィスキーを飲んでいると味覚が鋭くなり、
より細かい味を美味しく感じるようになるのだといいます。
これを切り取って、例えばジャーナリストの方は「ウィスキーは
科学(サイエンス)か芸術(アート)か」という表題を掲げられます
が、これまでの時間の経過を踏まえて表せば「伝統的に芸術の
領域だったものに、どんどん科学が進出している」と評すのが
正しい表現でしょうが、ポイントはどこまで時代が下って、どこ
まで科学が進出しても、ウィスキーは嗜好品という趣味の分野の
製品だということです。
趣味が嵩じて研究になれば、ごく一般的な事実は前提となり、
もっぱら関心は「美味しさを生み出す秘密(要素)や秘訣(技術)」
に移り、その数が多く複雑であるほどこれらのミックスやバラ
ンス、最大公約数の可能性を探求することになります。もし、
さらに趣味が嵩じて製造する立場になった人物がいたとしたら、
最大公約数だけでなく最小公倍数の可能性も経営には必要と
なるでしょう。
そういう時系列のなかにいて、現在がどの時点かといえば、先の
カヴァラン蒸溜所のアプローチは、とりあえず最大公約数は
考えずに最小公倍数だけ訴求するという種類のものです。それは
モルトスターから購入した麦芽をエアコンディショニングされた
工場で発酵させ、シェリー樽でフィニッシュした味わいからも
明らかです。
足元の市場が「甘め」を志向しているとき、このアプローチは
短期的に大ヒットする可能性を秘めています。広告宣伝にレバ
レッジを効かせれば、数世紀の歴史と伝統のブランドを曇らせる
だけの力があるかもしれません。
一方で消費者の関心は移ろいやすく、現代のスピード社会では
その速度は加速するばかりですから”ハイボールのお客さん”
ばかりに経営の基盤を求める一本足打法経営はレバレッジを
効かせるには危険が伴います。
こういう最前線で、ウィスキー製造の現場において何かを目的
に、アートがサイエンスに置換される事態が進行しています。
それは製造のリードタイム短縮であったり、均一な味を訴求し
バラツキという誤差を極小化することであったり、製造コストを
削減することであったりです。この3つのどれかひとつでも
あるいは全てならもちろん経営努力として評価されるのは間
違いありません。
しかしながら、飽きやすいのに鋭いセンサーをもつ人間の味覚
に対し、この努力はゴーイングコンサーン(事業の継続可能性)
と映らないかもしれません。それが証拠にワインの分野では、
科学的な製造アプローチで評価を受ける銘柄と、完全に伝統的
な製造アプローチで評価をうける銘柄では、依然として後者の
評価が高いからです。
この評価が確立し業界全体として浸透するのは、マニア向けに
ハイエンドしたシングルカスクマニアのレイヤーと、蒸溜所レ
ベルでの個性を楽しむモルトファンのレイヤーと、氷や水や
トニックウォーターで割って飲みやすい味を求めるレイヤーが
統合ではなく分離した後の、これから十数年~数十年の後の
ことでしょう。
このあいだに、ひとつでも多くの蒸溜所が存続できることを
希望したいと思います。(了)
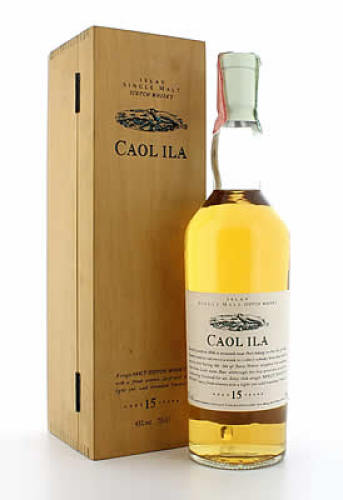

にほんブログ村
感謝!