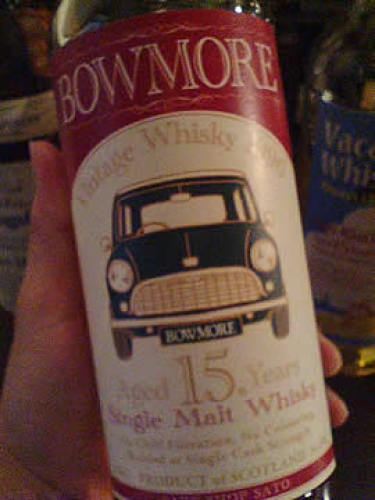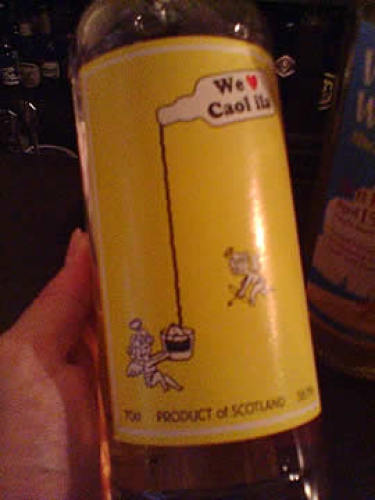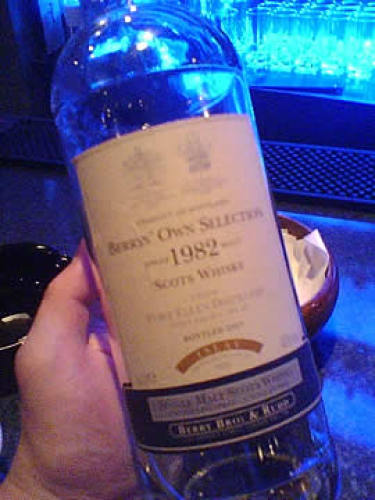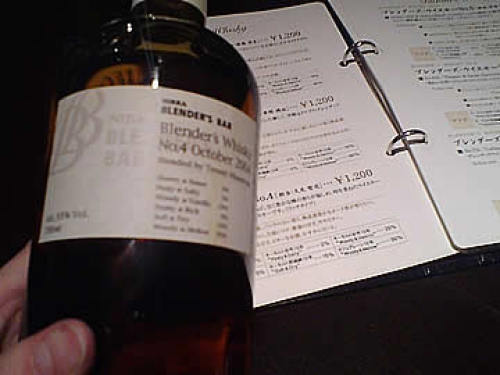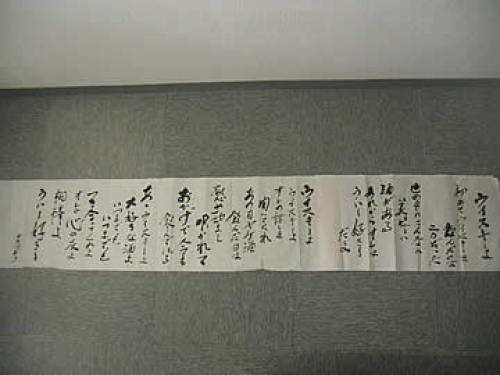昨日のパンチョン樽がサントリー・ウィスキーの正体なら、
今日のミズナラ樽は山崎の正体だ。

前回のパンチョン樽に比べて、色が濃いのが分かるだろうか。
パンチョン樽というのは、いわゆるオーク樽の大型480L版
なのだけれども、飲み物としてみれば新樽の濃いバニラ香よりも、
蒸溜原酒のもつエステル香が強かったりするのが特徴といえば
特徴と言えるのではないか。
対して、日本のミズナラで作る樽というのは、日本の木だから
なのかそうなのかは分からないが、間違いなく言えるのは木の
種類が異なることによる風味や香味の違い、濃度の違いといった
ものがあるということ。
それが、あの山崎をひと口舐めたときに感じる、梅酒のような
フルーティで甘く口の中に広がるボディだろう。昨年、ベンチャー
ウィスキーの秩父蒸溜所で作ったミズナラ樽をテストさせて
いただいたが、同様にリキュールのような果実味あふれる独特の
味がして「これがウィスキーか」と驚いた。
そして、その驚きは響のボディともなり、世界のコンテストで
受賞を重ねるようになり、ジャパニーズ・ウィスキー独特の個性
として世界で知られるようになりつつある。
これは新樽の味なんだよ、そうフランス人にでも話したら、きっと
眼を丸くして驚くだろう。
そう。他所で作れないからこそ商売になり、最高の場所とは限ら
なかったからオリジナルの製法になった。
ミズナラ樽は、だから山崎とサントリー社の公然の秘密なのだ。
![]()
にほんブログ村
感謝!