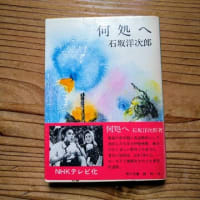うちにある古典的な本を取り出してみました。最初は、1919年の和辻哲郎さんの『古寺巡礼』からです。和辻さんが30歳の時、京都・奈良の古寺を巡り、その印象をまとめた本だったそうです。和辻さんはその後書き改めようとしたそうです。けれども、その時の印象を変更するわけにもいかず、そのまま今日に至っていしまったということでした。
もう百年以上前の百済観音の印象記ですね。
彼ら(百済観音に初めて対面した当時の人々)は新しい目で人体をながめ、新しい心で人情を感じた。そこに測り難い深さが見いだされた。そこに浄土の象徴があった。そうしてその感動の結晶として、漢の様式をもってする仏像が作り出されたのである。
スリムな百済観音さんのお姿を見ていると、人間的なスタイルのあれこれはデォルメされていて、手足は長いし、背は驚くほど高いし、顔は小さいし、バランスは普通の人間を越えてはいるのです。でも、人の姿に似た存在ではあるので、おすがりしたい気持ちも刺激されるし、すべての苦難を取り除いてくれそうな、たくましさや強さも感じるのです。どんなことがあっても、慌てないでそこにスックと立っておられる姿に私たちは励まされるのです。
この仏様は、百済(朝鮮半島)の仏様なのか、韓国伝来なのか、それとも漢(中国風)スタイルなのか? 木材はクスノキだそうで、日本の木で作られた可能性が高いということでした。
制作した人たちが朝鮮半島から渡来した人たちだったのか、それにしては、あまりにポッンとしておられて、もっと他の仲間の仏様はおられなかったのだろうか。存在そのものがミステリアスなのです。

百済観音の奇妙に神秘的な清浄な感じは、右のごとき素朴な感情を物語っている(こういう仏様を作りますよという渡来人のみなさんたちの制作意図に共鳴した?)。あの円い清らかな腕や、楚々として濁りのない滑らかな胸の美しさは、人体の美に慣れた心の所産ではなく、初めて人体に底知れぬ美しさを見いだした驚きの心の所産である。
飛鳥時代の仏様って、そんなに人体のしなやかさを形にしたものはありませんでしたね。素朴で、ただ真面目に仏教の世界はこんなですよ。お釈迦さまが中心ですよ。静かな世界ですよ。平安の世界ですよ。祈りなさい。その体系を形にした仏像も、ほら、この通りに真面目で、瞑想的で、上から人々の世界をしっかり見ていますよ。すべてお見通しですよ。聖徳太子さんくらいに真面目に仏様にお仕えしたら、あの人みたいに仏様になれたりしますよ。ステキでしょ? という感じがありましたよね。

あのかすかに微笑を帯びた、なつかしく優しい、けれども憧憬の結晶のようにほのかな、どことなく気味悪ささえ伴った顔の表情は、慈悲ということのほかに何ごとも考えられなくなったういういしい心の、病理的と言っていいほどに烈しい偏執を度外しては考えられない。このことは特に横からながめた時に強く感ぜられる。面長な柔らかい横顔にも、薄い体の奇妙なうねり方にも。
百済観音さまのお顔は、そんな表情でしたか。でも、この文って、あまりに長すぎて、装飾的でわかりにくいですね。
お顔の表情は、慈悲の感じが出てる、というのを言いたかったんですね。横から見たら特にそれが感じられる、ということなんですね。
百済観音さんって、他の法隆寺の仏様たちと何か違うというのは、私みたいなものが見てもわかります。スタイルが違う。お顔は、ものすごく疲れておられるようにも見えるし、何か言いかけて途中でやめて、静かに様子を見ているようにも見える。でも、何かメッセージは感じることができるから、よくはわからないけど、お参りしたい気持ちは自然に湧き上がってしまう。
和辻哲郎さんは、もっとあれこれ書いておられるんですけど、抜き書きしたところではこんな感じです。他の古典もみてみようと思います。