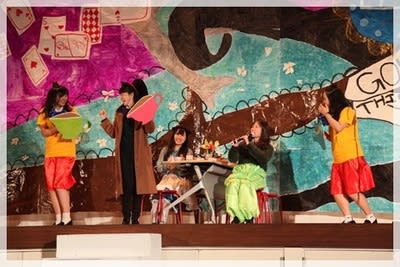「祇園」から白川沿いに歩いて東大路をこえると、東山を「借景」にした知恩院へ続く一本道がみえ、その手前にドラマ「京都地検の女」で和服姿の名取裕子が日傘をさして佇んだシーンで有名な「一本橋」がある。
「天台宗」の総本山・比叡山延暦寺にて七年間にわたって行われる修行=「千日回峰行」(せんにちかいほうぎょう)で、京都市中を歩きまわるときに修行者がこの橋を渡ることで知られる。別名「行者橋」(ぎょうじゃばし)と言うのはここからきている。





映画『ぼく明日』では、男性(福士)の下宿が「一本橋」近くという設定。男性と女性(小松)が楽しげに買い物をするシーンもこの商店街。ちなみに『京都地検の女』で女性グループがミックスジュースを飲みながら盛り上がるシーンもこの商店街で撮影された。
その昔、「東の錦」と言われるぐらい繁盛したらしいが、今その面影はない。しかし、各所に町屋を改装したおしゃれな宿泊施設が点在、生徒たちもそのセンスの良さに注目していた。



今後のスケジュールを考えると、ここで時間を費やすヒマはない。後日、個人的に満足いくまで味わえばいい。

「東大路三条」交差点にある日本一地味な(?)マクド。

瓦に「三つ巴」のマークを発見。「巴」マークを「水滴」にみたてて、「火事」を防ぐまじないとした。日本建築の瓦でよくあるマークだ。

外国人観光客の間で有名な「懐古庵」。京都市中でよくみかける「路地」(ろーじ)の長屋を改装して、長期滞在が可能な宿泊施設とした。もちろん外国人でなくても宿泊は可能。

「路地」(ろーじ)の入口付近は階上に部屋や物置があると思われるトンネルになっているパターンが多い。


そのトンネルを抜けると左右の軒の間から空が見える。通路には「犬矢来」「おくどさん」「井戸」「地蔵尊」「五右衛門風呂」など、レトロ好きにはたまらないアイテムが並んでいた。

「五右衛門風呂」発見。

京都の「路地」(ろーじ)の一番奥に必ず鎮座している「地蔵尊」。「地蔵尊」は「地蔵菩薩」の尊敬語。平安時代後期に「院政」を始めた「白河天皇」が、幼くして亡くなった子供の身代わりとなってその苦しみから救うという「地蔵菩薩」を手厚く大切にしたエピソードから、庶民の間でもその風習が広まったという。

以下次号