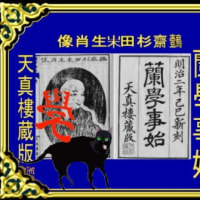「ほこり」の国・・・「誇(言+夸→大+一+丂)=ほこり=埃(十+一+ム+ノ一+一+人)・塵(鹿+十+一)・芥(丱+∧+リ)」・・・「絵字附図」・・・「埃及(エジプト)」・・・金字塔=ピラミッド(Pyramid、アラビア語: هرمハラム)・・・ギリシア語で三角形のパンを指すピューラミス(πυραμίς; pyramis; ピラミス、ピラムスとも)に由来。古代エジプト語ではギザのピラミッドに「昇る」という意味の「メル(ミル、ムルとも。ヒエログリフでは△と書く)」・・・「誉田(譽田=與+言)別」・・・「応神天皇(仲哀天皇九年十二月十四日・200年1月5日)~(応神天皇四十一年二月十五日・310年3月31日)、生地は「宇美町」、母は「神功皇后」、父は「仲哀天皇」、諱は「誉田別尊(ほむたわけのみこと)」、「大鞆和気命(おおともわけのみこと)」・・・「胎中天皇」、「品陀和氣命(ほむだわけのみこと・古事記)」・・・「品陀天皇・品太天皇」・・・そして、似た様な名前が「垂仁天皇」の「品牟都和氣命・本牟智和氣御子(古事記では天皇位についた人物だけが御子と記録されるが本牟智和気命、倭建命は天皇位に就いていない)」しかも、同じ「古事記」の記録の場所で「品牟都和氣命」と「本牟智和氣御子」が同一人物の記録とされている」、「日本書紀」には「誉津別命(ほむんつわけ)」と記録・・・
ーーー↓
垂仁天皇
崇神天皇二十九年一月一日~垂仁天皇九十九年七月十四日)
第十一代天皇
在位は垂仁天皇元年一月二日~垂仁天皇九十九年七月十四日)
活目入彦五十狭茅尊(いくめいりびこいさちのみこと)
活目尊
「古事記」は「伊久米伊理毘古伊佐知命(いくめいりびこいさちのみこと)」
「常陸国風土記」は「伊久米天皇」
「令集解・所引・古記」は「生目天皇」
「上宮記・逸文」は「伊久牟尼利比古(いくむにりひこ)大王」
父は「崇神天皇」
子に「倭姫命」・・・大和秘めの名
ーーー↓
古事記原文
亦
天皇、命詔
其后言、
凡
子
名、
必
母名、
何稱
是子之御名。
爾
答白、
今當
火燒
稻城
之
時而、
火中所生。
故、
其
御名
宜稱
本牟智和氣御子。
ーーー↑
何故、「火中所生」が「本牟智和氣御子」の名前と関連するのか?・・・これは前文の
「稻城・・・・・イナギ→異名義・伊名義・否義
之・・・・・・シ→詞、史、師、士、死・氏・至・・・市
時而」・・・・時(とき・ジ)・而(しこうして・しかも・ジ・ニ)
ジジ=時事・次次・次々・爺
が、その「理由」である・・・「伊藤博文」である、カナ・・・
ーーーーー
(一四段)・・・十四段・壱拾四段・壱四段・壱拾肆(長+聿)
市は
辰(たつ)の市。・・・辰刻(七~八時)・龍→劉・隆・留・立
椿市は、・・・・・・・つばき→通葉記・・・唾(口+垂)
大和に・・・・・・・・ダイワに→拿意話似
數多・・・・・・・・・スウタ→数他・崇多
↓
崇神天皇・大多田根子(大三輪氏の祖)
大田田根子命
意富多々泥古命
ある中に、
長谷寺に・・・・・・・「長国事・兆国次・超克時・帳国字」似
まうづる人の、・・・・毎鶴の人
かならず・・・・・・・掛名等事
そこに
とど・・・・・・・・・トド・鯔・椴・百々
まり・・・・・・・・・真理・万理・鞠・毬・麿・麻呂
ければ、・・・・・・・仮例葉
觀音の・・・・・・・・観れ音を
御縁ある・・・・・・・音宛
にやと、・・・・・・・似也止
心・・・・・・・・・・シンの同音漢字のスベテ
こと・・・・・・・・・異
なる・・・・・・・・・鳴る
なり。・・・・・・・・名理
ーーー↓
おふさの市。・・・・・負ふさ埜一
おふさ観音バラまつり
春と秋に開催
イングリッシュ・ローズ等の薔薇市
おふさ観音=火寺のある地名と合わせて
「小房(おふさ) 観音」と呼ばれている
正式名は高野山真言宗別格本山観音寺
本尊は
十一面観音
奈良県
橿原市
小房(おうさ)町の寺院通称名
山号は
十無量山
正式名称は高野山
真言宗
別格
本山
十無量山
観音寺
英国薔薇(イングリッシュローズ種)が
境内に咲き乱れる寺院
ーーー↓
大和
七福八宝めぐり
三輪明神、長谷寺、信貴山朝護孫子寺、
當麻寺中之坊、安倍文殊院、
おふさ観音、談山神社、久米寺の一つ
創建年
1650年(慶安三年)4月
開基
妙円尼
別称
積の観音さん
ーーー↓
餝摩の市。・・・・・・餝摩(しかま)=食+芳+麻+手
消滅直前の時点では
姫路市を南北に挟む形で、
内陸部に位置する
夢前町と沖合いに位置する
家島町(家島諸島)との
二町で構成されていた
飾磨郡(しかまぐん・しかまのこおり)は、
播磨国の郡の1つ。
また、
1896年~2006年まで
兵庫県の南部にあった郡。
ーーー↓
飛鳥の市。・・・・・・飛鳥(あすか・ヒチョウ→秘帳)
奈良県
高市郡
明日香村
大字
飛鳥
---↓
大阪府
羽曳野市
及び
太子町あたりの地域名
---↓
二つの飛鳥を区別
河内国(大阪府)の飛鳥は
「近つ飛鳥」・「河内飛鳥」
大和国(奈良県)の飛鳥は
「遠つ飛鳥」・「大和飛鳥」と
よばれた・・・
ーーーーー
「いち・シ」は、いと、をかし・・・幕末明治の「こつじき」・・・推してしるべし・・・「こじき」カナ・・・
ーーー↓
垂仁天皇
崇神天皇二十九年一月一日~垂仁天皇九十九年七月十四日)
第十一代天皇
在位は垂仁天皇元年一月二日~垂仁天皇九十九年七月十四日)
活目入彦五十狭茅尊(いくめいりびこいさちのみこと)
活目尊
「古事記」は「伊久米伊理毘古伊佐知命(いくめいりびこいさちのみこと)」
「常陸国風土記」は「伊久米天皇」
「令集解・所引・古記」は「生目天皇」
「上宮記・逸文」は「伊久牟尼利比古(いくむにりひこ)大王」
父は「崇神天皇」
子に「倭姫命」・・・大和秘めの名
ーーー↓
古事記原文
亦
天皇、命詔
其后言、
凡
子
名、
必
母名、
何稱
是子之御名。
爾
答白、
今當
火燒
稻城
之
時而、
火中所生。
故、
其
御名
宜稱
本牟智和氣御子。
ーーー↑
何故、「火中所生」が「本牟智和氣御子」の名前と関連するのか?・・・これは前文の
「稻城・・・・・イナギ→異名義・伊名義・否義
之・・・・・・シ→詞、史、師、士、死・氏・至・・・市
時而」・・・・時(とき・ジ)・而(しこうして・しかも・ジ・ニ)
ジジ=時事・次次・次々・爺
が、その「理由」である・・・「伊藤博文」である、カナ・・・
ーーーーー
(一四段)・・・十四段・壱拾四段・壱四段・壱拾肆(長+聿)
市は
辰(たつ)の市。・・・辰刻(七~八時)・龍→劉・隆・留・立
椿市は、・・・・・・・つばき→通葉記・・・唾(口+垂)
大和に・・・・・・・・ダイワに→拿意話似
數多・・・・・・・・・スウタ→数他・崇多
↓
崇神天皇・大多田根子(大三輪氏の祖)
大田田根子命
意富多々泥古命
ある中に、
長谷寺に・・・・・・・「長国事・兆国次・超克時・帳国字」似
まうづる人の、・・・・毎鶴の人
かならず・・・・・・・掛名等事
そこに
とど・・・・・・・・・トド・鯔・椴・百々
まり・・・・・・・・・真理・万理・鞠・毬・麿・麻呂
ければ、・・・・・・・仮例葉
觀音の・・・・・・・・観れ音を
御縁ある・・・・・・・音宛
にやと、・・・・・・・似也止
心・・・・・・・・・・シンの同音漢字のスベテ
こと・・・・・・・・・異
なる・・・・・・・・・鳴る
なり。・・・・・・・・名理
ーーー↓
おふさの市。・・・・・負ふさ埜一
おふさ観音バラまつり
春と秋に開催
イングリッシュ・ローズ等の薔薇市
おふさ観音=火寺のある地名と合わせて
「小房(おふさ) 観音」と呼ばれている
正式名は高野山真言宗別格本山観音寺
本尊は
十一面観音
奈良県
橿原市
小房(おうさ)町の寺院通称名
山号は
十無量山
正式名称は高野山
真言宗
別格
本山
十無量山
観音寺
英国薔薇(イングリッシュローズ種)が
境内に咲き乱れる寺院
ーーー↓
大和
七福八宝めぐり
三輪明神、長谷寺、信貴山朝護孫子寺、
當麻寺中之坊、安倍文殊院、
おふさ観音、談山神社、久米寺の一つ
創建年
1650年(慶安三年)4月
開基
妙円尼
別称
積の観音さん
ーーー↓
餝摩の市。・・・・・・餝摩(しかま)=食+芳+麻+手
消滅直前の時点では
姫路市を南北に挟む形で、
内陸部に位置する
夢前町と沖合いに位置する
家島町(家島諸島)との
二町で構成されていた
飾磨郡(しかまぐん・しかまのこおり)は、
播磨国の郡の1つ。
また、
1896年~2006年まで
兵庫県の南部にあった郡。
ーーー↓
飛鳥の市。・・・・・・飛鳥(あすか・ヒチョウ→秘帳)
奈良県
高市郡
明日香村
大字
飛鳥
---↓
大阪府
羽曳野市
及び
太子町あたりの地域名
---↓
二つの飛鳥を区別
河内国(大阪府)の飛鳥は
「近つ飛鳥」・「河内飛鳥」
大和国(奈良県)の飛鳥は
「遠つ飛鳥」・「大和飛鳥」と
よばれた・・・
ーーーーー
「いち・シ」は、いと、をかし・・・幕末明治の「こつじき」・・・推してしるべし・・・「こじき」カナ・・・