これは、おもしろい。本書は文芸春秋創業65周年・菊池寛生誕100年
記念として、昭和63(1988)年にまとめられ、発刊されたものだ。
文芸春秋社は大正12(1923)年創業。菊池寛は、明治21(1888)年
の生まれ(小泉信三と同い年である)。
「おもしろい」ところは、例えば、どこでもいいのだが、「昭和12年」の
ページをめくると、
○組閣工作の109時間(宇垣一成)S29/7号
○学生の知能低下に就いて(三木 清)S12/5
○近衛文麿論(阿部真之助)S12/7
○日支両国青年座談会(日中青年9氏)S12/9
○通州の日本人大虐殺(安藤利男)S30/8
○中学英語全廃論(藤村 作)S13/2
という記事が再録されている。
戦後になって書かれたものもあるが、多くはその当時、文芸春秋の掲載
されたものなので、当時を「現代史」として読むことができる。まことに
おもしろい。--一般に、戦後になって、私は戦争に反対だった式の論は
おもしろくない。
「昭和47年」には、
○わたしの憂国記(横井庄一)S47/11
○重信房子の父として(重信末夫)S47/8
○蓮見喜久子・過去からの証人(澤地久枝)S49/6
○今だから話そう(佐藤栄作)S48/1
が取り上げられている。
佐藤栄作は、総理大臣当時、佐藤「無策」だなどと批判されたが、当たり
前のことながら、総理大臣として「実力」があった。「今だから話そう」を
読んでも、なるほどと思うところが多い。
「昭和60年」には、
○地獄からの生還(吉崎博子)S60/10号
○日米の狭間に生きた30年(鈴木茂男)S60/9
○「靖国批判」の中の北京(山崎豊子)S61/4
の3点が掲載されている。
上記の「日米の狭間に生きた30年」の執筆者は、「駐日アメリカ大使館
の広報文化交流局報道部に長年勤務した人」である。駐日アメリカ大使
館勤務、30年の体験談だけあって、具体的な話満載でおもしろい。
ちなみに、この執筆者は、私の母方の伯父であり、生前はかわいがって
もらい、お世話になった。伯父は私のことを、英米風に、名前を呼びつけ
にしていた。
三巻セット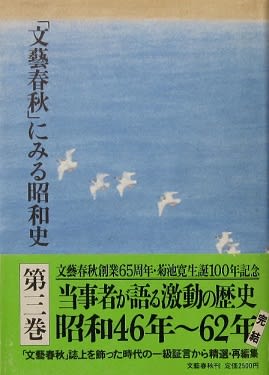
『「文藝春秋」にみる昭和史』第三巻
本書はむろん絶版だが、文庫の中古本がamazonなどで安価で入手
できるようだ。おすすめである。
最新の画像[もっと見る]
-
 5/13-14 杉原歯科 ラウンジ懇話会(自由懇談)
3時間前
5/13-14 杉原歯科 ラウンジ懇話会(自由懇談)
3時間前
-
 5/13-14 杉原歯科 ラウンジ懇話会(自由懇談)
3時間前
5/13-14 杉原歯科 ラウンジ懇話会(自由懇談)
3時間前
-
 5/13-14 杉原歯科 ラウンジ懇話会(自由懇談)
3時間前
5/13-14 杉原歯科 ラウンジ懇話会(自由懇談)
3時間前
-
 5/13-14 杉原歯科 ラウンジ懇話会(自由懇談)
3時間前
5/13-14 杉原歯科 ラウンジ懇話会(自由懇談)
3時間前
-
 5/13-14 杉原歯科 ラウンジ懇話会(自由懇談)
3時間前
5/13-14 杉原歯科 ラウンジ懇話会(自由懇談)
3時間前
-
 5/13-14 杉原歯科 ラウンジ懇話会(自由懇談)
3時間前
5/13-14 杉原歯科 ラウンジ懇話会(自由懇談)
3時間前
-
 5/13-14 杉原歯科 ラウンジ懇話会(自由懇談)
3時間前
5/13-14 杉原歯科 ラウンジ懇話会(自由懇談)
3時間前
-
 5/13-14 杉原歯科 ラウンジ懇話会(自由懇談)
3時間前
5/13-14 杉原歯科 ラウンジ懇話会(自由懇談)
3時間前
-
 5/13-14 杉原歯科 ラウンジ懇話会(自由懇談)
3時間前
5/13-14 杉原歯科 ラウンジ懇話会(自由懇談)
3時間前
-
 5/13-14 杉原歯科 ラウンジ懇話会(自由懇談)
3時間前
5/13-14 杉原歯科 ラウンジ懇話会(自由懇談)
3時間前

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます