
団子下げは稲作の成功を願う「予祝行事」のひとつだそうです。
団子の木は普通ミズキ(水木)といわれる赤味を帯びた茶色の木を使います。
この木の枝や枝先にいろいろなものを飾り付けて、茶の間などに取り付けて秋のみのりが立派になることを願うと言う訳です。
各家庭では、木の枝先には餅米を付け、枝の途中にはふな菓子を下げ、茶の間の大黒柱やえびす神・大黒神をまつる神棚の脇の柱に飾り付けられます。
団子の木の取り付けは1月15日に行います。20日におろして食べるという家が多く、正月の終わりを祝う意味があります。団子下げは、このように昔から伝わる伝統行事でどこの家庭でも行っていたものです。
しかし、今では子供も少なくなってきたせいか、各家庭で余り行われなくなってしまいました。この伝統行事を大事にしようと、当地区では高橋長三さんたち有志が中心となって「団子下げ保存会」を作りながらこの行事を毎年行って来ました。
伝統行事は、親から子へ、子から孫へと絶え間なく伝えていかなければ何時か途切れてしまいます。今後ともこのような素晴らしい伝統の団子下げを金山に伝承して行きたいものです。
団子の木は普通ミズキ(水木)といわれる赤味を帯びた茶色の木を使います。
この木の枝や枝先にいろいろなものを飾り付けて、茶の間などに取り付けて秋のみのりが立派になることを願うと言う訳です。
各家庭では、木の枝先には餅米を付け、枝の途中にはふな菓子を下げ、茶の間の大黒柱やえびす神・大黒神をまつる神棚の脇の柱に飾り付けられます。
団子の木の取り付けは1月15日に行います。20日におろして食べるという家が多く、正月の終わりを祝う意味があります。団子下げは、このように昔から伝わる伝統行事でどこの家庭でも行っていたものです。
しかし、今では子供も少なくなってきたせいか、各家庭で余り行われなくなってしまいました。この伝統行事を大事にしようと、当地区では高橋長三さんたち有志が中心となって「団子下げ保存会」を作りながらこの行事を毎年行って来ました。
伝統行事は、親から子へ、子から孫へと絶え間なく伝えていかなければ何時か途切れてしまいます。今後ともこのような素晴らしい伝統の団子下げを金山に伝承して行きたいものです。

















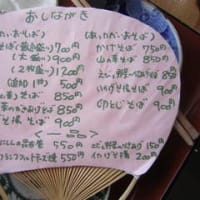


今年は、子供たちが、枝もぎから団子つくり、賄かないものの配膳まで主体的に行ってくれてとっても良かった。
久しぶりに若い力をもらったような気がした。
ありがとう!