鹿児島県 大口市針持
以前はJR宮之城線がすぐ近くを通っていたようです。この路線は1987年に廃止になっており、ここから少し東に歩いたところに「針持駅跡」という公園があります。
山間部ですが広々とした田園を眺めるようにして、針持の田の神さぁは立っておられました。
シキをかぶっていますが、衣装はどちらかというと神職像に似ています。右手には何か持物があったのでしょうか、やや上に上げてポーズをとっています。
銘文が無いのでいつ頃に造立された田の神さぁであるのかわかりません。ただ、風化の具合からすると江戸時代まで遡るかもしれません。
鹿児島ではもう、刈り入れもほとんど済んでいるでしょうか。この季節に田の神さぁを訪れると田圃では刈り入れ作業をされる農家の方々も多く、田の神さぁの周りが急に賑やかになったような気がして、何故か嬉しい気持ちになります。


刈り入れ時の田圃を眺める田の神さぁ
「にほんブログ村・ブログランキング」に参加しています
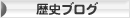

以前はJR宮之城線がすぐ近くを通っていたようです。この路線は1987年に廃止になっており、ここから少し東に歩いたところに「針持駅跡」という公園があります。
山間部ですが広々とした田園を眺めるようにして、針持の田の神さぁは立っておられました。
シキをかぶっていますが、衣装はどちらかというと神職像に似ています。右手には何か持物があったのでしょうか、やや上に上げてポーズをとっています。
銘文が無いのでいつ頃に造立された田の神さぁであるのかわかりません。ただ、風化の具合からすると江戸時代まで遡るかもしれません。
鹿児島ではもう、刈り入れもほとんど済んでいるでしょうか。この季節に田の神さぁを訪れると田圃では刈り入れ作業をされる農家の方々も多く、田の神さぁの周りが急に賑やかになったような気がして、何故か嬉しい気持ちになります。


刈り入れ時の田圃を眺める田の神さぁ
「にほんブログ村・ブログランキング」に参加しています






























