和歌山市 紀三井寺
自転車で和歌山市内へ出掛けたときに、紀三井寺の前を通りかかりました。
紀三井寺といえば正月は初詣の参詣者で賑わうところで、境内には文化財指定を受けた建築がいくつもあります。
室町時代・永正6年(1509年)建立の建築として国指定文化財となっている朱色の楼門から階段を上がっていくのが本来の参拝順路のようですが、今日は残念ながら時間が無くて境内へはよりみちできず、楼門を見ながら前を通り過ぎるだけにしました。
ところが、その楼門を通り過ぎてからすぐ、奇麗な彫刻で飾られた門を見かけました。境内に続く参道の一つの入り口にあたる場所ですから、紀三井寺に関係がある建築のようです。
どうやらもともと、ほかの場所にあったものらしいのですが、いつ頃のものかはよく分りません。
江戸時代以降とは思いますが…。
木鼻や斗供のつくりも面白いのですが、松に鳥、龍や獅子などは非常に精緻で、一部は破損していますが、木の質感もあって、こんな場所にこんな建築が残されているのはちょっと意外なほどです。
現在、参拝の道路はすぐ脇を通っていて、この門をくぐって山に登るようなことはありませんが、道は境内からずっと続いていますから、参拝のおりにちょっと遠回りしてここまで来てみるのもいいかもしれません。


今回はデジタルカメラがなくて携帯電話のカメラにて撮影のため、山門全体の写真は撮ることができませんでした。
新年まであと1日、境内にある文化財の建築物の見学も兼ねて、正月は是非ともここに参拝に訪れたいものです。



にほんブログ村」歴史ブログランキングに参加しています
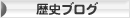


自転車で和歌山市内へ出掛けたときに、紀三井寺の前を通りかかりました。
紀三井寺といえば正月は初詣の参詣者で賑わうところで、境内には文化財指定を受けた建築がいくつもあります。
室町時代・永正6年(1509年)建立の建築として国指定文化財となっている朱色の楼門から階段を上がっていくのが本来の参拝順路のようですが、今日は残念ながら時間が無くて境内へはよりみちできず、楼門を見ながら前を通り過ぎるだけにしました。
ところが、その楼門を通り過ぎてからすぐ、奇麗な彫刻で飾られた門を見かけました。境内に続く参道の一つの入り口にあたる場所ですから、紀三井寺に関係がある建築のようです。
どうやらもともと、ほかの場所にあったものらしいのですが、いつ頃のものかはよく分りません。
江戸時代以降とは思いますが…。
木鼻や斗供のつくりも面白いのですが、松に鳥、龍や獅子などは非常に精緻で、一部は破損していますが、木の質感もあって、こんな場所にこんな建築が残されているのはちょっと意外なほどです。
現在、参拝の道路はすぐ脇を通っていて、この門をくぐって山に登るようなことはありませんが、道は境内からずっと続いていますから、参拝のおりにちょっと遠回りしてここまで来てみるのもいいかもしれません。


今回はデジタルカメラがなくて携帯電話のカメラにて撮影のため、山門全体の写真は撮ることができませんでした。
新年まであと1日、境内にある文化財の建築物の見学も兼ねて、正月は是非ともここに参拝に訪れたいものです。



にほんブログ村」歴史ブログランキングに参加しています

















































 塀の断面を見ることができるようになっています
塀の断面を見ることができるようになっています こちらは落水園を囲む博多塀です。
こちらは落水園を囲む博多塀です。



