佐賀県内と福岡の一部の神社ではよく、
「肥前狛犬」
と呼ばれる小さな狛犬を見かけます。
その大きさや形態からすぐにそれとわかり、全国的に見られる狛犬像からすると明らかに異なる一群の狛犬像です。
神社の鳥居をくぐり、賽銭を投げ入れてから手を合わせる…ところで、
「こんなところに」と本殿の前に見つけてしまうこともあります。

本殿の前の肥前狛犬。(神埼市内で)
気が付けばこんなところに座っていました。
像高はたいてい30~35cmほどで、ほとんどが古い時代のものであるらしく、また風化による摩滅もあってそれほど目立ちませんが、しかしすぐにこのかわいらしい犬の視線に気が付きます。中国では獅子を表現していた像が、日本においては犬と表現されたのも、昔から日本人にとっては、時として番犬などのように生活を助ける犬がとても身近な存在であったのかもしれません。
神社の神様の、小さな守り神というのが似合いそうに思えます。
トップに貼った写真と、以下の写真は長崎街道沿いの神社(道祖神社-佐賀市道祖元町(さやのもとまち))で見つけた肥前狛犬です。

こちらは右側にすわっているほうで、位置から言えば「阿形」ということになります
像の小ささからか、参道の両脇ではなくより本殿の近く、本殿入り口の両脇に座っているのをよく見かけます。
参拝者からみると、足元に見下ろす形になるからだとも考えられますが、その表情は特に上面に表現されることが多いようです。一般的な狛犬よりも、前方上方を意識した彫刻となっているような気がします。


直立した両前脚の表現は、日本で最古とされる東大寺南大門の狛犬に似ています。
足元がコンクリート埋もれているのは、しっかりと固定しすぎのような気がしますが…。
肥前狛犬に記銘があるものは非常に少なく、制作年代は特定できない例がほとんどです。
佐賀は長崎が近く長崎街道沿いであるせいか、狛犬はいわゆる”唐獅子”も多いのですが、肥前狛犬はそういった狛犬よりも古くからあるとされています。
全国的に、神社を守る石像狛犬が多く作られ始めるのは江戸時代の中頃からと言われますので、
肥前狛犬の多くは、その制作時期が江戸時代の初めから中頃までと推定される、ということになります。

「にほんブログ村」歴史ブログランキングに参加しています
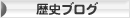
「肥前狛犬」
と呼ばれる小さな狛犬を見かけます。
その大きさや形態からすぐにそれとわかり、全国的に見られる狛犬像からすると明らかに異なる一群の狛犬像です。
神社の鳥居をくぐり、賽銭を投げ入れてから手を合わせる…ところで、
「こんなところに」と本殿の前に見つけてしまうこともあります。

本殿の前の肥前狛犬。(神埼市内で)
気が付けばこんなところに座っていました。
像高はたいてい30~35cmほどで、ほとんどが古い時代のものであるらしく、また風化による摩滅もあってそれほど目立ちませんが、しかしすぐにこのかわいらしい犬の視線に気が付きます。中国では獅子を表現していた像が、日本においては犬と表現されたのも、昔から日本人にとっては、時として番犬などのように生活を助ける犬がとても身近な存在であったのかもしれません。
神社の神様の、小さな守り神というのが似合いそうに思えます。
トップに貼った写真と、以下の写真は長崎街道沿いの神社(道祖神社-佐賀市道祖元町(さやのもとまち))で見つけた肥前狛犬です。

こちらは右側にすわっているほうで、位置から言えば「阿形」ということになります
像の小ささからか、参道の両脇ではなくより本殿の近く、本殿入り口の両脇に座っているのをよく見かけます。
参拝者からみると、足元に見下ろす形になるからだとも考えられますが、その表情は特に上面に表現されることが多いようです。一般的な狛犬よりも、前方上方を意識した彫刻となっているような気がします。


直立した両前脚の表現は、日本で最古とされる東大寺南大門の狛犬に似ています。
足元がコンクリート埋もれているのは、しっかりと固定しすぎのような気がしますが…。
肥前狛犬に記銘があるものは非常に少なく、制作年代は特定できない例がほとんどです。
佐賀は長崎が近く長崎街道沿いであるせいか、狛犬はいわゆる”唐獅子”も多いのですが、肥前狛犬はそういった狛犬よりも古くからあるとされています。
全国的に、神社を守る石像狛犬が多く作られ始めるのは江戸時代の中頃からと言われますので、
肥前狛犬の多くは、その制作時期が江戸時代の初めから中頃までと推定される、ということになります。

「にほんブログ村」歴史ブログランキングに参加しています





























