ちょうど新型インフルエンザが世界中に拡大している中でしたので、出発の空港からマスク持参で出かけました。
今回仕事で韓国まで行くことになって「天吹を思い出した、」
というのはそのとおりなのですが、
実は、天吹と韓国は今のところ、まったく関わりがないのです。
ただ、以前に「韓国には、天吹に似た笛がある、…」という話を聞いたことがあったので、「それではその笛を確かめてこよう。」と考えて、今回の仕事の合間に、ちょっと探してくることにしたのです。
今回宿泊したホテルの案内の方がとても親切で、楽器店の場所まで詳しく調べてくれたので、ハングルの全く分からない私でも道に迷うこともなく楽器店までたどり着き、その「タンソー(ダンソー)」を手にとることができました。
表に4孔、裏に1孔という、細い竹でできた笛は、現在韓国に2種類あるということです。
一つは「トゥンソー」といい、もう一つは「ダンソー」あるいは「タンソー」という笛です。
ただし、「トゥンソー」というのは横笛で、天吹と同じ縦笛は「ダンソー」のほうです。見てみると確かに尺八によく似ています。
吹いてみれば、以外にも音は天吹よりもずっと低く感じられ、音域もそれほど広いとは思えません。
以前天吹を作った際に気になったことですが、笛の中にある節に穴をあける際、材料は竹ですから、節のところを上から下まで貫通させないと、笛にはなりません。)この部分、息が抜けるための孔はとても小さく空けるだけなのです。
しかしこうすることで、孔を指でふさぐ際に変わる音の高低の差が、よりはっきりしてきます。
表現力が増す、ということにも繋がるでしょうか。
一般的に笛から鳴る音の高さは、歌口から一番初めの孔までの距離が長いほど、低くなっていきますが、天吹の音色、この笛の一番下に来る節にどれくらいの大きさの穴をあけるか、とうことにも深く関わっていそうです。


実際、「タンソー」のほうはこの孔が大きくなっており、また歌口から第1孔までの距離も長く作られていることから、演奏できる音は全体的に低くなっていると思われます。
そういったわけで、天吹と同じように孔を押さえて吹いてみても、天吹と同じ音階にはならず、まったく別の楽器で演奏しているように聞こえます。
この「タンソー」が、いつ頃から韓国に伝えられているのか、またどういった曲があって、それがどういうふうにで演奏されるのか、といったことは今後調べてみたいと思いますが、やはり天吹とタンソー、それぞれに演奏される曲の間にも、やはりかなりの違いがありそうです。
にほんブログ村」歴史ブログランキングに参加しています
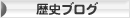



今回仕事で韓国まで行くことになって「天吹を思い出した、」
というのはそのとおりなのですが、
実は、天吹と韓国は今のところ、まったく関わりがないのです。
ただ、以前に「韓国には、天吹に似た笛がある、…」という話を聞いたことがあったので、「それではその笛を確かめてこよう。」と考えて、今回の仕事の合間に、ちょっと探してくることにしたのです。
今回宿泊したホテルの案内の方がとても親切で、楽器店の場所まで詳しく調べてくれたので、ハングルの全く分からない私でも道に迷うこともなく楽器店までたどり着き、その「タンソー(ダンソー)」を手にとることができました。
表に4孔、裏に1孔という、細い竹でできた笛は、現在韓国に2種類あるということです。
一つは「トゥンソー」といい、もう一つは「ダンソー」あるいは「タンソー」という笛です。
ただし、「トゥンソー」というのは横笛で、天吹と同じ縦笛は「ダンソー」のほうです。見てみると確かに尺八によく似ています。
吹いてみれば、以外にも音は天吹よりもずっと低く感じられ、音域もそれほど広いとは思えません。
以前天吹を作った際に気になったことですが、笛の中にある節に穴をあける際、材料は竹ですから、節のところを上から下まで貫通させないと、笛にはなりません。)この部分、息が抜けるための孔はとても小さく空けるだけなのです。
しかしこうすることで、孔を指でふさぐ際に変わる音の高低の差が、よりはっきりしてきます。
表現力が増す、ということにも繋がるでしょうか。
一般的に笛から鳴る音の高さは、歌口から一番初めの孔までの距離が長いほど、低くなっていきますが、天吹の音色、この笛の一番下に来る節にどれくらいの大きさの穴をあけるか、とうことにも深く関わっていそうです。


実際、「タンソー」のほうはこの孔が大きくなっており、また歌口から第1孔までの距離も長く作られていることから、演奏できる音は全体的に低くなっていると思われます。
そういったわけで、天吹と同じように孔を押さえて吹いてみても、天吹と同じ音階にはならず、まったく別の楽器で演奏しているように聞こえます。
この「タンソー」が、いつ頃から韓国に伝えられているのか、またどういった曲があって、それがどういうふうにで演奏されるのか、といったことは今後調べてみたいと思いますが、やはり天吹とタンソー、それぞれに演奏される曲の間にも、やはりかなりの違いがありそうです。
にほんブログ村」歴史ブログランキングに参加しています




















